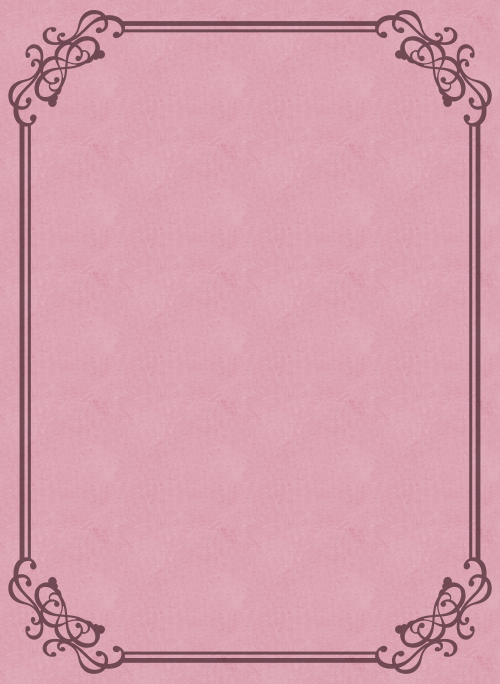母が落ち着いた声で、私の肩に手を置いた。
「ごめんね、隠してて」
混乱はしているけど、別に隠していたことを怒っているわけじゃない。
ただ、脳が追いつかない。
父はそんな私を見て、小さく笑った。
「胡桃、今まで黙っていて悪かった。……胡桃には、人間として普通に生きてほしかったんだ」
『……普通に生きる……?』
なんか深刻そうに言ってるけど、こっちはただ状況が急展開すぎてまだ頭がついていかない。
父の声音は今まで聞いたことのないような重い雰囲気をまとっていた。
「吸血鬼の世界は……綺麗なものじゃない。人間として生まれたからにはこっちのいざこざなんて知らない方がいいし、巻き込みたくなかったんだ」
父の低く静かな声が、病室の壁に染み込むように響く。
静かに告げられたその言葉に胸の奥がざわめいた。
……でも。
『……なら、何で白星学園に……吸血鬼がいる寮に私を入れたの?』
父と母の考えとして、私を守ろうとしていたのは分かる。きっとそれは愛情だったのだと思う。
でもそれなら…私をこの学園に転校させた事との辻褄が合わない。
母が小さく肩で息をつき、苦笑するように表情を緩める。
そして私の肩にそっと手を置いた。
「最初は反対したのよ。危ないって」
その手は温かく、優しい。
けれど、掌の奥にわずかな強張りが伝わってきた。
「……仕事の関係でこっちに来ないといけなくなった。でも胡桃を一人残していくのは心配だったし……。前の街には吸血鬼はほとんどいなかったから警戒してなかったけど、こっちに越すとなると話が変わってくる」
父はそう言って視線を伏せ、一拍置いてからゆっくりと口を開いた。
「純混血である以上、完全に隠しきることはできない。匂いに敏感な吸血鬼にはいずれ見抜かれる」
その一言に、心臓がぎゅっと掴まれた気がした。
……実際、叶兎くんや春流くんにだって、あっという間に見抜かれていた。
私の動揺を見透かしたように、父の声音が少しだけ柔らかくなる。
「だからこそ、信頼できる者たちのそばに置いた方が安全だと思った」
視線がすっと横へ移る。
その視線の先は…叶兎くんだった。