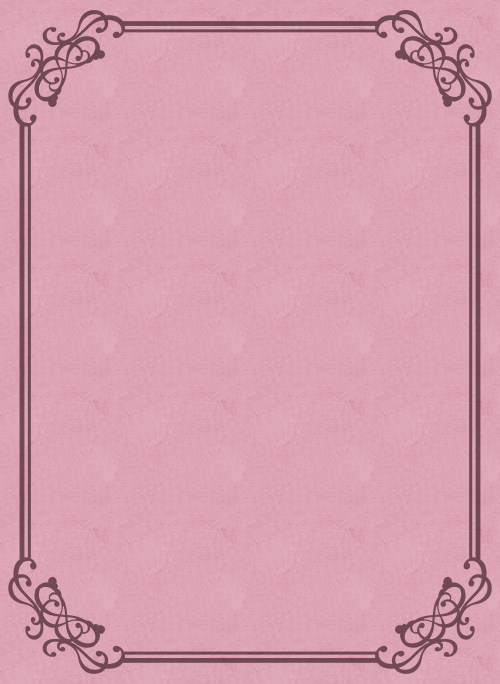『……っ、離して!』
「…。」
精一杯抵抗して体をよじる。
強引に立ち上がると肩のあたりからじわりと血が滲むのが分かったけど、そんなことを気にしている余裕はない。
『っ私、帰る』
きっと今頃…みんな心配してる。
だから一刻も早く学園に戻りたい。
それに、なんだか私はここにいてはいけない気がした。
「帰る?どこに?」
『学園に帰るの!』
視線の先にあるドアを見た。
鍵はかかっていない……走れば、逃げられるかもしれない。
足に力を込めようとした、その時。
「ふぅん、…やっぱり僕のことなんてどうでもいいんだ?」
『そういう意味じゃ…』
そういう言い方をされるとなんて返したらいいのかわからない。
別に、朔がどうとかそういう問題じゃないし…、
そもそも強引に連れてきたのはそっちでしょ。
「…行かないで、」
掴まれた腕が熱い。
その声があまりにも弱々しくて、顔を上げれば、朔が悲しそうに私を見ていた。
………どうして、そんな目で見るの。