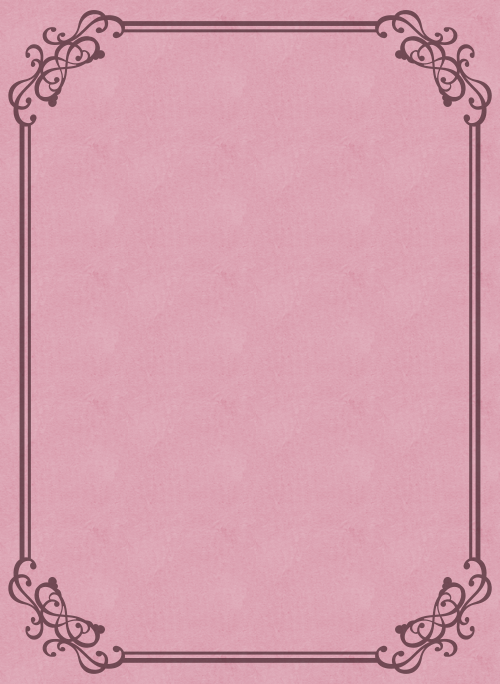『……。』
「甘い匂いがする。これが純混血の血の匂い…」
『朔、どうしてこんなことするの?』
「こんなこと?…だって、くーちゃんが僕の誘いを断るからこうやって連れてくるしかなかったんだよ」
“連れてくるしかなかった”って…
私の意見は最初から聞くつもりがない言い方だ。
「くーちゃんだって僕とまた会えて嬉しいでしょ?」
『それは…そうだけど…』
朔にまた会えたのが嬉しくないかといえば嘘になる
けど、こう言う形は望んでない。
「これからは一緒にいよーね」
『え、それ、どういう…』
その笑顔が、怖い。
その声は甘やかで、けれど逃げ場を与えない檻のようでもあった。
視線は優しいのに、向けられたその視線に少し、狼狽えてしまいそうになる。