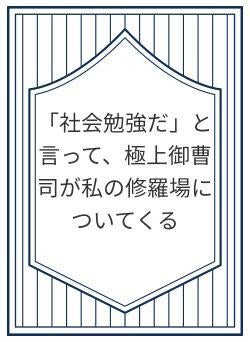こんな時。ちょうど夕方に差し掛かる、いったん客足が途絶え店内が落ち着くわずかな時間。
ふと。僕の想い続ける彼女は、いまどんな姿かたちになっているんだろうと考える。
カウンターに立ち、フードの数をかぞえ発注シートに記入しているうちにぼんやりしてしまう。
僕のなかで、彼女の姿は十八歳のままで止まっている。
肩で切り揃えたボブを揺らして、嬉しそうに紙パックのいちご牛乳を飲む横顔をよく覚えてる。
ベランダで友達と喋りながら、チラチラとその教室での姿を目で追った。
たまに目が合うと彼女が眉を下げて笑うので、僕はあわてて下を向く。
うるさい心臓の音が、誰にも聞こえないように願う。帰りには、さりげなく自販機でいちご牛乳を買ってから帰った。
ひとりの帰り道。いちご牛乳を飲みながら、こっそり彼女の唇の柔らかさを想像した。
こんなにも胸を焦がし、いまだに強く惹かれている理由が自分にもわからない。
わからないというより、たくさんあり過ぎるのかもしれない。
言葉にするのは難しい、フィーリングみたいなものも合っていた気がする。
これが好き、という気持ち。
これが、恋。
その初恋を見事に拗らせ、ついに八年目に突入してしまった。
彼女だって、ただのクラスメイトだった僕なんか、とっくに忘れているはずだ。
まだ二十五歳、されど二十五歳。もしかしたら結婚をしているかもしれない。
もしかしたら.......初恋はとうとうおばけになって、拗らせた僕を祟っているのだろうか。
制服を着た彼女の姿をしたおばけを想像しながら、カウンター内で冷蔵ケースの温度チェックをするために、よいしょとしゃがむ。
そのタイミングでお客さまが入ってきたようで、素早く斎藤くんがレジに入ってくれた。
斎藤くんの隣から急にニュっと立ち上がるのも悪くて、お会計が済むのを待つことにした。
少しつらい体勢だけど、来週に控えた定期的なスタッフとの二者面談材料の話題になるいい機会だ。
「こんにちは! 今日はちょっと冷えましたね」
三月に入っても、まだ肌寒い日が突然やってくる。今日なんかも、朝はなかなかベッドから出られなかった。
斎藤くんは元からコミュニケーションは得意なほうだったので、お客さまとの会話のきっかけ作りがうまい。
足元で小さくなる上司を一切気にしないそぶりは、ベテラン感すらある。
「そうですね、今朝は手袋を置いて出勤したので、途中で後悔しちゃいました」
女性のお客さまからも、ぽんっと気持ちのよい返事が返ってきた。
こちらからはまったく姿はみえない。
でも、なんだろう。妙に胸がざわざわする。
.......あれ、この声にかすかに聞き覚えがある?
「じゃあ、今日は温かい飲み物のほうがいいですか?」
「そうですね、ドリップコーヒーも飲みたいけど.......クリーム感も欲しいかも。でもココアだと重くて」
「では、ドリップコーヒーにスチームミルクをのせるのはどうでしょう。ナッツのシロップを追加すると、風味も香りも増して美味しいですよ」
「あっ、それいいですね!」
弾んだ声が、ガシッと僕の心臓をわし掴む。
疑問は懐かしい学生時代の記憶を呼び起こし、どんどん確信へと変わっていく。
このカウンターのむこうに。
もしかしたら。
「.......は、ははっ」
しゃがんでいた足腰から一気に力が抜けて、その場に尻もちをついてしまった。
「あっ、はるさん?! どうしたんですか、足が痺れちゃったんですかー?」
斎藤くんが、笑いながらしゃがみ、よいしょと思わぬ怪力で僕を立ち上がらせる。
そこからはスローモーションだった。
ゆっくりと一コマ一コマが、答え合わせのように流れていく。
僕をみる、その印象的な大きな目。
みつけた時から何度も思い出した、口元のちいさなほくろ。
あの頃ボブだった髪は、いまはセミロングになっていた。
ふっくらした頬はシャープになり、メイクもしてうんと綺麗な大人の女性になって·····目を丸くして突然現れた僕をみている。
春の優しい風によく似合う、そんなリップで彩られた唇が動く。
「·····間部くん·····だよね?」
もしかして、なんて付けずに一発で僕の名前を言い当てる。
あ、眉が下がる癖だ。
僕の顔を再度みて、表情をゆるめる。
「やっぱり、間部くんだ! 私のこと覚えてるかな.......って、やっぱり八年も経ったら忘れちゃったよね」
まるで、忘れられていることが当たり前のように。すらりとそんな言葉が出てくるのは、何度も繰り返したセリフなんだろうか。
「私の名前、近成ありさだよ。高校のときにクラスメイトだったんだけど転校して.......」
知ってる、知ってるとも。
その名前を心のなかで何度呼んだか。
忘れるわけない、僕のいまでも絶賛継続中の初恋の相手だ。
「.......近成さん」
「ふふ、もしかして、思い出してくれたとか?」
「文化祭の買い出し係が一緒になって、買い物のあとになぜか近成さんの親戚の家に寄って」
「あはは! そうそう、親戚が留守のあいだの犬の世話を頼まれててね。犬の散歩に付き合ってもらったよね」
訳もわからずに、ドキドキしながら近成さんと犬のうしろをついて歩いた思い出だ。
二人きり、時々喋って、また歩く。犬を家に戻して、学校へ戻った。
実質、デートだろ!と、その日は浮かれて眠れない夜を過ごした。
色褪せ始めた思い出に、嵐のように咲き乱れはじめた花がまた彩色していく。
僕の顔も、赤く染め上げられてしまった。
ああ、この日のために、この瞬間のために頑張ってきたのに。
感極まって、次の言葉が出てこない。
情けなくも固まってしまった俺に、斎藤くんは「はるさんって、感動屋さんなんですね!」と背中を思いっきり叩いてきた。
「ねぇ、斎藤くん」
「なんですか?」
「女の子って、シナモンロールが好きなんだよね? でもそれって、みんなが好きなのかな。困らないで、貰ってくれるものなのかな」
「すごい早口になってますよ.......そういうのって、はるさんの方がよく知ってるんじゃないんですか? お客さんと、よく喋ってるじゃないですか」
「.......なんか、接客で積み重ねてきたもの全部、さっき吹き飛んだ.......」
近成さんは飲み物を受け取ると、奥の空いた席を探して座った。
僕はもうカチコチになってしまい、そのあとはまともな会話にならなかった。
斎藤くんがカウンターに立っているあいだ、アイスコーヒーの為の豆を挽く。
膝ががくがくしてる気もするけど、仕事はきちんとしなければならない。
「つまりはるさんは、さっき久しぶりに会ったあのお客さんに、いま差し入れしたいんですね?」
「.......うん。だけど、好きな食べ物とかわからないし。お腹いっぱいかもしれない」
ため息と一緒に、一気に吐き出す。
「はるさん。そういうときは、食べきれない分は持って帰れますって言うんですよ。一緒に紙袋と紙ナプキンを渡しちゃえば、判断はあっちが自分でしてくれます」
普段なら、イートインなら紙袋を先に渡すことはない。持って帰りたいと声をかけられたら、用意するものだ。
でも、そうか。一緒に渡してあげればいいのか。
「斎藤くん、どうしてそんなにすぐ答えが出てくるの」
斎藤くんは、うーんと考える。そして、パッと表情を明るくした。
「あれですね、もし、俺と彼女だったらって考えたんです。どうしようって、もし食べきれなかった物の前で、彼女が気を使って悩んだら可哀想ですもん」
「男前だ.......」
「イケメンのはるさんに言われると、照れちゃいますね。俺、彼女のことが大好きで、めっちゃたくさん考えて頑張ったんです。一度フラれてるので、リベンジして」
「すごい、すごいよ! 僕なんて、言葉も出なければうじうじも始めちゃうし。格好悪いよね。でもいま動かなきゃ、また後悔する」
いまこの瞬間にも、近成さんの飲み物が空になったら帰ってしまうかもしれないんだ。
また、この店に寄ってくれる保証も、その時に僕が居るのかもわからない。
動かなきゃ。
どういう形であれ、いま一歩踏み出さないと。
あんなに後悔したんだから。固まってる場合じゃないぞ。
「.......休憩時間の十五分だけいまから取っていい?」
「いいっすよ。じゃあシナモンロール、先に温めておきますね」
斎藤くんはショーケースをあけて、トングでシナモンロールを掴んだ。
「ありがとう! 支払いはこれで、斎藤くんの彼女の分も好きなだけ買っていいから」
名札の裏から現金がチャージされたカードを斎藤くんに渡し、素早くバックルームでしていたエプロンを脱ぐ。
早く、早く、急げ。
バックルームで作業をしていたスタッフが、僕の勢いに驚いている。
「ごめんね、いまから十五分だけ先に休憩いただきます」
そう言った自分の声がちょっとだけ緊張で震えているから、ひとりで可笑しくなってしまった。
ふと。僕の想い続ける彼女は、いまどんな姿かたちになっているんだろうと考える。
カウンターに立ち、フードの数をかぞえ発注シートに記入しているうちにぼんやりしてしまう。
僕のなかで、彼女の姿は十八歳のままで止まっている。
肩で切り揃えたボブを揺らして、嬉しそうに紙パックのいちご牛乳を飲む横顔をよく覚えてる。
ベランダで友達と喋りながら、チラチラとその教室での姿を目で追った。
たまに目が合うと彼女が眉を下げて笑うので、僕はあわてて下を向く。
うるさい心臓の音が、誰にも聞こえないように願う。帰りには、さりげなく自販機でいちご牛乳を買ってから帰った。
ひとりの帰り道。いちご牛乳を飲みながら、こっそり彼女の唇の柔らかさを想像した。
こんなにも胸を焦がし、いまだに強く惹かれている理由が自分にもわからない。
わからないというより、たくさんあり過ぎるのかもしれない。
言葉にするのは難しい、フィーリングみたいなものも合っていた気がする。
これが好き、という気持ち。
これが、恋。
その初恋を見事に拗らせ、ついに八年目に突入してしまった。
彼女だって、ただのクラスメイトだった僕なんか、とっくに忘れているはずだ。
まだ二十五歳、されど二十五歳。もしかしたら結婚をしているかもしれない。
もしかしたら.......初恋はとうとうおばけになって、拗らせた僕を祟っているのだろうか。
制服を着た彼女の姿をしたおばけを想像しながら、カウンター内で冷蔵ケースの温度チェックをするために、よいしょとしゃがむ。
そのタイミングでお客さまが入ってきたようで、素早く斎藤くんがレジに入ってくれた。
斎藤くんの隣から急にニュっと立ち上がるのも悪くて、お会計が済むのを待つことにした。
少しつらい体勢だけど、来週に控えた定期的なスタッフとの二者面談材料の話題になるいい機会だ。
「こんにちは! 今日はちょっと冷えましたね」
三月に入っても、まだ肌寒い日が突然やってくる。今日なんかも、朝はなかなかベッドから出られなかった。
斎藤くんは元からコミュニケーションは得意なほうだったので、お客さまとの会話のきっかけ作りがうまい。
足元で小さくなる上司を一切気にしないそぶりは、ベテラン感すらある。
「そうですね、今朝は手袋を置いて出勤したので、途中で後悔しちゃいました」
女性のお客さまからも、ぽんっと気持ちのよい返事が返ってきた。
こちらからはまったく姿はみえない。
でも、なんだろう。妙に胸がざわざわする。
.......あれ、この声にかすかに聞き覚えがある?
「じゃあ、今日は温かい飲み物のほうがいいですか?」
「そうですね、ドリップコーヒーも飲みたいけど.......クリーム感も欲しいかも。でもココアだと重くて」
「では、ドリップコーヒーにスチームミルクをのせるのはどうでしょう。ナッツのシロップを追加すると、風味も香りも増して美味しいですよ」
「あっ、それいいですね!」
弾んだ声が、ガシッと僕の心臓をわし掴む。
疑問は懐かしい学生時代の記憶を呼び起こし、どんどん確信へと変わっていく。
このカウンターのむこうに。
もしかしたら。
「.......は、ははっ」
しゃがんでいた足腰から一気に力が抜けて、その場に尻もちをついてしまった。
「あっ、はるさん?! どうしたんですか、足が痺れちゃったんですかー?」
斎藤くんが、笑いながらしゃがみ、よいしょと思わぬ怪力で僕を立ち上がらせる。
そこからはスローモーションだった。
ゆっくりと一コマ一コマが、答え合わせのように流れていく。
僕をみる、その印象的な大きな目。
みつけた時から何度も思い出した、口元のちいさなほくろ。
あの頃ボブだった髪は、いまはセミロングになっていた。
ふっくらした頬はシャープになり、メイクもしてうんと綺麗な大人の女性になって·····目を丸くして突然現れた僕をみている。
春の優しい風によく似合う、そんなリップで彩られた唇が動く。
「·····間部くん·····だよね?」
もしかして、なんて付けずに一発で僕の名前を言い当てる。
あ、眉が下がる癖だ。
僕の顔を再度みて、表情をゆるめる。
「やっぱり、間部くんだ! 私のこと覚えてるかな.......って、やっぱり八年も経ったら忘れちゃったよね」
まるで、忘れられていることが当たり前のように。すらりとそんな言葉が出てくるのは、何度も繰り返したセリフなんだろうか。
「私の名前、近成ありさだよ。高校のときにクラスメイトだったんだけど転校して.......」
知ってる、知ってるとも。
その名前を心のなかで何度呼んだか。
忘れるわけない、僕のいまでも絶賛継続中の初恋の相手だ。
「.......近成さん」
「ふふ、もしかして、思い出してくれたとか?」
「文化祭の買い出し係が一緒になって、買い物のあとになぜか近成さんの親戚の家に寄って」
「あはは! そうそう、親戚が留守のあいだの犬の世話を頼まれててね。犬の散歩に付き合ってもらったよね」
訳もわからずに、ドキドキしながら近成さんと犬のうしろをついて歩いた思い出だ。
二人きり、時々喋って、また歩く。犬を家に戻して、学校へ戻った。
実質、デートだろ!と、その日は浮かれて眠れない夜を過ごした。
色褪せ始めた思い出に、嵐のように咲き乱れはじめた花がまた彩色していく。
僕の顔も、赤く染め上げられてしまった。
ああ、この日のために、この瞬間のために頑張ってきたのに。
感極まって、次の言葉が出てこない。
情けなくも固まってしまった俺に、斎藤くんは「はるさんって、感動屋さんなんですね!」と背中を思いっきり叩いてきた。
「ねぇ、斎藤くん」
「なんですか?」
「女の子って、シナモンロールが好きなんだよね? でもそれって、みんなが好きなのかな。困らないで、貰ってくれるものなのかな」
「すごい早口になってますよ.......そういうのって、はるさんの方がよく知ってるんじゃないんですか? お客さんと、よく喋ってるじゃないですか」
「.......なんか、接客で積み重ねてきたもの全部、さっき吹き飛んだ.......」
近成さんは飲み物を受け取ると、奥の空いた席を探して座った。
僕はもうカチコチになってしまい、そのあとはまともな会話にならなかった。
斎藤くんがカウンターに立っているあいだ、アイスコーヒーの為の豆を挽く。
膝ががくがくしてる気もするけど、仕事はきちんとしなければならない。
「つまりはるさんは、さっき久しぶりに会ったあのお客さんに、いま差し入れしたいんですね?」
「.......うん。だけど、好きな食べ物とかわからないし。お腹いっぱいかもしれない」
ため息と一緒に、一気に吐き出す。
「はるさん。そういうときは、食べきれない分は持って帰れますって言うんですよ。一緒に紙袋と紙ナプキンを渡しちゃえば、判断はあっちが自分でしてくれます」
普段なら、イートインなら紙袋を先に渡すことはない。持って帰りたいと声をかけられたら、用意するものだ。
でも、そうか。一緒に渡してあげればいいのか。
「斎藤くん、どうしてそんなにすぐ答えが出てくるの」
斎藤くんは、うーんと考える。そして、パッと表情を明るくした。
「あれですね、もし、俺と彼女だったらって考えたんです。どうしようって、もし食べきれなかった物の前で、彼女が気を使って悩んだら可哀想ですもん」
「男前だ.......」
「イケメンのはるさんに言われると、照れちゃいますね。俺、彼女のことが大好きで、めっちゃたくさん考えて頑張ったんです。一度フラれてるので、リベンジして」
「すごい、すごいよ! 僕なんて、言葉も出なければうじうじも始めちゃうし。格好悪いよね。でもいま動かなきゃ、また後悔する」
いまこの瞬間にも、近成さんの飲み物が空になったら帰ってしまうかもしれないんだ。
また、この店に寄ってくれる保証も、その時に僕が居るのかもわからない。
動かなきゃ。
どういう形であれ、いま一歩踏み出さないと。
あんなに後悔したんだから。固まってる場合じゃないぞ。
「.......休憩時間の十五分だけいまから取っていい?」
「いいっすよ。じゃあシナモンロール、先に温めておきますね」
斎藤くんはショーケースをあけて、トングでシナモンロールを掴んだ。
「ありがとう! 支払いはこれで、斎藤くんの彼女の分も好きなだけ買っていいから」
名札の裏から現金がチャージされたカードを斎藤くんに渡し、素早くバックルームでしていたエプロンを脱ぐ。
早く、早く、急げ。
バックルームで作業をしていたスタッフが、僕の勢いに驚いている。
「ごめんね、いまから十五分だけ先に休憩いただきます」
そう言った自分の声がちょっとだけ緊張で震えているから、ひとりで可笑しくなってしまった。