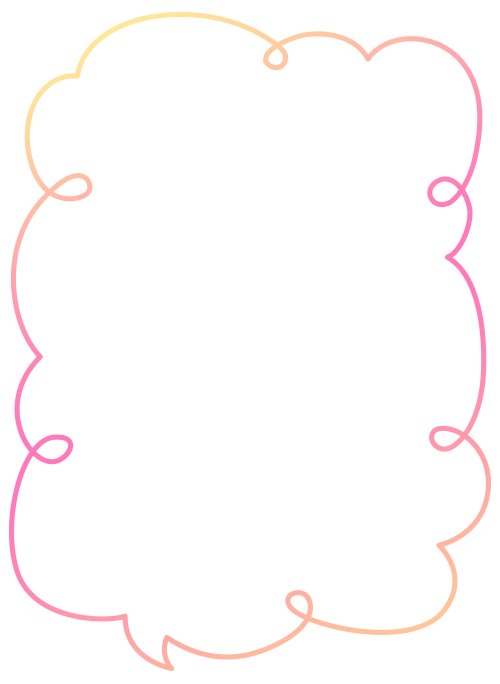その子のことを可愛いと言うコウくんの瞳は、温かさの上に穏やかさを重ねていて。
こちらに向けられている華やかな笑みは今までとは比べ物にならないほどの極上のもので、自分が好かれているような錯覚すら覚えさせられる。
だからこそ、
『あぁ、私は一生その子に勝てないんだ……』
はっきりと、これから先自分の恋が叶うことはないのだとわかった。
じくじくと痛んで、でも錯覚に騙されてときめいてしまう正直な胸を抑えながら、私は白旗を上げる。
そもそも、うるさい私のことなんか纏わりつく謎の綿毛くらいにしか思われていなかったのかもしれない。
邪魔くさいけど取るのも億劫で相手にされない、大したことない存在。
柄にもなく暗い思考に陥ったとき、つうっと一粒の涙が頬に筋を作って。
「……え?」
驚きに目を見開くコウくんを横目に。
私はその場から立ち上がり、駆け出していた。