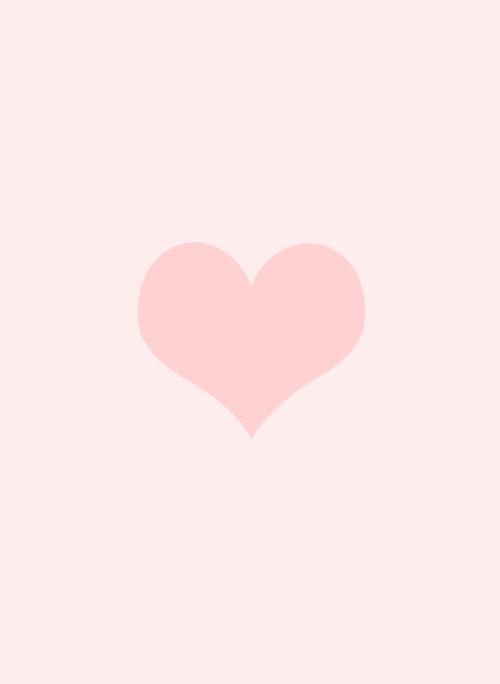誰かが私の裏垢を作ってなりすましていたことや、私がそれほど恨まれているかもしれないこと。
それを話したことによって、時枝くんがすべての出来事を思い出すかもしれない。
もしも、突き放されたら私の心は今度こそ折れてしまいそうだ。
スカートに涙が滲みを残していく。時枝くんは遠慮がちに私の肩へと手を伸ばした。大きな手が暖かくて、縋りついて寄りかかってしまいたくなる。
「不安かもしれないけど、たとえ忘れてもまた宮里のこと思い出すから」
嗚咽を漏らしながら泣きじゃくる私を時枝くんは引き寄せると、背中を軽くとんとんと優しいリズムで叩いてくれた。
「一緒に思い出してもらう方法を探そう」
「……ありがとう」
透明現象は私自身が望んだことで、本当は戻る勇気がない。
時枝くんや未羽、真衣たちから一緒に過ごした大事な思い出が消えてしまうことは悲しい。けれど忘れられている今の方が安らげる環境だなんて、話せなかった。
ずるくて、勝手で、最低だ。
それでも私の存在を〝忘れないで〟と願いたくなる。
その日の夜、私は部屋のローテーブルに置いていたレインドームをじっと観察していた。雨が桜の木に降り注いでいる。
購入した日よりも、雨が強くなっているように思えるけれど、これがすごい力を秘めているようにも見えない。こんなことが起こっているのに、レインドームに不思議な力があるということに対しては、半信半疑だった。
「……時枝くんが私のことを覚えていてくれたらいいのに」
そんな都合のいい願いが叶うはずないかと思いながらも、私は指先でレインドームに触れる。
だけどきっと、また忘れられてしまう。
床に落ちていた青いリボンを拾い上げる。
時枝くんに渡したいと思っていたバレンタインのチョコレートをラッピングしていたものだ。
それを握りしめながら、いまだに机の上に置いてあるチョコレートの箱を眺める。
友達用に買ったチョコレートだけど、このままだと自分で食べるしかない。
もしも私のことを覚えていてくれたら、そのときは——淡い期待を抱いて、私はチョコレートを一箱カバンの中に入れた。