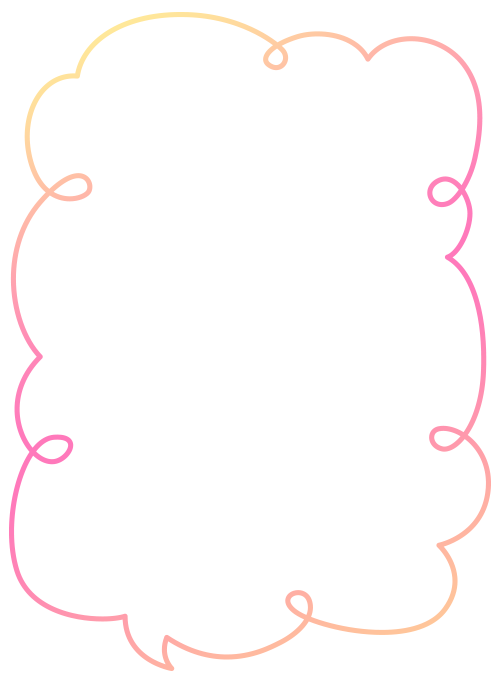◇ ◇ ◇
「うへ、きもちわる」
わたしが目を開けてから真っ先に映ったもの。それはわたしの写真だった。
壁、床、天井、扉。
隙間を探す方が難しいくらいに敷き詰められた、こちらを向かないわたしの姿。
夏の格好だけでなく、まだ訪れていない冬の装いをしている写真もあることからストーカーの歴の長さがわかる。
もっとも、わたしがそのヤバい存在に気づいたのはつい最近のことなんだけど。
椅子に座らされた状態のわたしが次に目にしたのはこの部屋の出口、つまり扉で。
一刻も早くこの気色悪い部屋から出たいと駆け寄ろうとしたとき、それを無情にも阻む無機質なものの感触が手首に伝わった。
それから、今まで黙っていたストーカーが視界の隅で動き、鼻先で笑ったのも聞こえた。
「そんな簡単に逃がすわけないだろ。浮気者にはちゃんと躾をしなきゃいけないからな」
そう言った男はわたしの手に自分の手を重ね、わたしを味わうかのようにそれを這わせた。
不愉快な温度が移り、わたしの背中にゾッと寒気が走る。
露骨に顔を歪めてみせたのだけど、ニヤついた男はさして気にしてもない様子でわたしの手を触り続けた。