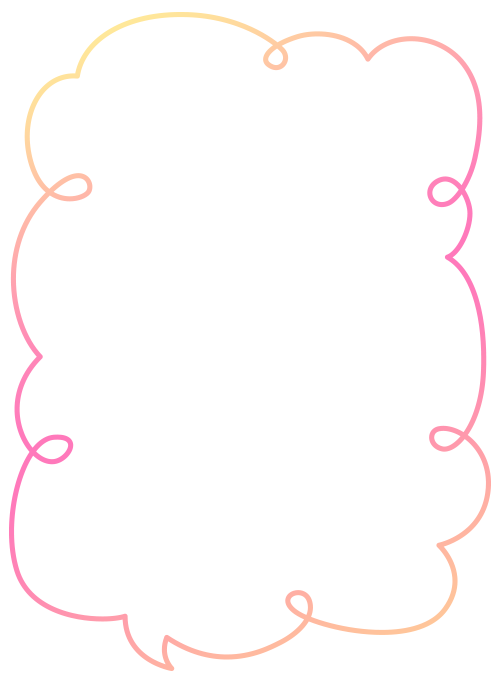首元に顔をうずめたストーカーはわたしの匂いを堪能しながら、わたしの存在を確かめるように身体を上から下へと手でなぞっていく。
肩から腕。腕から腰。腰から太もも。
後ろで拘束されたわたしにはそれを止める術もなく、できるのは効力を持たない抵抗の言葉を吐くことだけ。
言葉の通じない自己中心的な男を目の前に、わたしの心は恐怖で支配されていく。つられて瞳も潤み始めた。
やだ、無理、怖い、気持ち悪い。上手く息ができない。
寒くないのに身体が震えちゃう。
おにいちゃん、どこにいるの?なにをしてるの?
「……おにいちゃん、たすけて」
「は?なんで今あいつのことを呼ぶんだよ。“たすけて”ってなんだよ」
「わたしをおにいちゃんのところに返して……」
「ふざけんな!一番気に食わねぇやつのところに返してたまるかよ!お前はもう俺のものなんだ。一生ここから出してやらねーよ」
「わたしはあんたのものじゃない!」
「うるせー!否定するんじゃねぇ!」
「やっ、ん———」
逆上したストーカーにいとも簡単に奪われるわたしのファーストキス。荒々しく重なった唇は想像とはかけ離れていて……わたしは深く絶望した。