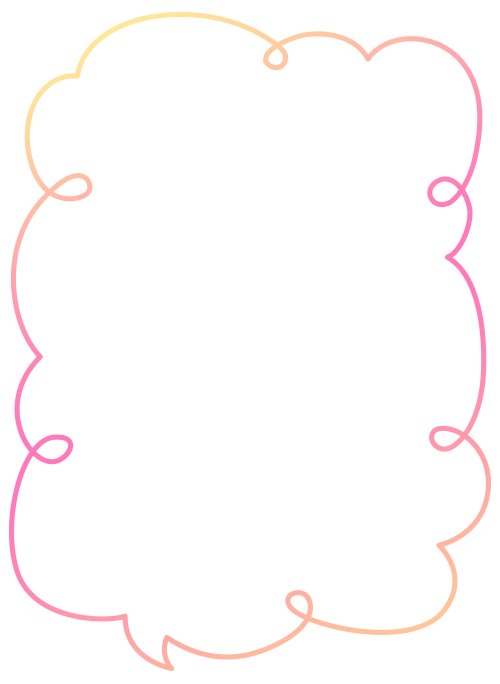「涙、止まっちゃったみたいですね。残念」
そう言ってさりげなく涙の跡を拭う男子高校生は、さぞかし学校でモテることだろう。
そんな人がどうしたら私を想い続けられるというのか。
あいにく、夢見るお年頃はとうの昔に過ぎてしまっている。
今の想いは真剣でもそれがいつまでもそうとは限らないのだ。
それは私の中に生まれ始めている、この甘く小さな恋心も同じで。
こんなの認められない。認めちゃいけない。
「お姉さんって簡単なことを複雑に考えるのが好きそうだよね」
「……大人だもの」
つい1分前まではまっさらな気持ちを伝えてくれていたのに、男子高校生の言葉には嫌味が含まれているような気がした。
負けじと言い返した私の言葉は意地が悪いもので、わざと私と男子高校生との差というものを感じさせる言葉を選んだ。
効果てきめんだったようで、男子高校生はあっさりと口を閉じた。
頬に触れていた手を力なく下ろし、私から距離を取る。
諦めてくれて良かったと思う反面、言いようのない後悔の念が込み上げてくる。
自分で突き放しておいて傷つくなんて、バカみたい。
これが最善の選択。私は間違ってなんかいない。これでいいんだ。
そう自分の行いを正当化していると、
「じゃあお姉さん。俺と友達になってよ」
改まって握手を求めるように手を差し出され、軽快な口調でそんなお願いをされた。