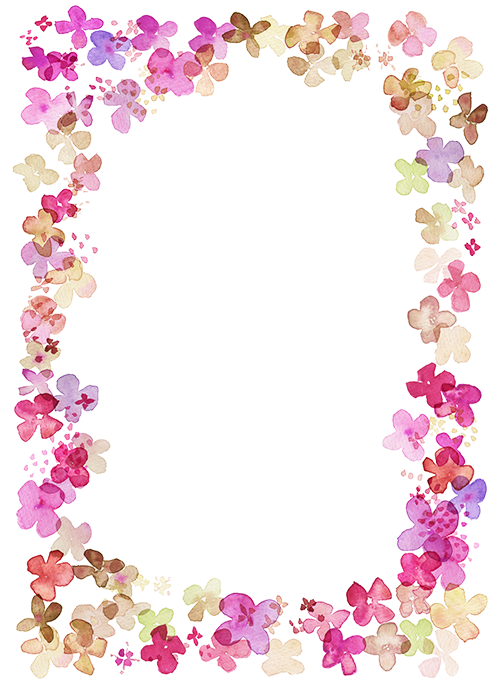「そこまで娘を想っていると。『新規事業は母の夢でもある』と、いつか君が語っていたのを覚えているが」
「…そうです。このポータルサイト運営事業は、私の母が抱いてきた長年の夢でもあります」
『日本文化の保全と発展に貢献する』
我が社の経営方針ともなっているこの考えは、母の悲願でもあった。
倒産を回避することから始まった綾部ホールディングスの道のりは、言い換えれば日本文化離れとの戦いの軌跡でもあった。
欧米志向が普及した結果、多くの同業者や取引先である問屋や工房店といった日本文化の担い手が、この戦いに敗れ、消え去っていった。
嘆き悲しむ余裕などなく、母と綾部屋も生き残るのに必死の思いでやってきた。胸の奥では常に、いつかこの苦境を打破したい、同じようにあえいでいる仲間たちの助けになりたい、という宿願を抱きながら。
大きく躍進を遂げることに成功した今、日本文化の担い手と消費者のつながりをもっと密接なものにすることを目的としたこのポータルサイト運営事業は、その戦いにおける大きな切り札とも言えた。
まさに、母と綾部屋の悲願の達成だった。
だからこそ、芽衣子の件は俺から母に直に伝えるべきことだった。
あの綾部屋本店に行った折、芽衣子を残して俺一人で母に会いに行ったのは、それをするためだった。
新規事業を振り出しに戻してしまうという危険に晒してしまうことと、それでも芽衣子を選びたいと願う我儘を謝罪しに。
母にあれほど誠実に真剣に頭を下げたのは初めてだった。
そんな俺を母は静かに受け止め、許してくれた。
そして改めて、俺に綾部屋を託してくれたのだ。
「…そうです。このポータルサイト運営事業は、私の母が抱いてきた長年の夢でもあります」
『日本文化の保全と発展に貢献する』
我が社の経営方針ともなっているこの考えは、母の悲願でもあった。
倒産を回避することから始まった綾部ホールディングスの道のりは、言い換えれば日本文化離れとの戦いの軌跡でもあった。
欧米志向が普及した結果、多くの同業者や取引先である問屋や工房店といった日本文化の担い手が、この戦いに敗れ、消え去っていった。
嘆き悲しむ余裕などなく、母と綾部屋も生き残るのに必死の思いでやってきた。胸の奥では常に、いつかこの苦境を打破したい、同じようにあえいでいる仲間たちの助けになりたい、という宿願を抱きながら。
大きく躍進を遂げることに成功した今、日本文化の担い手と消費者のつながりをもっと密接なものにすることを目的としたこのポータルサイト運営事業は、その戦いにおける大きな切り札とも言えた。
まさに、母と綾部屋の悲願の達成だった。
だからこそ、芽衣子の件は俺から母に直に伝えるべきことだった。
あの綾部屋本店に行った折、芽衣子を残して俺一人で母に会いに行ったのは、それをするためだった。
新規事業を振り出しに戻してしまうという危険に晒してしまうことと、それでも芽衣子を選びたいと願う我儘を謝罪しに。
母にあれほど誠実に真剣に頭を下げたのは初めてだった。
そんな俺を母は静かに受け止め、許してくれた。
そして改めて、俺に綾部屋を託してくれたのだ。