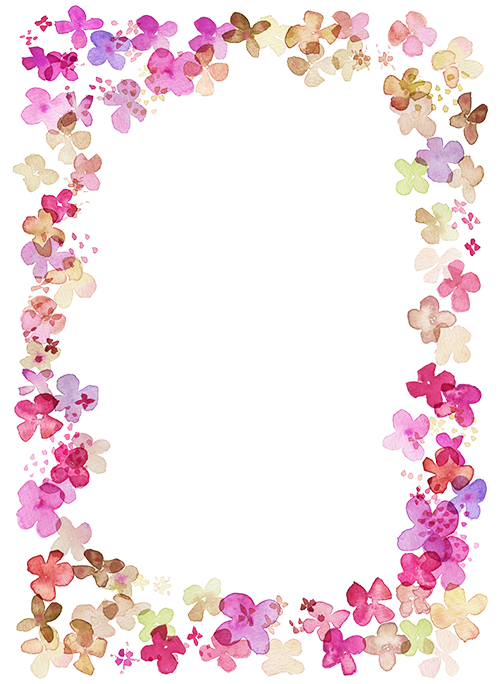あっという間に二人きりに戻った私と雅己さんは、顔を見合わせる。
「なんだったんだろうな、母さん。ったく」
「やっぱり、パワフルな方…」
「ま、なんにせよ、君のことを大いに気に入ったみたいだ」
「だと…いいのだけれど…」
と言葉を濁す私の頬を、雅己さんは「上出来だったよ」と褒めるように撫でる。
「とても素敵なお母様ね。お母様と話している時の雅己さんもなんだかいつもと違ってて、面白かった」
「おいおい」
雅己さんは笑った。
「俺は母子家庭だからね。母一人子一人。あっちも過保護だし、俺もなんだかんだで弱い」
黙ってうなずく私に、雅己さんはさらに話を続けた。
「うちがもともとは京都の老舗呉服店だというのは知っているだろ。母が後継ぎで父は婿養子だったんだ。ところが父は俺が小さい時に外に女を作って蒸発してしまった」
「…」
「『着物が売れる時代なんてとうに過ぎていたのに、老舗呉服店の婿養子になれば楽な暮らしができると安直に考えて受けた縁談だったんでしょうね』と母は笑ってたよ。老舗って看板だけ立派で、爪の先に火を灯すような暮らしに耐え切れず、父は俺と母を捨てたんだ。薄情な男だろ。顔を覚えていないのがせめてもの救いだ」
そう言い切る雅己さんの笑みは哀愁など微塵もなく、むしろすっきりと明るかった。
「そこから母は一人で頑張って、俺を一人で育てながら小さな呉服店を綾部ホールディングスなんて化け物に変えた。最初は反発することも多かったけれど、やっぱりあの人は偉大だったよ。あの人の跡を継ぐことは俺の運命だと思ったし、その運命を面白く感じるようにもなってきた」
雅己さんは私の手を握った。
「なんだったんだろうな、母さん。ったく」
「やっぱり、パワフルな方…」
「ま、なんにせよ、君のことを大いに気に入ったみたいだ」
「だと…いいのだけれど…」
と言葉を濁す私の頬を、雅己さんは「上出来だったよ」と褒めるように撫でる。
「とても素敵なお母様ね。お母様と話している時の雅己さんもなんだかいつもと違ってて、面白かった」
「おいおい」
雅己さんは笑った。
「俺は母子家庭だからね。母一人子一人。あっちも過保護だし、俺もなんだかんだで弱い」
黙ってうなずく私に、雅己さんはさらに話を続けた。
「うちがもともとは京都の老舗呉服店だというのは知っているだろ。母が後継ぎで父は婿養子だったんだ。ところが父は俺が小さい時に外に女を作って蒸発してしまった」
「…」
「『着物が売れる時代なんてとうに過ぎていたのに、老舗呉服店の婿養子になれば楽な暮らしができると安直に考えて受けた縁談だったんでしょうね』と母は笑ってたよ。老舗って看板だけ立派で、爪の先に火を灯すような暮らしに耐え切れず、父は俺と母を捨てたんだ。薄情な男だろ。顔を覚えていないのがせめてもの救いだ」
そう言い切る雅己さんの笑みは哀愁など微塵もなく、むしろすっきりと明るかった。
「そこから母は一人で頑張って、俺を一人で育てながら小さな呉服店を綾部ホールディングスなんて化け物に変えた。最初は反発することも多かったけれど、やっぱりあの人は偉大だったよ。あの人の跡を継ぐことは俺の運命だと思ったし、その運命を面白く感じるようにもなってきた」
雅己さんは私の手を握った。