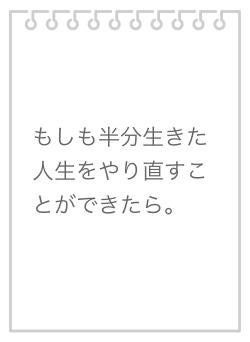13時52分、
わたしは独りぼっちの病室で目を覚ます。
酸素マスクからツンとしたにおいが息苦しい。
目覚めて分かったのは、お腹にはぽっかり穴が空いたように何かがなくなっているということ。
わたしだけが生き延びているということ。
中絶したのに何も痛みがないということ。
「ごめんっ………ごめんなさい」
わたしは生きていた。
死んで当然なわたしはまだ生かされて生きていた。
生きる希望も資格もないわたしが生きている理由はない。
この子に必要とされる未来をわたしが潰した。
理由はこの子が大人になったとき、わたしが母を憎むような恨むような目や言葉で傷つけられることを恐れたため。
死にたい。
その約1時間後、わたしは病院を出た。
♪〜♪〜♪
【朝日、今日仕事午前中で終わりやし、迎えに行くわ!〇〇病院やな?入口で待ってて】
放心状態のまま、わたしは彼を待った。
下腹部が重力に押され、子宮が下に下がってくる感覚。
立っていられなくて、座り込んでしまう。
冷や汗が止まらない。
苦しい痛みが続いた。
わたしの今見ている世界から、色が消えていく。
「朝日!こっち!」
駐車場で待つ大矢さんに手を振り、ゆっくりと駆け寄った。
「どうやった?検査」
「………」
「朝日?」
「…堕ろしたよ」
「…えっ」
「もういない」
「………」
「…家まで送ってください」
彼は車内で何も言わなかった。
ただ黙って、わたしの手を握ってくれた。
わたしは独りぼっちの病室で目を覚ます。
酸素マスクからツンとしたにおいが息苦しい。
目覚めて分かったのは、お腹にはぽっかり穴が空いたように何かがなくなっているということ。
わたしだけが生き延びているということ。
中絶したのに何も痛みがないということ。
「ごめんっ………ごめんなさい」
わたしは生きていた。
死んで当然なわたしはまだ生かされて生きていた。
生きる希望も資格もないわたしが生きている理由はない。
この子に必要とされる未来をわたしが潰した。
理由はこの子が大人になったとき、わたしが母を憎むような恨むような目や言葉で傷つけられることを恐れたため。
死にたい。
その約1時間後、わたしは病院を出た。
♪〜♪〜♪
【朝日、今日仕事午前中で終わりやし、迎えに行くわ!〇〇病院やな?入口で待ってて】
放心状態のまま、わたしは彼を待った。
下腹部が重力に押され、子宮が下に下がってくる感覚。
立っていられなくて、座り込んでしまう。
冷や汗が止まらない。
苦しい痛みが続いた。
わたしの今見ている世界から、色が消えていく。
「朝日!こっち!」
駐車場で待つ大矢さんに手を振り、ゆっくりと駆け寄った。
「どうやった?検査」
「………」
「朝日?」
「…堕ろしたよ」
「…えっ」
「もういない」
「………」
「…家まで送ってください」
彼は車内で何も言わなかった。
ただ黙って、わたしの手を握ってくれた。