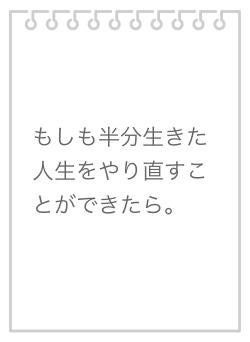何を思って来たのか。
母親は「中絶しなさい」「まだ若いんやから」「まだやり直せる」と言ってきた。
やり直せる?
簡単に言わないでほしい。
こうなってる時点でやり直せるわけがない。
お腹がじんじんと痛む。
「お兄ちゃんはね」
母がこの日教えてくれたことは、わたしが死ぬ選択をするきっかけになったんよ。
後悔する?
でもね、あんな話を愛に飢えている自分の子どもにするべきではなかったよ。
「お父さんと別れるか別れへんかのときにできた子やったんよ…」
母親の口から重苦しく出たこの言葉が、今まで悩みながら生きてきたわたしのすべての腑に落ちた。
その言葉を聞いた瞬間、「ああ、やっぱり」と思えてならなった。
やっぱりね。
やっぱりわたしは生まれてくるべき人間じゃなったんやね。
生まれてくるべき人間じゃなかったから、愛されなかったんや。
そりゃ、愛されなくて同然やね。
そう思わずにはいられなかった。
母もきっと誰にも言えなかったんだろう。
その言葉を境に母が抱えていた思いが言葉となって落ちてくる。
降り注ぐその言葉たちがわたしを見つけて、近寄って、蝕んでゆく。
あなたの愛の言葉に包まれたかったよ。
「お兄ちゃんを妊娠してた時、21歳やって。お母さんは実家からこっちに一人暮らしで出てきたから周りに家族や知り合いがいなくて、すごく心細かったのを覚えてる」
母親は声を震わせた。
その後続いた言葉をわたしは俯きながら聞いた。
もう母親の顔すら見れなかった。
本当はデキ婚だった。
昔は授かり婚なん優しい言葉はなかったから、きっと嬉しかった反面、周りからの視線が母親自身不安であり、嫌悪感があったはず。
若くして兄を授かって、誰にも相談出来なったから心細いわたしの気持ちに寄り添えた。
やっぱりそうやったんや。
母親は自分が経験したことでしかわたしに共感もしてくれないひとだった。
子どもの心に寄り添えないひとだった。
もしも、母がもっと遅くに妊娠出来ていたら。
結婚してから妊娠していたら。
母の理想の子どもの授かり方ができていたら。
わたしはどれ程、罵倒されていたんやろう。
どれ程、怒鳴られていたんやろう。
罰が当たったと、日ごろの行いが悪いと、大っ嫌いな軽蔑の目で見下されていたんだろう。
母親は「中絶しなさい」「まだ若いんやから」「まだやり直せる」と言ってきた。
やり直せる?
簡単に言わないでほしい。
こうなってる時点でやり直せるわけがない。
お腹がじんじんと痛む。
「お兄ちゃんはね」
母がこの日教えてくれたことは、わたしが死ぬ選択をするきっかけになったんよ。
後悔する?
でもね、あんな話を愛に飢えている自分の子どもにするべきではなかったよ。
「お父さんと別れるか別れへんかのときにできた子やったんよ…」
母親の口から重苦しく出たこの言葉が、今まで悩みながら生きてきたわたしのすべての腑に落ちた。
その言葉を聞いた瞬間、「ああ、やっぱり」と思えてならなった。
やっぱりね。
やっぱりわたしは生まれてくるべき人間じゃなったんやね。
生まれてくるべき人間じゃなかったから、愛されなかったんや。
そりゃ、愛されなくて同然やね。
そう思わずにはいられなかった。
母もきっと誰にも言えなかったんだろう。
その言葉を境に母が抱えていた思いが言葉となって落ちてくる。
降り注ぐその言葉たちがわたしを見つけて、近寄って、蝕んでゆく。
あなたの愛の言葉に包まれたかったよ。
「お兄ちゃんを妊娠してた時、21歳やって。お母さんは実家からこっちに一人暮らしで出てきたから周りに家族や知り合いがいなくて、すごく心細かったのを覚えてる」
母親は声を震わせた。
その後続いた言葉をわたしは俯きながら聞いた。
もう母親の顔すら見れなかった。
本当はデキ婚だった。
昔は授かり婚なん優しい言葉はなかったから、きっと嬉しかった反面、周りからの視線が母親自身不安であり、嫌悪感があったはず。
若くして兄を授かって、誰にも相談出来なったから心細いわたしの気持ちに寄り添えた。
やっぱりそうやったんや。
母親は自分が経験したことでしかわたしに共感もしてくれないひとだった。
子どもの心に寄り添えないひとだった。
もしも、母がもっと遅くに妊娠出来ていたら。
結婚してから妊娠していたら。
母の理想の子どもの授かり方ができていたら。
わたしはどれ程、罵倒されていたんやろう。
どれ程、怒鳴られていたんやろう。
罰が当たったと、日ごろの行いが悪いと、大っ嫌いな軽蔑の目で見下されていたんだろう。