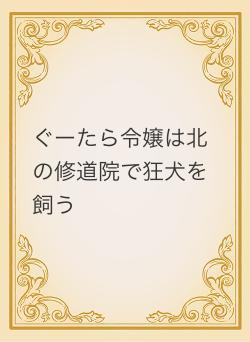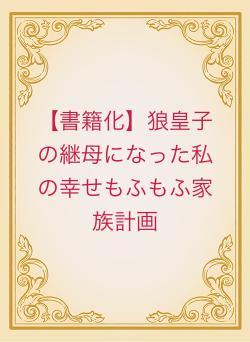不運ゆえ奇人と呼ばれ、友人の一人もいないが恋人ができた。これは喜ばしいことなのだろうか。数日ベッドの住人となっていた私は、のろのろと起き上がった。
オルガ様に送ってもらった日、私は本当に熱を出した。もちろん、知恵熱だ。めまぐるしい感情の波について行けず、私はそのまま熱をだした。そのあと三日ほど熱に浮かされていたように思う。
娘が熱で倒れたというのに、お父さまのほうはウキウキしていた。あの日、オルガ様が倒れてはいけないからと甲斐甲斐しく横抱きにして部屋まで連れて行ってくれたのだから。
お父さまは熱に浮かされた娘の隣で何度も「結婚の申し込みもすぐだな」と呪文のように唱えていた。
そういう話は元気になってからでもいいのではないかしら。
「お嬢さま、ようやく回復してよかったですね。これで魔導師長様の元へ通えますし」
「あなたもそうやって意地悪言わないで。また熱が出ちゃう」
侍女は、うふふと笑うと身体を拭ってくれる。
「でも、お礼には行かれた方がよろしいですよ。魔導師長様ったら、この三日お仕事のあと毎晩通われて朝までお嬢さまの側にいらしたのですから」
「そうなの!?」
「ええ、ずっと心配なされて。その様子を見た旦那様なんて目を潤ませておいででしたわ」
「それは想像できるわね。でも……そうね。ご迷惑をかけたなら謝りに行かなくてはならないわ」
彼は忙しい魔導師長なのよ。仕事帰りに毎夜この屋敷に通うなど、簡単なことではないはずだ。
「お嬢様、謝罪ではなくお礼に行けばよろしいのです。素直ではないですね」
「善は急げと言うし、これから行こうかしら?」
気持ちがそわそわをしているのは、迷惑をかけてしまったからだわ。恋人がいた経験などないのだから、これが普通なのかもわからない。
とにかく会いに行きたかった私は、「明日でもいいのでは」というみんなの言葉を振り切って、城へと向かったのだ。
何を伝えるのかと聞かれたら、決まってはいない。「ありがとう」? それとも、「ごめんなさい」? ただ、会いたいという気持ちに嘘はなかった。
だったら会ってから考えればいいわ。
今日の私はついている。家で転びそうにはならなかったし、鳥の贈り物も落ちてこなかった。
道中、道のど真ん中で牛が立ち往生するようなこともなかったのだ。
今日の私は最高潮だわ。
今日なら素直な気持ちを言えるのではないかと思ったのだ。
城についたらまっすぐ魔導師長の執務室へと向かう。もう慣れた道だ。オルガ様の案内などなくても一人で行けるくらい通った。
いつもよりも気持ち歩くのが速くなる。城ではなるべくお淑やかなにとは思っているのだけれど、気が急くのだ。
広くて長い回廊の途中、見慣れた背中を見つけて私は足を止めた。
あれはオルガ様? と、誰かしら?
声をかけようとしたところで、角を曲がってしまった。慌てて追いかける。
そういえば、同僚の方とお話しするのを見たことがないわ。どんな話をしているのかしら? すこし興味が湧いたので、彼らの死角で様子をうかがうことにしたのだ。
「最近君と変わりもののマリエル嬢の噂をよく耳にするよ。ご執心だって」
「そうか」
私の話をしているのかしら?
オルガ様は無愛想に答えた。いつも私の前では柔やかな優しい紳士なのに、イメージが全然違う。
「そろそろ捕まえられるんじゃないか?」
「なにがだ?」
「悪魔だよ。あ・く・ま。悪魔の角を手に入れるために彼女に近づいたんじゃないか。忘れたのか?」
「……あ、ああ。そうだったな」
「あとは悪魔の角が手に入れば、秘薬が完成しそうなんだろう? で、どうなわけ? 彼女から悪魔は抜けそうか?」
「あともう少しだと思う。そうすれば彼女は……」
「難儀だよなぁ。取憑いた悪魔を引き剥がす方法が心が震えるような甘い台詞と愛なんてさ。それにしてもすごいよ。奇人相手にここまでやれる奴はおまえしかいない」
「あのな、だから私は――……」
「はいはい。そういうのはいいから。でさ、」
少しずつ声は遠のいていく。私は必死に両手で口を押さえた。
私は不運体質。それはけっしては忘れてはいけなかった。
なぜ朝から調子が良いのか。
なぜ来る途中になんの不運も私を襲わなかったのか考えるべきだったのだ。
この話を聞かせるためだったのね。
足が震えて立っているのも難しい。しかし、ここで堪えなければ、更なる不運に見舞われるのは、不運専門家の私ならすぐにわかる。この話を盗み聞きしていたことがオルガ様に知られたら……。
私は喉から出そうになる不安を飲み込み必死に足音が遠のくのを待った。
オルガ様に送ってもらった日、私は本当に熱を出した。もちろん、知恵熱だ。めまぐるしい感情の波について行けず、私はそのまま熱をだした。そのあと三日ほど熱に浮かされていたように思う。
娘が熱で倒れたというのに、お父さまのほうはウキウキしていた。あの日、オルガ様が倒れてはいけないからと甲斐甲斐しく横抱きにして部屋まで連れて行ってくれたのだから。
お父さまは熱に浮かされた娘の隣で何度も「結婚の申し込みもすぐだな」と呪文のように唱えていた。
そういう話は元気になってからでもいいのではないかしら。
「お嬢さま、ようやく回復してよかったですね。これで魔導師長様の元へ通えますし」
「あなたもそうやって意地悪言わないで。また熱が出ちゃう」
侍女は、うふふと笑うと身体を拭ってくれる。
「でも、お礼には行かれた方がよろしいですよ。魔導師長様ったら、この三日お仕事のあと毎晩通われて朝までお嬢さまの側にいらしたのですから」
「そうなの!?」
「ええ、ずっと心配なされて。その様子を見た旦那様なんて目を潤ませておいででしたわ」
「それは想像できるわね。でも……そうね。ご迷惑をかけたなら謝りに行かなくてはならないわ」
彼は忙しい魔導師長なのよ。仕事帰りに毎夜この屋敷に通うなど、簡単なことではないはずだ。
「お嬢様、謝罪ではなくお礼に行けばよろしいのです。素直ではないですね」
「善は急げと言うし、これから行こうかしら?」
気持ちがそわそわをしているのは、迷惑をかけてしまったからだわ。恋人がいた経験などないのだから、これが普通なのかもわからない。
とにかく会いに行きたかった私は、「明日でもいいのでは」というみんなの言葉を振り切って、城へと向かったのだ。
何を伝えるのかと聞かれたら、決まってはいない。「ありがとう」? それとも、「ごめんなさい」? ただ、会いたいという気持ちに嘘はなかった。
だったら会ってから考えればいいわ。
今日の私はついている。家で転びそうにはならなかったし、鳥の贈り物も落ちてこなかった。
道中、道のど真ん中で牛が立ち往生するようなこともなかったのだ。
今日の私は最高潮だわ。
今日なら素直な気持ちを言えるのではないかと思ったのだ。
城についたらまっすぐ魔導師長の執務室へと向かう。もう慣れた道だ。オルガ様の案内などなくても一人で行けるくらい通った。
いつもよりも気持ち歩くのが速くなる。城ではなるべくお淑やかなにとは思っているのだけれど、気が急くのだ。
広くて長い回廊の途中、見慣れた背中を見つけて私は足を止めた。
あれはオルガ様? と、誰かしら?
声をかけようとしたところで、角を曲がってしまった。慌てて追いかける。
そういえば、同僚の方とお話しするのを見たことがないわ。どんな話をしているのかしら? すこし興味が湧いたので、彼らの死角で様子をうかがうことにしたのだ。
「最近君と変わりもののマリエル嬢の噂をよく耳にするよ。ご執心だって」
「そうか」
私の話をしているのかしら?
オルガ様は無愛想に答えた。いつも私の前では柔やかな優しい紳士なのに、イメージが全然違う。
「そろそろ捕まえられるんじゃないか?」
「なにがだ?」
「悪魔だよ。あ・く・ま。悪魔の角を手に入れるために彼女に近づいたんじゃないか。忘れたのか?」
「……あ、ああ。そうだったな」
「あとは悪魔の角が手に入れば、秘薬が完成しそうなんだろう? で、どうなわけ? 彼女から悪魔は抜けそうか?」
「あともう少しだと思う。そうすれば彼女は……」
「難儀だよなぁ。取憑いた悪魔を引き剥がす方法が心が震えるような甘い台詞と愛なんてさ。それにしてもすごいよ。奇人相手にここまでやれる奴はおまえしかいない」
「あのな、だから私は――……」
「はいはい。そういうのはいいから。でさ、」
少しずつ声は遠のいていく。私は必死に両手で口を押さえた。
私は不運体質。それはけっしては忘れてはいけなかった。
なぜ朝から調子が良いのか。
なぜ来る途中になんの不運も私を襲わなかったのか考えるべきだったのだ。
この話を聞かせるためだったのね。
足が震えて立っているのも難しい。しかし、ここで堪えなければ、更なる不運に見舞われるのは、不運専門家の私ならすぐにわかる。この話を盗み聞きしていたことがオルガ様に知られたら……。
私は喉から出そうになる不安を飲み込み必死に足音が遠のくのを待った。