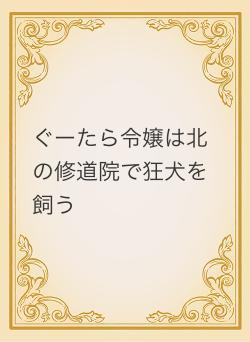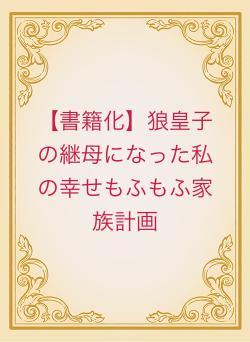最初は事故だった。二度目の事故は回避したはずだ。なのに、唇は重なった。
これは不運? それとも――……。
私は今日も城に向かう馬車に乗る。昨日のことを思い出して何度も唇をなぞった。
あれはなんだったの?
回避したはずだった。そのまま立ち上がれば、二度目の口づけは回避できたはずなのだ。でも、私たちは恋人。口づけの一つや二つしてもおかしくはない。
あのとき、私だって回避しようと思えば、回避できた。それをオルガ様が望んだからと、受け入れたのだ。
「や、やっぱり今日は帰ります!」
「そうおっしゃられても……」
私は馬車が止まり、扉が開いた瞬間に叫んだ。御者は困惑を隠さない。そうよね、もう目的地に到着したのですもの。
でも! それでも譲れないことってあるじゃない……?
昨日のことをありありと思い出せば、頬に熱が集まる。こんな状態で会えば、大変なことになっていしまう。不運がどうのとかどうでも良くなってしまうじゃない。
私の人生は不運を中心に回っていたはずよ。オルガ様が中心なんかじゃない。
「マリエルは私のことが嫌いになってしまった?」
突然の声に肩が跳ねる。胸も容易く跳ねた。私の脳がこの声はオルガ様の声だと知っているからだ。
彼はいつも馬車まで迎えに来てくれるではないか。これは予想できた事態。駄々をこねるなら屋敷の中ですべきだったし、ここまで来たら腹を括るべきだった。
「嫌いではありません。嫌いではありませんが……」
「が?」
オルガ様、なぜ馬車に乗り込むのでしょうか?
彼は狭い馬車の中に乗り込むと、扉を閉めてしまった。カーテンで外界とは仕切られていて、ここは密室だ。
胸は容易く高鳴る。
「……いえ、今日はなんだか調子が悪いみたいで。風邪でしたら、オルガ様に迷惑がかかりますから」
わざとらしく手の甲で額を触る。ついでに上気した頬も冷やした。熱いような気がする。もし熱があるなら、風邪ではなく知恵熱ではあるが。
「風邪か……それは心配だ」
「えっ!?」
オルガ様の顔が急に近づいてきて、私は小さな悲鳴を上げた。
コツンと額が合わさる。く、唇が近い……!
また口づけられるのでは?
しかし、昨日のように唇が合わさることはなく、すぐに離れていった。
「熱はないようだ。だが、頬は少し赤みを帯びているな。城にはいい医師がいる。診てもらおう」
「い、いえ! いえいえ! 大丈夫です! 熱がないなら、私の勘違いみたいですわね」
ただ熱を心配してくれただけだというのに、勝手に勘違いしてなんて。破廉恥なのは私だ!
「無理はよくない。今日はこのまま屋敷に送ろう」
「ええ、そうですわね。今日は帰って休みますから、オルガ様はお仕事――……え?」
オルガ様はにこりと笑うと、御者に馬車を出すように命じる。行き先は私の屋敷。逆戻りだ。
彼は入ってきたときは向かい側に座っていたが、今は隣に座る。豪奢で広めの馬車なのにぴったりとくっついている。
「オルガ様もご一緒に?」
「何かあってはいけないからね。それに、君との時間は私にとって癒やしなんだ。送り届ける権利を奪わないでほしい」
そう言われてだめだと言えるだろうか。私は小さく頷くことしかできない。
ああ、頬が熱い。本当に熱が出そうだわ。
「実は昨日、無理に口づけたから嫌われたかと思って心配した」
「そんな……ことは」
ごにょごぎょと語尾が弱くなる。嫌ってはいない。でも会うのは恥ずかしいと思った。
「今日も迎えに行った馬車がここに止まったとき安堵したんだ。もう会ってくれなかったらどうしようかと思った」
「迎えが来たら行きます。だって、こ、恋人ですから」
恥ずかしい。彼との関係を自ら「恋人」と言うのは初めてだった。もしかしたら、騙されているのかもしれないとずっと思っていたからだ。
でも、ここまでしてくれる彼をどう疑えばいいのだろうか。もしこのまま疑い続けていれば、不運の悪魔がこの縁まで刈り取ってしまうのではないかと不安になった。
一度くらい、運命に身を任せてもいいわよね。
「ようやく私を恋人だと認めてくれたんだ。嬉しいよ」
オルガ様の手が私の頬を撫でる。もう慣れた行為のはずなのに、恥ずかしさが勝った。
「口づけてもいい?」
「それは……聞くようなことですか?」
「昨日反省したんだ。無理強いはよくないと」
長いまつげが僅かに震える。そんな顔で見ないでほしい。
「一度や二度は変わらないのでしょう? なら、三度だってたいした問題ではないと思います」
「弱ったな。昨日はそうでも言わないと逃げられると思ったんだ」
彼の指が私の唇をなぞる。それは口づけと何ら変わらないのではないだろうか。私の唇と彼の指が触れあっているのだから。
「も、もう逃げません……」
「本当に?」
彼の問いに小さく頷くと、指がそっと離れていく。淡く感じていた温もりが消えると寂しさを感じるものだ。しかし、その寂しさを拭うように彼の唇が重なった。
これは不運? それとも――……。
私は今日も城に向かう馬車に乗る。昨日のことを思い出して何度も唇をなぞった。
あれはなんだったの?
回避したはずだった。そのまま立ち上がれば、二度目の口づけは回避できたはずなのだ。でも、私たちは恋人。口づけの一つや二つしてもおかしくはない。
あのとき、私だって回避しようと思えば、回避できた。それをオルガ様が望んだからと、受け入れたのだ。
「や、やっぱり今日は帰ります!」
「そうおっしゃられても……」
私は馬車が止まり、扉が開いた瞬間に叫んだ。御者は困惑を隠さない。そうよね、もう目的地に到着したのですもの。
でも! それでも譲れないことってあるじゃない……?
昨日のことをありありと思い出せば、頬に熱が集まる。こんな状態で会えば、大変なことになっていしまう。不運がどうのとかどうでも良くなってしまうじゃない。
私の人生は不運を中心に回っていたはずよ。オルガ様が中心なんかじゃない。
「マリエルは私のことが嫌いになってしまった?」
突然の声に肩が跳ねる。胸も容易く跳ねた。私の脳がこの声はオルガ様の声だと知っているからだ。
彼はいつも馬車まで迎えに来てくれるではないか。これは予想できた事態。駄々をこねるなら屋敷の中ですべきだったし、ここまで来たら腹を括るべきだった。
「嫌いではありません。嫌いではありませんが……」
「が?」
オルガ様、なぜ馬車に乗り込むのでしょうか?
彼は狭い馬車の中に乗り込むと、扉を閉めてしまった。カーテンで外界とは仕切られていて、ここは密室だ。
胸は容易く高鳴る。
「……いえ、今日はなんだか調子が悪いみたいで。風邪でしたら、オルガ様に迷惑がかかりますから」
わざとらしく手の甲で額を触る。ついでに上気した頬も冷やした。熱いような気がする。もし熱があるなら、風邪ではなく知恵熱ではあるが。
「風邪か……それは心配だ」
「えっ!?」
オルガ様の顔が急に近づいてきて、私は小さな悲鳴を上げた。
コツンと額が合わさる。く、唇が近い……!
また口づけられるのでは?
しかし、昨日のように唇が合わさることはなく、すぐに離れていった。
「熱はないようだ。だが、頬は少し赤みを帯びているな。城にはいい医師がいる。診てもらおう」
「い、いえ! いえいえ! 大丈夫です! 熱がないなら、私の勘違いみたいですわね」
ただ熱を心配してくれただけだというのに、勝手に勘違いしてなんて。破廉恥なのは私だ!
「無理はよくない。今日はこのまま屋敷に送ろう」
「ええ、そうですわね。今日は帰って休みますから、オルガ様はお仕事――……え?」
オルガ様はにこりと笑うと、御者に馬車を出すように命じる。行き先は私の屋敷。逆戻りだ。
彼は入ってきたときは向かい側に座っていたが、今は隣に座る。豪奢で広めの馬車なのにぴったりとくっついている。
「オルガ様もご一緒に?」
「何かあってはいけないからね。それに、君との時間は私にとって癒やしなんだ。送り届ける権利を奪わないでほしい」
そう言われてだめだと言えるだろうか。私は小さく頷くことしかできない。
ああ、頬が熱い。本当に熱が出そうだわ。
「実は昨日、無理に口づけたから嫌われたかと思って心配した」
「そんな……ことは」
ごにょごぎょと語尾が弱くなる。嫌ってはいない。でも会うのは恥ずかしいと思った。
「今日も迎えに行った馬車がここに止まったとき安堵したんだ。もう会ってくれなかったらどうしようかと思った」
「迎えが来たら行きます。だって、こ、恋人ですから」
恥ずかしい。彼との関係を自ら「恋人」と言うのは初めてだった。もしかしたら、騙されているのかもしれないとずっと思っていたからだ。
でも、ここまでしてくれる彼をどう疑えばいいのだろうか。もしこのまま疑い続けていれば、不運の悪魔がこの縁まで刈り取ってしまうのではないかと不安になった。
一度くらい、運命に身を任せてもいいわよね。
「ようやく私を恋人だと認めてくれたんだ。嬉しいよ」
オルガ様の手が私の頬を撫でる。もう慣れた行為のはずなのに、恥ずかしさが勝った。
「口づけてもいい?」
「それは……聞くようなことですか?」
「昨日反省したんだ。無理強いはよくないと」
長いまつげが僅かに震える。そんな顔で見ないでほしい。
「一度や二度は変わらないのでしょう? なら、三度だってたいした問題ではないと思います」
「弱ったな。昨日はそうでも言わないと逃げられると思ったんだ」
彼の指が私の唇をなぞる。それは口づけと何ら変わらないのではないだろうか。私の唇と彼の指が触れあっているのだから。
「も、もう逃げません……」
「本当に?」
彼の問いに小さく頷くと、指がそっと離れていく。淡く感じていた温もりが消えると寂しさを感じるものだ。しかし、その寂しさを拭うように彼の唇が重なった。