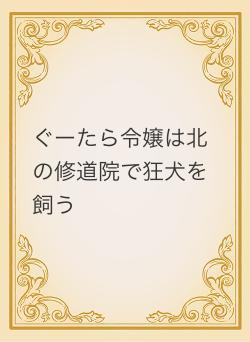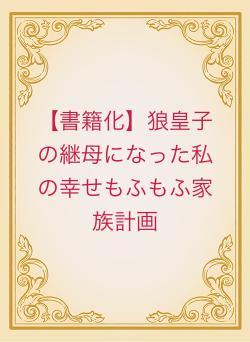その日から、毎日彼は子爵家に迎えをよこす。よくこの奇人と呼ばれた私に飽きずに恋人を続けているものだ。
オルガ様の愛は留まることを知らず。月に一度はドレスが贈られてきて、それを着て夜会に参加する。女性からの刺さるような視線と、羨望。不運な私なら、視線だけで死ぬ可能性もある。
そんなやられかねない状況の中、会場裏に呼び出されてワインをかけられ……ることはなかった。常に、というかずっとオルガ様が私の側にいるからだ。
誘拐され、悪い男に手込めにされそうになったり――などもない。もともと不運回避のため、引きこもり気味の私。お出かけはいつもオルガ様が用意してくれた馬車。
抜かりはないのだ。
そんな感じでのらりくらりとオルガ様の恋人をしている私だが、困っていることがある。――彼の溺愛が最近輪をかけてひどくなっているのだ。
最初こそ、詐欺か何かだと思っていたわけだけれど、付き合っていくうちにそんなことをする人ではないことがわかった。なら、なんで私を恋人にするのかという話なのだが、それはまだわからない。
ただ、彼は夜に日傘をさしても、「いつも素敵な傘を用意しているね」と新しい傘を贈ってくれる。ワインを必要以上に怖がっても、「私も酒は得意ではないから」とスマートにワインから離してくれるのだ。
なので、最近の勝率は格段に上がっている。不運が起死回生をかけ、屋敷の中で起るようになったのは困った話ではあるが。
ああ、不運の神様。どうか、彼にだけは私の不運を移さないでください。
雨の日も、風の日も豪奢な馬車は私を乗せ、どなどなと城へ連れていった。
「マリエル、すまない。今日は姫様方が友人を呼んでそこかしこでパーティをしているらしい。ここしか空いていなくてね」
「それは構いませんが……、私はお仕事のお邪魔ではありませんか?」
ここは魔導師長に与えられた執務室。Lの形をした部屋は、窓以外の壁に本が並び、奥には大きな机が一つ。
よくわからない道具がところ狭しと置かれ、客を迎えるテーブルと椅子は端に追いやられていた。
「ずっといてくれたほうが仕事もはかどりそうだよ。私の心配をしてくれるなんて嬉しいよ」
「お邪魔でなければいいのです!」
肩を抱いてこめかみに口づける。
毎日この調子なので、これくらいで恥ずかしがってなどいられない! でも恥ずかしいものははずかしい。
今日は馬車まで迎えに来たときに指先に一度、そして今のこめかみに一度。計二回。
不運の回数しか数えてこなかった私が、口づけの回数を数えるようになるとは思わなかった。
「いつも思っていたのですが、なぜ、オルガ様は休憩時間を私との時間に充てるのですか? ご迷惑でしょう?」
彼は華やかな顔立ちのわりに、とても真面目で良い人なのだ。私と毎日会っているが、それは休憩時間らしく、怠けているわけではないのだという。
休憩に恋人を呼びつける男など聞いたことはないが、天才の考えることは常人にはわからないというし。『マリエルという女が毎日オルガ様にちょっかいをかけている』という言われない噂もあったのだが、毎日仲睦まじい姿を見せつけていたせいか、その噂もなくなった。
毎日愛されて幸せー! と、叫びたいところだが、なにせ私は不運体質である。この幸運には裏がある! あるに決まっているのだ。
もしかしたら、これは不幸の前兆。カウントダウンである可能性は否めないわ。
「休憩くらい愛する人と一緒にいたい。夜遅くては会いに行くこともできないからね。だが、毎日は迷惑だったね……」
「そんなことは! 断じて! お断りなどすれば、お父さまに何を言われるか……!」
まあ、正直二日に一回。いや、贅沢を言うならば、三日か四日に一回くらいに減らしてもらえたらと思うときはある。
そりゃあ、私は奇人なのでお茶会のお誘いもない。今、そんなところに行けば針のむしろだし、行くつもりもない。
「父上が許せば、断りたい?」
オルガ様がわかりやすく眉尻を落とす。心が痛んだ。
「違うのです! 嫌とかではなく……!」
「ではなく?」
「それは……その」
「教えてくれなくてはわからない」
ずいっと近づかれた顔。鼻先が当たりそうなほどの距離に、私は慌てて立ち上がった。
「ただ、緊張しちゃって。恋人などいたこともないものですから」
オルガ様の甘い囁きと、綺麗な顔に心臓がもたないのだ。恥ずかしさが勝って、私はオルガ様から距離を取る。
「ここって面白いですね。知らない物でいっぱい!」
魔導具というものだろう。興味も知識もないが、オルガ様の近くに座っているよりも断然気が楽だ。
「わっ!」
私はこのとき、忘れていた。己が不運体質であることを。
床に落ちていた書類に足を滑らせる。だから足下まで隠れるドレスは苦手だと何度言って……る場合ではない。
まあ、この不運は大きいものではない。紙で足を滑らせて転ぶなど、よくある不運のうちの一つだ。ちょっと頭に瘤をつくる程度なのでここは甘んじて受け入れよう。
「危ないっ!」
諦めたと同時に、私を抱きとめようとオルガ様が腕を伸ばす。これでは、先の夜会の二の舞だ。
抱きとめたオルガ様と一緒に床に倒れ込んだ先にあるのは、ファースト事故(キス)……はもう終えたので、二度目の事故だ。
不運を先読みしてきた私ならはわかる。
この回避方法はただ一つ。とばかりに、両手で唇を覆った。
当たったのは、オルガ様の唇と私の手の甲。
柔らかい唇の感触が手にひろがり、「勝った!」と思った。
不運の悪魔よ、今日は私の勝ちよ!
今日の最大級の不運はまたもや事故でオルガ様の唇を奪うことにあったのだと予測する。
とはいえ、床の上。私が押し倒す形で二人は重なり合っているわけで。今、人が入ってきたら完全に私は痴女だ。超美麗魔導師長の色香に当てられて襲った変態になってしまう。
「ごめんなさいっ! 今、起きますから。ちょっとまってくださいね」
唇から手を離し、オルガ様の頭の横に手をつく。起き上がろうとしたとき。オルガ様の左腕が私の腰を抱いた。
「オルガ様、これでは起き上がれません……!」
不運の足音が聞こえる。絶対に誰かがこの執務室に入ってきて、明日には噂になるだろう。早くしなければ!
「……ひどいな。私とはもう口づけもしたくないと?」
「いや、そんなことはないですけど……」
長いまつげが近い。腕をの力を緩めれば、行き着く先はオルガ様の唇だ。私の腕の力などたかがしれている。そんじょそこらの令嬢となんら変わりないのよ!
ぷるぷると震え出す腕。そろそろ……限界なんですってば。
「一度目は突然のことに驚いたが、二度目となると冷静になれるな」
「そう……ですか」
「マリエル。一度や二度、変わらないと思わないか?」
彼の言いたいことがわからずに、目を瞬かせる。しかし、すぐにその意味がわかる。彼の左腕が首元まで移動すると、強く押されたからだ。
自分の身体を支えるだけで精一杯だった私の腕はすぐに限界を迎える。
オルガ様は落ちた唇を迎えるようにして、受け止めたのだ。
オルガ様の愛は留まることを知らず。月に一度はドレスが贈られてきて、それを着て夜会に参加する。女性からの刺さるような視線と、羨望。不運な私なら、視線だけで死ぬ可能性もある。
そんなやられかねない状況の中、会場裏に呼び出されてワインをかけられ……ることはなかった。常に、というかずっとオルガ様が私の側にいるからだ。
誘拐され、悪い男に手込めにされそうになったり――などもない。もともと不運回避のため、引きこもり気味の私。お出かけはいつもオルガ様が用意してくれた馬車。
抜かりはないのだ。
そんな感じでのらりくらりとオルガ様の恋人をしている私だが、困っていることがある。――彼の溺愛が最近輪をかけてひどくなっているのだ。
最初こそ、詐欺か何かだと思っていたわけだけれど、付き合っていくうちにそんなことをする人ではないことがわかった。なら、なんで私を恋人にするのかという話なのだが、それはまだわからない。
ただ、彼は夜に日傘をさしても、「いつも素敵な傘を用意しているね」と新しい傘を贈ってくれる。ワインを必要以上に怖がっても、「私も酒は得意ではないから」とスマートにワインから離してくれるのだ。
なので、最近の勝率は格段に上がっている。不運が起死回生をかけ、屋敷の中で起るようになったのは困った話ではあるが。
ああ、不運の神様。どうか、彼にだけは私の不運を移さないでください。
雨の日も、風の日も豪奢な馬車は私を乗せ、どなどなと城へ連れていった。
「マリエル、すまない。今日は姫様方が友人を呼んでそこかしこでパーティをしているらしい。ここしか空いていなくてね」
「それは構いませんが……、私はお仕事のお邪魔ではありませんか?」
ここは魔導師長に与えられた執務室。Lの形をした部屋は、窓以外の壁に本が並び、奥には大きな机が一つ。
よくわからない道具がところ狭しと置かれ、客を迎えるテーブルと椅子は端に追いやられていた。
「ずっといてくれたほうが仕事もはかどりそうだよ。私の心配をしてくれるなんて嬉しいよ」
「お邪魔でなければいいのです!」
肩を抱いてこめかみに口づける。
毎日この調子なので、これくらいで恥ずかしがってなどいられない! でも恥ずかしいものははずかしい。
今日は馬車まで迎えに来たときに指先に一度、そして今のこめかみに一度。計二回。
不運の回数しか数えてこなかった私が、口づけの回数を数えるようになるとは思わなかった。
「いつも思っていたのですが、なぜ、オルガ様は休憩時間を私との時間に充てるのですか? ご迷惑でしょう?」
彼は華やかな顔立ちのわりに、とても真面目で良い人なのだ。私と毎日会っているが、それは休憩時間らしく、怠けているわけではないのだという。
休憩に恋人を呼びつける男など聞いたことはないが、天才の考えることは常人にはわからないというし。『マリエルという女が毎日オルガ様にちょっかいをかけている』という言われない噂もあったのだが、毎日仲睦まじい姿を見せつけていたせいか、その噂もなくなった。
毎日愛されて幸せー! と、叫びたいところだが、なにせ私は不運体質である。この幸運には裏がある! あるに決まっているのだ。
もしかしたら、これは不幸の前兆。カウントダウンである可能性は否めないわ。
「休憩くらい愛する人と一緒にいたい。夜遅くては会いに行くこともできないからね。だが、毎日は迷惑だったね……」
「そんなことは! 断じて! お断りなどすれば、お父さまに何を言われるか……!」
まあ、正直二日に一回。いや、贅沢を言うならば、三日か四日に一回くらいに減らしてもらえたらと思うときはある。
そりゃあ、私は奇人なのでお茶会のお誘いもない。今、そんなところに行けば針のむしろだし、行くつもりもない。
「父上が許せば、断りたい?」
オルガ様がわかりやすく眉尻を落とす。心が痛んだ。
「違うのです! 嫌とかではなく……!」
「ではなく?」
「それは……その」
「教えてくれなくてはわからない」
ずいっと近づかれた顔。鼻先が当たりそうなほどの距離に、私は慌てて立ち上がった。
「ただ、緊張しちゃって。恋人などいたこともないものですから」
オルガ様の甘い囁きと、綺麗な顔に心臓がもたないのだ。恥ずかしさが勝って、私はオルガ様から距離を取る。
「ここって面白いですね。知らない物でいっぱい!」
魔導具というものだろう。興味も知識もないが、オルガ様の近くに座っているよりも断然気が楽だ。
「わっ!」
私はこのとき、忘れていた。己が不運体質であることを。
床に落ちていた書類に足を滑らせる。だから足下まで隠れるドレスは苦手だと何度言って……る場合ではない。
まあ、この不運は大きいものではない。紙で足を滑らせて転ぶなど、よくある不運のうちの一つだ。ちょっと頭に瘤をつくる程度なのでここは甘んじて受け入れよう。
「危ないっ!」
諦めたと同時に、私を抱きとめようとオルガ様が腕を伸ばす。これでは、先の夜会の二の舞だ。
抱きとめたオルガ様と一緒に床に倒れ込んだ先にあるのは、ファースト事故(キス)……はもう終えたので、二度目の事故だ。
不運を先読みしてきた私ならはわかる。
この回避方法はただ一つ。とばかりに、両手で唇を覆った。
当たったのは、オルガ様の唇と私の手の甲。
柔らかい唇の感触が手にひろがり、「勝った!」と思った。
不運の悪魔よ、今日は私の勝ちよ!
今日の最大級の不運はまたもや事故でオルガ様の唇を奪うことにあったのだと予測する。
とはいえ、床の上。私が押し倒す形で二人は重なり合っているわけで。今、人が入ってきたら完全に私は痴女だ。超美麗魔導師長の色香に当てられて襲った変態になってしまう。
「ごめんなさいっ! 今、起きますから。ちょっとまってくださいね」
唇から手を離し、オルガ様の頭の横に手をつく。起き上がろうとしたとき。オルガ様の左腕が私の腰を抱いた。
「オルガ様、これでは起き上がれません……!」
不運の足音が聞こえる。絶対に誰かがこの執務室に入ってきて、明日には噂になるだろう。早くしなければ!
「……ひどいな。私とはもう口づけもしたくないと?」
「いや、そんなことはないですけど……」
長いまつげが近い。腕をの力を緩めれば、行き着く先はオルガ様の唇だ。私の腕の力などたかがしれている。そんじょそこらの令嬢となんら変わりないのよ!
ぷるぷると震え出す腕。そろそろ……限界なんですってば。
「一度目は突然のことに驚いたが、二度目となると冷静になれるな」
「そう……ですか」
「マリエル。一度や二度、変わらないと思わないか?」
彼の言いたいことがわからずに、目を瞬かせる。しかし、すぐにその意味がわかる。彼の左腕が首元まで移動すると、強く押されたからだ。
自分の身体を支えるだけで精一杯だった私の腕はすぐに限界を迎える。
オルガ様は落ちた唇を迎えるようにして、受け止めたのだ。