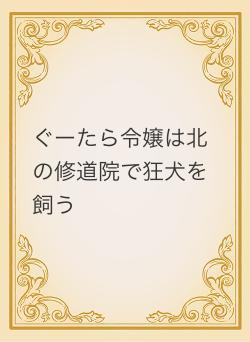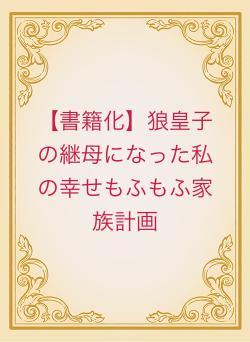私は頭を抱えるしかない。
今までの私なら、先の不運を見通す力もあったはずだ。
なぜ、なぜ……! なぜこうなったの!
「ほら、動かないで」
耳元にかかる吐息。彼の顔は真剣そのものだ。私は何もできず、彼のいいなりのまま、立ち尽くした。
「もう……諦めましょう」
「だめだ。君を傷つけることは許されない」
「私は髪の一本や二本、構いませんから……」
蚊の鳴くような声しかでなかった。
オルガ様との二度目の口づけを回避しようとした私は、まんまと薔薇の罠にかかってしまったのだ。今の私は蜘蛛の巣に捕らえられた蝶。あ、オルガ様のほうが数十倍美しいので、そのたとえは間違っているか。
つまり、私の癖毛の癖が強すぎて、髪の毛が薔薇に絡まって取れないのだ。それをオルガ様が必死に取ろうとしてくれている。
どなたか、早くオルガ様に鋏を貸して差し上げて……!
ずっと耳元で喋られて、こちらは気絶しそうなんだから!
倒れたいと思っても人間、簡単には倒れられないものなのだ。衝撃的なことがあって気絶できてしまう令嬢は運が良い。
その点、私は運が悪いので入らないところで倒れてしまう。
「よし、あともう少しまって……」
「お茶がさめてしまいますし……」
「そんなの入れ直してもらえばいい。今は君のほうが大切だ」
ファーストキスの効果なの? なんなの? それとも嫌がらせなの?
今日、私は初めて自分の癖毛を恨んだ。私がさらさらストレートヘアであったならば、今ごろこんなことにはなっていなかっただろう。
「よし、もう大丈夫。すまなかった。私が側にいながら」
「私が勝手に突っ込んでいっただけなので、気にしないでください」
私は私の不運を人の責任にするほど低俗な人間ではないの。不運体質にも矜持くらいあるのだ。
「お茶が冷めてしまったね。入れ直してもらおう」
げ。その展開はやばい。
「えっとこのままでもいいではありませんか。宮廷のお茶ならとても美味しいのでしょう?」
「だが、暖かいほうがもっと美味しい」
「いえ、丹精込めて茶葉を作られた方がいるのですから、敬意を払うのは当然です」
これだけは譲れないわ。だって、入れ直したら折角回避した不運に見舞われることになるんですから。
もちろん、紅茶がもったいない気持ちも大きい。王族やそれに近しい人にとってみれば、一匙の茶葉はたいした価値もないのだろう。しかし、我が家は貴族とはいえ、後ろから数えたほうが早い。お高いお茶を一口も飲まず捨てるなど、考えられない。
私はオルガ様が指示を出すよりも先に席へ座り、紅茶を口に含む。
あら、さすが高い茶葉。冷めても美味しい。でも、もったいないを強要するのは悪いことよね。私は慌てて宮廷の侍女にお願いする。
「オルガ様には暖かい物を差し上げて。これは私がいただくから」
オルガ様についだお茶が私の頭に被ったら、そのときは己の不運を呪うのみだ。
「いや、私もそれをもらおう。……マリエルと同じ物が飲みたい」
今日、私はなぜか、「マリエル嬢」から「マリエル」に昇進したのであった。
今までの私なら、先の不運を見通す力もあったはずだ。
なぜ、なぜ……! なぜこうなったの!
「ほら、動かないで」
耳元にかかる吐息。彼の顔は真剣そのものだ。私は何もできず、彼のいいなりのまま、立ち尽くした。
「もう……諦めましょう」
「だめだ。君を傷つけることは許されない」
「私は髪の一本や二本、構いませんから……」
蚊の鳴くような声しかでなかった。
オルガ様との二度目の口づけを回避しようとした私は、まんまと薔薇の罠にかかってしまったのだ。今の私は蜘蛛の巣に捕らえられた蝶。あ、オルガ様のほうが数十倍美しいので、そのたとえは間違っているか。
つまり、私の癖毛の癖が強すぎて、髪の毛が薔薇に絡まって取れないのだ。それをオルガ様が必死に取ろうとしてくれている。
どなたか、早くオルガ様に鋏を貸して差し上げて……!
ずっと耳元で喋られて、こちらは気絶しそうなんだから!
倒れたいと思っても人間、簡単には倒れられないものなのだ。衝撃的なことがあって気絶できてしまう令嬢は運が良い。
その点、私は運が悪いので入らないところで倒れてしまう。
「よし、あともう少しまって……」
「お茶がさめてしまいますし……」
「そんなの入れ直してもらえばいい。今は君のほうが大切だ」
ファーストキスの効果なの? なんなの? それとも嫌がらせなの?
今日、私は初めて自分の癖毛を恨んだ。私がさらさらストレートヘアであったならば、今ごろこんなことにはなっていなかっただろう。
「よし、もう大丈夫。すまなかった。私が側にいながら」
「私が勝手に突っ込んでいっただけなので、気にしないでください」
私は私の不運を人の責任にするほど低俗な人間ではないの。不運体質にも矜持くらいあるのだ。
「お茶が冷めてしまったね。入れ直してもらおう」
げ。その展開はやばい。
「えっとこのままでもいいではありませんか。宮廷のお茶ならとても美味しいのでしょう?」
「だが、暖かいほうがもっと美味しい」
「いえ、丹精込めて茶葉を作られた方がいるのですから、敬意を払うのは当然です」
これだけは譲れないわ。だって、入れ直したら折角回避した不運に見舞われることになるんですから。
もちろん、紅茶がもったいない気持ちも大きい。王族やそれに近しい人にとってみれば、一匙の茶葉はたいした価値もないのだろう。しかし、我が家は貴族とはいえ、後ろから数えたほうが早い。お高いお茶を一口も飲まず捨てるなど、考えられない。
私はオルガ様が指示を出すよりも先に席へ座り、紅茶を口に含む。
あら、さすが高い茶葉。冷めても美味しい。でも、もったいないを強要するのは悪いことよね。私は慌てて宮廷の侍女にお願いする。
「オルガ様には暖かい物を差し上げて。これは私がいただくから」
オルガ様についだお茶が私の頭に被ったら、そのときは己の不運を呪うのみだ。
「いや、私もそれをもらおう。……マリエルと同じ物が飲みたい」
今日、私はなぜか、「マリエル嬢」から「マリエル」に昇進したのであった。