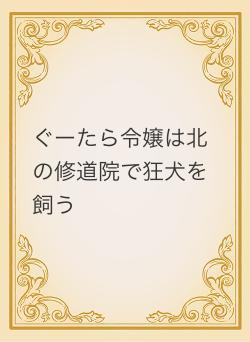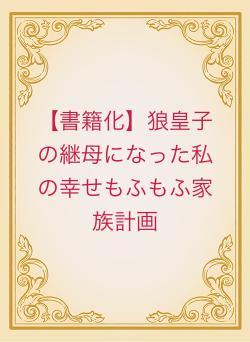魔導師長オルガ様と恋人となった次の日、私は些細な不運と戦うただの令嬢のままだと信じてやまなかった。
だって恋人になったとはいえ、それだけだし。昨日は仕事が忙しいらしくてすぐに帰っちゃったし。
私のステータスの奇人令嬢に魔導師長の恋人が加わっただけ。何も変わらない。
と、午前中の私は思っておりましたとも。
ああ、やばい。
私の本能がそう察したのは、日が高くなり始めたころ。子爵家の門の前に似つかわしくない大きくて豪華な馬車が止まったからだ。
私の部屋からばっちり見えちゃったのよ。
この場合の不運を回避する術を私は知らない。仮病を使って逃げたとき、屋敷の中で別の不運に見舞う可能性は九割に昇る。
不運回避の先は闇なのだ。
私は諦めて、その馬車に乗ることになった。
豪奢な馬車は私を王城へと連れて行く。ああ、車輪も点検していないし、馬の健康状態もわからない。心配だわ。
セーミット侯爵家の馬車に文句をつける女など、私くらいだろう。しかし、こっちは不運を親友にしているマリエル・セイメスなのだ。何度でも言おう。この馬車は、車輪が外れて崖の下に転落したり、馬が暴れて建物に激突したりしない?
不安を余所に、馬車は走る。マリエルを無事王城へと連れて行った。
「ええと……。なぜこのようなことになっているのでしょうか?」
宮廷魔導師の職場はもちろん城の中にある。つまり、魔導師長オルガ様の職場は城の中にあるということだ。それくらいは常識の範疇なのでよく知っている。
そうではない。
なぜ、私はオルガ様と薔薇園でテーブルを囲んでいるのかと言いたいのだ。しかも向かいあうのではなく隣同士。丸いテーブルに隣同士は変だわ。
「この城の中で美しい場所はいくつかあるが、この薔薇園はその中でも五本の指に入る。気に入ってくれただろうか?」
にこりと笑うオルガ様はまるで大天使。大輪の薔薇よりも麗しいので、あまり笑わないほうがいい。
「ええ、初めて拝見しましたが、よく手入れが行き届いていて、素晴らしい眺めです。一度は一人(・・)でゆっくり回ってみたいものです」
こういう高貴な身分の人が隣にいると、不運遭遇率が上昇するので美しい薔薇を愛でる暇などないのである。
心の中は頭を抱えた私でいっぱいだ。そうしているあいだにも、宮廷の侍女が紅茶を運んでくる。彼女、なんて不運そうな顔をしているのかしら?
類は友を呼ぶとはよく言ったもので、不運に傾きがちな人は見ただけでわかる。この場合、彼女が紅茶を零す確率は七割。
かわいそうな侍女は魔導師長の機嫌を損ね、退職させられるかもしれない。
私は早々に立ち上がった。
「オルガ様、折角の薔薇ですから少し近くで見ませんこと?」
「いいね。まだ準備ができるまで時間がある」
オルガ様は美しい身のこなしで私の手を取った。これが噂のプレミアム・エスコートか。
彼は夜会にもあまり参加しない。したとしても一人なのだ。その彼が数度女性を伴って夜会に参加したことがあるらしい。あくまでらしいである。私は見たことがないので。
そのときのオルガ様の身のこなしときたら、貴人を通り超し麗しさを超越していた……と、先のお茶会で伺った。私のような貴人……ではなく奇人に話しかけてくる変人はいないので、伺ったというよりは盗み聞いたが正解だ。
麗しさを超越したとはどういうことなのかと思ったが、ああ、たしかになと思うしかない。
優しく腰に添えられた手といい、女性の歩幅に合わせてゆっくり歩く長い足といい、スマートな男なら普通にやるであろうごくごく普通の行動だ。
けれど、顔が良すぎる。
彼が行えば、あれもそれもプレミアム・エスコートだろう。乱暴に扱われても女は瞳の形をハートに変化させるに決まっているのである。
「きゃっ」
高くて可愛い声が響いた。
ほらね。
私の予想は当たるのだ。侍女は転び、入れたての紅茶を勢いよく零した。私が座っていれば、頭から被っていたことだろう。
今ので三勝一敗ね。ちなみに、二勝分は屋敷の中で回避してきた分である。一敗はもちろん、この回避できなかった恋人(仮)との薔薇園デートに決まっている。
「申し訳ございません……!」
「いいのよ。焦らずに片付けて」
そう、誰にもかかっていないのだから悔やむことはない。かわいそうなので、今度会う機会があったら、あの子には不運回避術をおしえてあげようと思う。
「マリエル嬢は優しいんだね」
うっとりという形容詞が似合うほど、顔を綻ばせたオルガ様は、甘い吐息を漏らしながら、私の頬を撫でる。
「ちょっ……。さすがにそれ以上近づかれては……」
「私たちは恋人同士だろう? 構わないではないか」
「そうなのですが、まだ二日目。そう、二日目でしょう? オルガ様と違って、恋人などいたことのない私には心臓がもちません」
できるならば、不運を回避するために平常心を保っていたいのだ。この麗しい顔は好きでなくても緊張する。
恥じらうように目を伏せれば、彼の眉根が寄った。
「聞き捨てならないことを言うね」
「……え?」
「私だって君が初めての恋人だ」
「そうですか。大変ですね――……え?」
初めての恋人という単語はどうも二種類あるらしい。二十五才にもなって、しかもこの麗しさで一人の女とも恋人にならないなんてことあるのだろうか。
それに――……。
「信じていないね?」
「だって、オルガ様と親しい仲だと仰る女性を何人か拝見しておりますし」
「その女性は白昼夢を見る癖があるのだろう」
「そんな……」
あり得る。これだけ麗しいのだ。夢にでてもおかしくない。
「え、もしかしてこれも白昼夢?」
とうとう不運な私は白昼夢まで習得してしまったのだろうか。不幸の最中にいて、夢を見ることで回避しているのでは……!?
そこまでくると我ながら痛々しいというか。
オルガ様が肩を揺らして笑う。
「君は面白い人だ。君の目の前にいる私は本物だよ」
「夢の中の王子様はみんなそう言うのでしょう?」
だから、自称オルガ様の恋人が大勢現われるのだ。そこを理解していただきたい。
「さて、それはどう証明したらいいものか。もう一度口づければ、君は信じてくれるかな?」
陶器のような綺麗な指先が私の頬をなぞり、顎に触れる。私の目の前にいるのは本当にオルガ様なのだろうか。
彼に関する噂はどこでも耳にする。一つは甘い恋人の自慢話。もう一つは彼は堅物で、魔導が恋人のような人だと聞いたこともある。正反対の二人が合わせると、魔導が恋人なわけだが、愛する人ができると甘やかしてしまう男。だろうか。
思わず一歩後退った。
その一歩がさらなる不運を生むとは知らず。
だって恋人になったとはいえ、それだけだし。昨日は仕事が忙しいらしくてすぐに帰っちゃったし。
私のステータスの奇人令嬢に魔導師長の恋人が加わっただけ。何も変わらない。
と、午前中の私は思っておりましたとも。
ああ、やばい。
私の本能がそう察したのは、日が高くなり始めたころ。子爵家の門の前に似つかわしくない大きくて豪華な馬車が止まったからだ。
私の部屋からばっちり見えちゃったのよ。
この場合の不運を回避する術を私は知らない。仮病を使って逃げたとき、屋敷の中で別の不運に見舞う可能性は九割に昇る。
不運回避の先は闇なのだ。
私は諦めて、その馬車に乗ることになった。
豪奢な馬車は私を王城へと連れて行く。ああ、車輪も点検していないし、馬の健康状態もわからない。心配だわ。
セーミット侯爵家の馬車に文句をつける女など、私くらいだろう。しかし、こっちは不運を親友にしているマリエル・セイメスなのだ。何度でも言おう。この馬車は、車輪が外れて崖の下に転落したり、馬が暴れて建物に激突したりしない?
不安を余所に、馬車は走る。マリエルを無事王城へと連れて行った。
「ええと……。なぜこのようなことになっているのでしょうか?」
宮廷魔導師の職場はもちろん城の中にある。つまり、魔導師長オルガ様の職場は城の中にあるということだ。それくらいは常識の範疇なのでよく知っている。
そうではない。
なぜ、私はオルガ様と薔薇園でテーブルを囲んでいるのかと言いたいのだ。しかも向かいあうのではなく隣同士。丸いテーブルに隣同士は変だわ。
「この城の中で美しい場所はいくつかあるが、この薔薇園はその中でも五本の指に入る。気に入ってくれただろうか?」
にこりと笑うオルガ様はまるで大天使。大輪の薔薇よりも麗しいので、あまり笑わないほうがいい。
「ええ、初めて拝見しましたが、よく手入れが行き届いていて、素晴らしい眺めです。一度は一人(・・)でゆっくり回ってみたいものです」
こういう高貴な身分の人が隣にいると、不運遭遇率が上昇するので美しい薔薇を愛でる暇などないのである。
心の中は頭を抱えた私でいっぱいだ。そうしているあいだにも、宮廷の侍女が紅茶を運んでくる。彼女、なんて不運そうな顔をしているのかしら?
類は友を呼ぶとはよく言ったもので、不運に傾きがちな人は見ただけでわかる。この場合、彼女が紅茶を零す確率は七割。
かわいそうな侍女は魔導師長の機嫌を損ね、退職させられるかもしれない。
私は早々に立ち上がった。
「オルガ様、折角の薔薇ですから少し近くで見ませんこと?」
「いいね。まだ準備ができるまで時間がある」
オルガ様は美しい身のこなしで私の手を取った。これが噂のプレミアム・エスコートか。
彼は夜会にもあまり参加しない。したとしても一人なのだ。その彼が数度女性を伴って夜会に参加したことがあるらしい。あくまでらしいである。私は見たことがないので。
そのときのオルガ様の身のこなしときたら、貴人を通り超し麗しさを超越していた……と、先のお茶会で伺った。私のような貴人……ではなく奇人に話しかけてくる変人はいないので、伺ったというよりは盗み聞いたが正解だ。
麗しさを超越したとはどういうことなのかと思ったが、ああ、たしかになと思うしかない。
優しく腰に添えられた手といい、女性の歩幅に合わせてゆっくり歩く長い足といい、スマートな男なら普通にやるであろうごくごく普通の行動だ。
けれど、顔が良すぎる。
彼が行えば、あれもそれもプレミアム・エスコートだろう。乱暴に扱われても女は瞳の形をハートに変化させるに決まっているのである。
「きゃっ」
高くて可愛い声が響いた。
ほらね。
私の予想は当たるのだ。侍女は転び、入れたての紅茶を勢いよく零した。私が座っていれば、頭から被っていたことだろう。
今ので三勝一敗ね。ちなみに、二勝分は屋敷の中で回避してきた分である。一敗はもちろん、この回避できなかった恋人(仮)との薔薇園デートに決まっている。
「申し訳ございません……!」
「いいのよ。焦らずに片付けて」
そう、誰にもかかっていないのだから悔やむことはない。かわいそうなので、今度会う機会があったら、あの子には不運回避術をおしえてあげようと思う。
「マリエル嬢は優しいんだね」
うっとりという形容詞が似合うほど、顔を綻ばせたオルガ様は、甘い吐息を漏らしながら、私の頬を撫でる。
「ちょっ……。さすがにそれ以上近づかれては……」
「私たちは恋人同士だろう? 構わないではないか」
「そうなのですが、まだ二日目。そう、二日目でしょう? オルガ様と違って、恋人などいたことのない私には心臓がもちません」
できるならば、不運を回避するために平常心を保っていたいのだ。この麗しい顔は好きでなくても緊張する。
恥じらうように目を伏せれば、彼の眉根が寄った。
「聞き捨てならないことを言うね」
「……え?」
「私だって君が初めての恋人だ」
「そうですか。大変ですね――……え?」
初めての恋人という単語はどうも二種類あるらしい。二十五才にもなって、しかもこの麗しさで一人の女とも恋人にならないなんてことあるのだろうか。
それに――……。
「信じていないね?」
「だって、オルガ様と親しい仲だと仰る女性を何人か拝見しておりますし」
「その女性は白昼夢を見る癖があるのだろう」
「そんな……」
あり得る。これだけ麗しいのだ。夢にでてもおかしくない。
「え、もしかしてこれも白昼夢?」
とうとう不運な私は白昼夢まで習得してしまったのだろうか。不幸の最中にいて、夢を見ることで回避しているのでは……!?
そこまでくると我ながら痛々しいというか。
オルガ様が肩を揺らして笑う。
「君は面白い人だ。君の目の前にいる私は本物だよ」
「夢の中の王子様はみんなそう言うのでしょう?」
だから、自称オルガ様の恋人が大勢現われるのだ。そこを理解していただきたい。
「さて、それはどう証明したらいいものか。もう一度口づければ、君は信じてくれるかな?」
陶器のような綺麗な指先が私の頬をなぞり、顎に触れる。私の目の前にいるのは本当にオルガ様なのだろうか。
彼に関する噂はどこでも耳にする。一つは甘い恋人の自慢話。もう一つは彼は堅物で、魔導が恋人のような人だと聞いたこともある。正反対の二人が合わせると、魔導が恋人なわけだが、愛する人ができると甘やかしてしまう男。だろうか。
思わず一歩後退った。
その一歩がさらなる不運を生むとは知らず。