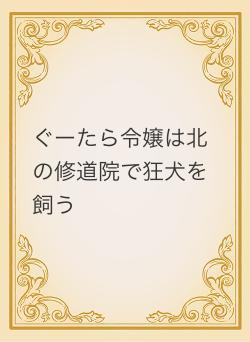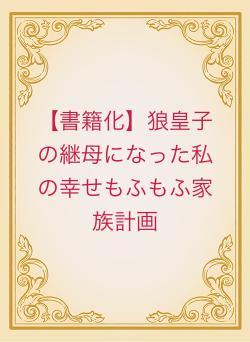なぜ? ああ、そっか。角がほしいと言っていた。取りに来たのね。
彼が小さく呪文を唱えると、蔦が燃えて消えて行く。不思議なことに蔦は燃えたのに、私のドレスは焦げ付きもしなかった。力の抜けた足では立っていられず、崩れ落ちそうになる。
彼が抱き留めてくれなければ、今ごろ倒れて顔半分が土に埋もれていただろう。
「遅くなってすまない」
「大丈夫です。今なら間に合います」
まだ悪魔はそこにいる。ほしかった角は手に入りますよ。私みたいな奇人を相手に噂まで流れたのに、悪魔の角も手に入らなければ踏んだり蹴ったりですもの。やっぱり彼は幸運だわ。
オルガ様の腕の中は優しくて、つい身を任せてしまいそうになる。
今日にも捨てられる身だというのに。捨てられるのが確定なら、今のうちに味わっておくのもいいかもしれない。
つい、身を預けてしまう。
「すぐに片付けよう。マリエルはここで待っているんだ」
彼は自分の上着を私の肩にかけると、ガゼボの柱に預けた。
いつも見せる朗らかな笑顔はない。まっすぐにゼノリスを見る目は視線だけで刺し殺しそうなほど強く冷ややかだ。
『あーあ。騎士が来ちゃったか。残念。もう少しで連れて行けそうだったのになぁ』
「無駄口を叩く前に、己の命の心配をするんだな」
足下を這っていた薔薇の蔦を、炎が燃やす。薔薇の中から這い出たゼノリスが肩を竦めた。
『あー怖い怖い。俺はまだ死ぬ予定はないんだわ。お嬢ちゃんのことはとりあえず諦めるから、今日のところは見逃してくれよ。あんたのほしいものはこれだろ?』
薔薇の蔦が宙を舞い、ゼノリスの角に当たる。ナイフのように鋭い蔦は、左側の角を根元から切り取った。
オルガ様の元にぽいっと角を投げる。
『お嬢ちゃん、死にたくなったらいつでも俺を呼んでくれ。すぐに迎えに来てやるからさ』
ウインクを見せて、ゼノリスは姿を消した。
「絶対に死なないので」
ゼノリスを呼ぶことはないだろう。
荒れた薔薇園と傷だらけの私。そして、オルガ様。ほしい物を手に入れた彼は、無情にここで別れを切り出すのだろうか。
なんともいたたまれない。
その日のうちに不運にけりをつけられるのは、非情にいいことだわ。親友(ゼノリス)が去って、運が回ってきたのかもしれない。
「よかったですね。角が手に入って。これで、秘薬が作れるのでしょう?」
「マリエル、君は知って――……」
身体中が痛くて、起き上がるのが辛い。ガゼボの柱の助けを借りながら立ち上がる。
「わかっております。全部、私のためでしょう?ですから、気にしないでください」
悲しくないと言ったら嘘になるが、それしか方法がなかったのなら、仕方ないではないか。私が勝手に舞い上がったせいだ。舞い上がらなければ、きっとうまくはいかずまだ悪魔は私の中にいたおとだろう。
私の失恋は必要な犠牲だということだ。
私は不運の中でも負けないマリエル・セイメス。最後まで気丈に振る舞いたい。
涙を堪え、背を向けた。
「今までのことは忘れますから、オルガ様も忘れてください。どうか、少しでもかわいそうだと思うのなら……」
私のことなど、忘れてほしい。あの日々は白昼夢で、縁のないマリエルが見た夢だ。そう思わせてもらえないだろうか。
返事は返ってこない。無言は肯定と取ってもいいわよね。
私は痛みのある足を必死に前に出した。
しかし、二歩目が大地を蹴り上げる前に、背中から抱きしめられてしまう。
「いやだ。忘れたくはない」
耳元で囁くのは優しいテノール。荒れた薔薇園には似つかわしくないほどの優しい声。
「君を離したくはない」
「そんなにファーストキスを奪われたことを恨んでいるのですか? まだ私をもてあそんでも足りないと?」
「違う。たしかに私は邪な思いで君に近づいた。だが、君と一緒にいるうちに気づいたんだ……」
抱きしめる腕が強くなる。
「はじめは演技だった。あのときの私は面倒な縁談の話と、居もしない恋人の噂で苛立っていたんだ。そんなとき、君が現われた」
「私を使って縁談を断って、噂話を払拭したのですか?」
「君に触れたとき、悪魔が取憑いていることはすぐにわかった。悪魔は人に不幸を招き、命を奪う。唯一祓う方法は、愛ある甘い言葉とそれに呼応する心。ああ、ついでに悪魔の角も手に入れば一石二鳥だと思っていた」
どうりで、ファーストキスの相手だからと優しかったわけだ。おかしいと思ったのよ。出会ってすぐに甘い台詞の数々。意味もなく愛されるなんておかしいもの。
「だが、いつの間にか君のことを本気で好きになっていた」
「え……? 嘘でしょう?」
「いや、不運に負けずに前を向く姿は私には輝いて見えたよ。だから、もう一度私に機会がほしい。どうか、私のほうを見て」
背中から伸ばされた腕が緩まる。どんな顔をして振り向けばいいの? 少しでも恋愛の経験があったら、わかったのだろうか。でも、どんな頑張って記憶を辿っても、縁のない私の記憶にはこういうときに見せる表情は出てこない。
こうなったら、女は度胸だわ!
覚悟を決めて振り返る。でも、恥ずかしくて見上げることはできない。ようやく慣れた綺麗な顔だったのに、まるで別の人のようなのだ。
彼の綺麗な指が頬をなぞり、顎に添えられた。優しく誘導されるように顔が上を向く。
「次は何を祓うために嘘をついているの?」
「もう嘘などつくものか。君に嘘を言って近づいたことを何度も後悔した。なかったことにしてくれとは言わない。やり直させてほしい。信じてもらうためなら、いくらでも私の誠意を差し出そう」
誠実なスカイブルーの目は、真実だと信じてもいいのだろうか? また白昼夢を見ている可能性は?
「どこまでが本当ですか? ファーストキスは?」
「あれは、本当だ。君が初めてで……君を最後にしたい」
彼の親指が唇をなぞる。
「……私にとっても、あれはファーストキスでした」
ファーストキスと呼べるような代物ではない。転んでぶつかった。あれは事故だ。あれをファーストキスに換算しなければならないのならば、私が赤子のころお父さまが口づけたという話のほうを優先させなければならないだろう。
でも、その次の口づけは私が望んで受け入れたものだ。
やっぱり好きなんだ。
嘘かもしれない。また悪魔が現われて、「次は右の角がほしかったんだ」と言われるかもしれない。もしそうなら、それまでに彼を骨抜きにすればいいだけじゃない。
私は不運さえも幸運に変えるマリエル・セイメスなのだから。
スカイブルーの瞳が私を捕らえてはなさない。
「どうか、マリエル。ファーストキスの責任を取らせてほしい。次は恋人ではなく、結婚してほしい」
「はい。私のファーストキスの責任、一生かけてとってください」
私はうんとかかとをあげて、顔を近づける。
彼は私を迎え入れるように唇を重ねた。
fin
彼が小さく呪文を唱えると、蔦が燃えて消えて行く。不思議なことに蔦は燃えたのに、私のドレスは焦げ付きもしなかった。力の抜けた足では立っていられず、崩れ落ちそうになる。
彼が抱き留めてくれなければ、今ごろ倒れて顔半分が土に埋もれていただろう。
「遅くなってすまない」
「大丈夫です。今なら間に合います」
まだ悪魔はそこにいる。ほしかった角は手に入りますよ。私みたいな奇人を相手に噂まで流れたのに、悪魔の角も手に入らなければ踏んだり蹴ったりですもの。やっぱり彼は幸運だわ。
オルガ様の腕の中は優しくて、つい身を任せてしまいそうになる。
今日にも捨てられる身だというのに。捨てられるのが確定なら、今のうちに味わっておくのもいいかもしれない。
つい、身を預けてしまう。
「すぐに片付けよう。マリエルはここで待っているんだ」
彼は自分の上着を私の肩にかけると、ガゼボの柱に預けた。
いつも見せる朗らかな笑顔はない。まっすぐにゼノリスを見る目は視線だけで刺し殺しそうなほど強く冷ややかだ。
『あーあ。騎士が来ちゃったか。残念。もう少しで連れて行けそうだったのになぁ』
「無駄口を叩く前に、己の命の心配をするんだな」
足下を這っていた薔薇の蔦を、炎が燃やす。薔薇の中から這い出たゼノリスが肩を竦めた。
『あー怖い怖い。俺はまだ死ぬ予定はないんだわ。お嬢ちゃんのことはとりあえず諦めるから、今日のところは見逃してくれよ。あんたのほしいものはこれだろ?』
薔薇の蔦が宙を舞い、ゼノリスの角に当たる。ナイフのように鋭い蔦は、左側の角を根元から切り取った。
オルガ様の元にぽいっと角を投げる。
『お嬢ちゃん、死にたくなったらいつでも俺を呼んでくれ。すぐに迎えに来てやるからさ』
ウインクを見せて、ゼノリスは姿を消した。
「絶対に死なないので」
ゼノリスを呼ぶことはないだろう。
荒れた薔薇園と傷だらけの私。そして、オルガ様。ほしい物を手に入れた彼は、無情にここで別れを切り出すのだろうか。
なんともいたたまれない。
その日のうちに不運にけりをつけられるのは、非情にいいことだわ。親友(ゼノリス)が去って、運が回ってきたのかもしれない。
「よかったですね。角が手に入って。これで、秘薬が作れるのでしょう?」
「マリエル、君は知って――……」
身体中が痛くて、起き上がるのが辛い。ガゼボの柱の助けを借りながら立ち上がる。
「わかっております。全部、私のためでしょう?ですから、気にしないでください」
悲しくないと言ったら嘘になるが、それしか方法がなかったのなら、仕方ないではないか。私が勝手に舞い上がったせいだ。舞い上がらなければ、きっとうまくはいかずまだ悪魔は私の中にいたおとだろう。
私の失恋は必要な犠牲だということだ。
私は不運の中でも負けないマリエル・セイメス。最後まで気丈に振る舞いたい。
涙を堪え、背を向けた。
「今までのことは忘れますから、オルガ様も忘れてください。どうか、少しでもかわいそうだと思うのなら……」
私のことなど、忘れてほしい。あの日々は白昼夢で、縁のないマリエルが見た夢だ。そう思わせてもらえないだろうか。
返事は返ってこない。無言は肯定と取ってもいいわよね。
私は痛みのある足を必死に前に出した。
しかし、二歩目が大地を蹴り上げる前に、背中から抱きしめられてしまう。
「いやだ。忘れたくはない」
耳元で囁くのは優しいテノール。荒れた薔薇園には似つかわしくないほどの優しい声。
「君を離したくはない」
「そんなにファーストキスを奪われたことを恨んでいるのですか? まだ私をもてあそんでも足りないと?」
「違う。たしかに私は邪な思いで君に近づいた。だが、君と一緒にいるうちに気づいたんだ……」
抱きしめる腕が強くなる。
「はじめは演技だった。あのときの私は面倒な縁談の話と、居もしない恋人の噂で苛立っていたんだ。そんなとき、君が現われた」
「私を使って縁談を断って、噂話を払拭したのですか?」
「君に触れたとき、悪魔が取憑いていることはすぐにわかった。悪魔は人に不幸を招き、命を奪う。唯一祓う方法は、愛ある甘い言葉とそれに呼応する心。ああ、ついでに悪魔の角も手に入れば一石二鳥だと思っていた」
どうりで、ファーストキスの相手だからと優しかったわけだ。おかしいと思ったのよ。出会ってすぐに甘い台詞の数々。意味もなく愛されるなんておかしいもの。
「だが、いつの間にか君のことを本気で好きになっていた」
「え……? 嘘でしょう?」
「いや、不運に負けずに前を向く姿は私には輝いて見えたよ。だから、もう一度私に機会がほしい。どうか、私のほうを見て」
背中から伸ばされた腕が緩まる。どんな顔をして振り向けばいいの? 少しでも恋愛の経験があったら、わかったのだろうか。でも、どんな頑張って記憶を辿っても、縁のない私の記憶にはこういうときに見せる表情は出てこない。
こうなったら、女は度胸だわ!
覚悟を決めて振り返る。でも、恥ずかしくて見上げることはできない。ようやく慣れた綺麗な顔だったのに、まるで別の人のようなのだ。
彼の綺麗な指が頬をなぞり、顎に添えられた。優しく誘導されるように顔が上を向く。
「次は何を祓うために嘘をついているの?」
「もう嘘などつくものか。君に嘘を言って近づいたことを何度も後悔した。なかったことにしてくれとは言わない。やり直させてほしい。信じてもらうためなら、いくらでも私の誠意を差し出そう」
誠実なスカイブルーの目は、真実だと信じてもいいのだろうか? また白昼夢を見ている可能性は?
「どこまでが本当ですか? ファーストキスは?」
「あれは、本当だ。君が初めてで……君を最後にしたい」
彼の親指が唇をなぞる。
「……私にとっても、あれはファーストキスでした」
ファーストキスと呼べるような代物ではない。転んでぶつかった。あれは事故だ。あれをファーストキスに換算しなければならないのならば、私が赤子のころお父さまが口づけたという話のほうを優先させなければならないだろう。
でも、その次の口づけは私が望んで受け入れたものだ。
やっぱり好きなんだ。
嘘かもしれない。また悪魔が現われて、「次は右の角がほしかったんだ」と言われるかもしれない。もしそうなら、それまでに彼を骨抜きにすればいいだけじゃない。
私は不運さえも幸運に変えるマリエル・セイメスなのだから。
スカイブルーの瞳が私を捕らえてはなさない。
「どうか、マリエル。ファーストキスの責任を取らせてほしい。次は恋人ではなく、結婚してほしい」
「はい。私のファーストキスの責任、一生かけてとってください」
私はうんとかかとをあげて、顔を近づける。
彼は私を迎え入れるように唇を重ねた。
fin