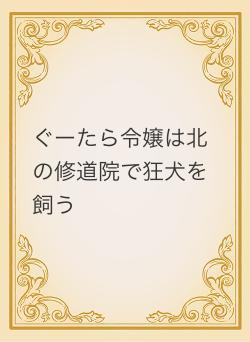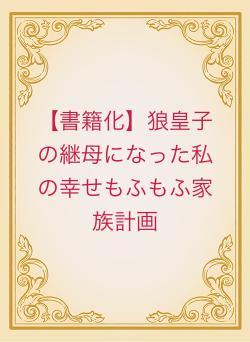「今までの不運の中で一番心臓をえぐる不運だわ」
ほら、やっぱり詐欺のようなものだったじゃない。信じた私が馬鹿だったのよ。彼は仕事のために悪魔の角がほしかっただけ。マリエル、私じゃない。
ふらふらと立ち寄ったのは薔薇園だった。感傷に浸るには城の中は人が多すぎる。その点、ここは誰でも入る場所ではないので、人影がないのだ。
管理のおじさまは私の顔を見て「今日も魔導師長様とかい?」と納得顔で入れてくれた。
顔パスだ。
感傷に浸りながら最後に薔薇を観賞して、蚕のように閉じこもろうと思う。元々引きこもり体質の私。運もなければ縁もない。お父さまは残念がるだろうけれど、こればかりは諦めてもらうしかなかった。
なんと説明しようかしら。
婚約しているわけでもないから、性格の不一致とか言えば良いかしらね。
大きなため息が漏れる。
ここでお茶を飲みながら何を話したのだったかしら? ドキドキばかりしていて、良く覚えていない。
やはり、彼のファーストキスは『私との』という飾りがついたものだったのだろう。そんな人に一度のみならず、何度も唇を許してしまった。一生の不覚……!
優しく唇をなぞる指を思い出す。あの甘い口づけも、全部、全部嘘だったなんて。悲しい。
『辛いならさ、楽になれる方法知ってるぜ?』
「そんな方法あるわけないわ。私は不運の女王マリエルよ。逃げたら転ける、隠れた穴には蛇がいるような人間なの。なめな――……え? だれ?」
目の前に現われたのは、華々しい薔薇園には不似合いな黒の塊。真っ白な肌と真っ赤な瞳。黒く艶やかな髪を持った男だった。頭には羊みたいな角。私を見下ろす目は爛々と輝いていた。
『ようやく会えたね。お嬢ちゃん』
「おじょ……って本当にどなた?」
『俺はゼノリス・ノーヴァ。お嬢ちゃんの親友さ』
あら、やいだわ。とうとう友達がいなさすぎて幻覚を見るようになったみたい。
『幻覚じゃない。お嬢ちゃん、不運は親友ってよく言ってたじゃないか。俺が不運の原因みたいなもんだし、親友だろ?』
不運……。私の不運はこいつが原因というわけ?
『そうそう。十年前からお嬢ちゃんとは一心同体だ。一緒に跳ねた泥を浴び、水に濡れた床に足を滑らせた仲だろ?』
「……って、なんで声に出してないのに答えてくれるの?」
『俺は悪魔だからな。取憑いた女の心の声くらい聞こえるさ』
だいぶ疲れているみたい。
『疲れてるんじゃなくて、憑かれてるんだよ。お嬢ちゃんは。ほら、さっき男たちも言ってたじゃないか。悪魔の角がほしーって。あいつらは俺のこれがほしいわけ』
長い指が頭の角を指す。ぐるぐると巻いた羊のような角。取憑いた悪魔を引き剥がす方法は、心が震えるような甘い台詞と愛。あれのためにオルガ様は私に甘い台詞を囁き、口づけまでしてくれていたのだ。
「さっさと忘れたいことを思い出させないでよ」
『あんなことそうそう忘れられないって。好きだったんだろ? ほら、死のうぜ? もう辛くて辛くてしかたねーだろ? 楽になるなら死ぬのが一番だ』
「死ぬ……ね。私に何か利点はあるのかしら?」
『そりゃあ、全部から逃げられる。これから起る不運からも、好きになった男への想いからも』
もう夜に日傘をさして指を指される心配もない。夜会でオルガ様に会ってどんな顔をして良いかわからないということもないのか。
悪くはない提案ね。
でも。
「お断りよ」
『は……? ええっ!? なんでだよ!? お嬢ちゃんにとって人生で初めての恋だろ? それが騙されてたんだぜ? もう生きていたくないだろーよ』
「馬鹿ね。初恋は実らないものなの。それに、魔導師長オルガと少しのあいだでも恋人だったとなれば箔もつくというものだわ」
それくらいで死んでたまるもんですか。
私は不運と人生を共にするマリエル・セイメスなの。男に騙されたくらいでめそめそはしても自分の首を絞めるわけがないじゃない。
不運でも不幸ではないわ。奇人と呼ばれても、家族は私に優しいし、友達はいなくても侍女たちが話し相手になってくれる。貴族の令嬢よりも平民の彼女たちのほうが気が合うのよ。
彼女たちは私を「おっちょこちょい」だと笑うけれど、「奇人」だとは馬鹿にしない。
週に一度のケーキは美味しいし、まだ続きが気になっている本もある。オルガ様との縁がなくなったくらいで全部手放してもいいとは思えないわ。
「やっぱり、死ぬのはないわ。親友かもしれないけど、その提案は受けられない。ごめんなさいね」
『……そ、そりゃあ困るぜ。俺は十年も我慢したわけよ。わかる?』
ゼノリスは大きなため息を吐き出す。
「意味が分からないわ。私に自殺教唆する暇があったら、あっちいってよ。私は不運を明日に持っていかない主義なの。今日だけは感傷に浸っていいんだから」
一つ一つ思い出をなぞって、涙を流すことは今日しかできない。不運を不幸にしない私の約束だからだ。
ゼノリスが眉根を寄せる。形のいい眉がゆがみ、機嫌の良さそうだった唇も歪に形を変えた。
『ありえねぇ……。ありえねぇよ』
「うるさいわ。親友なら黙っていてちょうだい」
折角静かなところで感傷に浸れると思ったのに。場所を変えよう。
ゼノリスに背を向けると、ひやりとした冷気が身体を覆った。
『折角、自ら死を選べるようにしてやったのに……。お嬢ちゃんはうまそうだから、そのまま連れて行ってやりたかったが、しかたねぇ。ここで喰うか』
「何を言っているの?」
『魔導師長の恋人になれたのに、お嬢ちゃんは悪魔がなにかも教えてもらえなかったもんなぁ。せっかくだから俺が教えてやるよ』
まるで凍り付いたように身体が動かない。吐く息も冷たく感じる。
『悪魔はな、人間に取憑いて不幸を呼ぶんだ。そしてじわじわと苦しめていくと、生きているのが嫌になるだろ? 俺たちはそんな人間が自ら首を絞めて死ぬのを待つんだ』
「そうなの。それで? 食べるの?」
『それは、ひ・み・つ。お嬢ちゃんがその細い首を自分で絞めれば答えがわかるぜ?』
ゼノリスの指が私の首をなぞる。
「なら、知らなくていいわ。死んだ女が好みなんでしょう? 早く放して」
『そりゃあできない。俺は十年も前からつばをつけていたんだ。自分で死なねーなら、俺が殺してやるよ』
首から指が離れ、ゼノリスが一歩二歩と後ろに下がる。
見えない空気がいまだ私の身体を押さえ、身動き一つ取れない。
ゼノリスが歯を見せて笑った瞬間、足に何かが巻き付いた。
「な、なにっ!?」
痛みに眉を顰める。
『痛いだろ? 自分で死んだほうが楽だぜ?』
「馬鹿にしないで! 私は死ぬ予定なんてないもの」
『そうかそうか。本当に残念だ。結構気に入ってたのになぁ』
足に巻き付いた物はぐるぐると腰を巡り胸まで回った。――薔薇だ。薔薇の蔦が身体を締め付けている。棘が肌に食い込み痛みに眉を寄せた。
「……ったいっ! やめて……!」
『大丈夫。綺麗に殺してやるよ。薔薇に埋もれて死ねるなんて、最高だろ?』
「全然最高じゃないし、死ぬ予定もないの」
『そう言うなって。魔界にも薔薇があるんだ。真っ黒で綺麗なんだぜ? それで飾ってやるよ。その頃にはおまえに意識はないかもしれねぇけど』
ぎゅうぎゅうと蔦が締め付ける。胸を通り過ぎ、首に巻き付いた。
もう……無理。誰か。……って、誰もいないんだったわ。こんなことなら、最後にオルガ様を殴ってすっきりするんだった。
まさか悪魔に襲われるだなんて、最悪だわ。明日はケーキを食べる日なのに。
意識を手放せたら楽なのだろうけど、少々図太い神経をしている私はまだ気を失えない。痛みが全身に走る。
『さあ、俺と一緒に魔界にいこ――……ぐっ』
頬に伸びた指が触れる前に離れていく。ゼノリスはまるで風に吹き飛ばされたかのように薔薇の中へと飛ばされた。
「悪いが、彼女は私の恋人なんだ。勝手に連れて行かれては困る」
「オル……ガさ、ま?」
ほら、やっぱり詐欺のようなものだったじゃない。信じた私が馬鹿だったのよ。彼は仕事のために悪魔の角がほしかっただけ。マリエル、私じゃない。
ふらふらと立ち寄ったのは薔薇園だった。感傷に浸るには城の中は人が多すぎる。その点、ここは誰でも入る場所ではないので、人影がないのだ。
管理のおじさまは私の顔を見て「今日も魔導師長様とかい?」と納得顔で入れてくれた。
顔パスだ。
感傷に浸りながら最後に薔薇を観賞して、蚕のように閉じこもろうと思う。元々引きこもり体質の私。運もなければ縁もない。お父さまは残念がるだろうけれど、こればかりは諦めてもらうしかなかった。
なんと説明しようかしら。
婚約しているわけでもないから、性格の不一致とか言えば良いかしらね。
大きなため息が漏れる。
ここでお茶を飲みながら何を話したのだったかしら? ドキドキばかりしていて、良く覚えていない。
やはり、彼のファーストキスは『私との』という飾りがついたものだったのだろう。そんな人に一度のみならず、何度も唇を許してしまった。一生の不覚……!
優しく唇をなぞる指を思い出す。あの甘い口づけも、全部、全部嘘だったなんて。悲しい。
『辛いならさ、楽になれる方法知ってるぜ?』
「そんな方法あるわけないわ。私は不運の女王マリエルよ。逃げたら転ける、隠れた穴には蛇がいるような人間なの。なめな――……え? だれ?」
目の前に現われたのは、華々しい薔薇園には不似合いな黒の塊。真っ白な肌と真っ赤な瞳。黒く艶やかな髪を持った男だった。頭には羊みたいな角。私を見下ろす目は爛々と輝いていた。
『ようやく会えたね。お嬢ちゃん』
「おじょ……って本当にどなた?」
『俺はゼノリス・ノーヴァ。お嬢ちゃんの親友さ』
あら、やいだわ。とうとう友達がいなさすぎて幻覚を見るようになったみたい。
『幻覚じゃない。お嬢ちゃん、不運は親友ってよく言ってたじゃないか。俺が不運の原因みたいなもんだし、親友だろ?』
不運……。私の不運はこいつが原因というわけ?
『そうそう。十年前からお嬢ちゃんとは一心同体だ。一緒に跳ねた泥を浴び、水に濡れた床に足を滑らせた仲だろ?』
「……って、なんで声に出してないのに答えてくれるの?」
『俺は悪魔だからな。取憑いた女の心の声くらい聞こえるさ』
だいぶ疲れているみたい。
『疲れてるんじゃなくて、憑かれてるんだよ。お嬢ちゃんは。ほら、さっき男たちも言ってたじゃないか。悪魔の角がほしーって。あいつらは俺のこれがほしいわけ』
長い指が頭の角を指す。ぐるぐると巻いた羊のような角。取憑いた悪魔を引き剥がす方法は、心が震えるような甘い台詞と愛。あれのためにオルガ様は私に甘い台詞を囁き、口づけまでしてくれていたのだ。
「さっさと忘れたいことを思い出させないでよ」
『あんなことそうそう忘れられないって。好きだったんだろ? ほら、死のうぜ? もう辛くて辛くてしかたねーだろ? 楽になるなら死ぬのが一番だ』
「死ぬ……ね。私に何か利点はあるのかしら?」
『そりゃあ、全部から逃げられる。これから起る不運からも、好きになった男への想いからも』
もう夜に日傘をさして指を指される心配もない。夜会でオルガ様に会ってどんな顔をして良いかわからないということもないのか。
悪くはない提案ね。
でも。
「お断りよ」
『は……? ええっ!? なんでだよ!? お嬢ちゃんにとって人生で初めての恋だろ? それが騙されてたんだぜ? もう生きていたくないだろーよ』
「馬鹿ね。初恋は実らないものなの。それに、魔導師長オルガと少しのあいだでも恋人だったとなれば箔もつくというものだわ」
それくらいで死んでたまるもんですか。
私は不運と人生を共にするマリエル・セイメスなの。男に騙されたくらいでめそめそはしても自分の首を絞めるわけがないじゃない。
不運でも不幸ではないわ。奇人と呼ばれても、家族は私に優しいし、友達はいなくても侍女たちが話し相手になってくれる。貴族の令嬢よりも平民の彼女たちのほうが気が合うのよ。
彼女たちは私を「おっちょこちょい」だと笑うけれど、「奇人」だとは馬鹿にしない。
週に一度のケーキは美味しいし、まだ続きが気になっている本もある。オルガ様との縁がなくなったくらいで全部手放してもいいとは思えないわ。
「やっぱり、死ぬのはないわ。親友かもしれないけど、その提案は受けられない。ごめんなさいね」
『……そ、そりゃあ困るぜ。俺は十年も我慢したわけよ。わかる?』
ゼノリスは大きなため息を吐き出す。
「意味が分からないわ。私に自殺教唆する暇があったら、あっちいってよ。私は不運を明日に持っていかない主義なの。今日だけは感傷に浸っていいんだから」
一つ一つ思い出をなぞって、涙を流すことは今日しかできない。不運を不幸にしない私の約束だからだ。
ゼノリスが眉根を寄せる。形のいい眉がゆがみ、機嫌の良さそうだった唇も歪に形を変えた。
『ありえねぇ……。ありえねぇよ』
「うるさいわ。親友なら黙っていてちょうだい」
折角静かなところで感傷に浸れると思ったのに。場所を変えよう。
ゼノリスに背を向けると、ひやりとした冷気が身体を覆った。
『折角、自ら死を選べるようにしてやったのに……。お嬢ちゃんはうまそうだから、そのまま連れて行ってやりたかったが、しかたねぇ。ここで喰うか』
「何を言っているの?」
『魔導師長の恋人になれたのに、お嬢ちゃんは悪魔がなにかも教えてもらえなかったもんなぁ。せっかくだから俺が教えてやるよ』
まるで凍り付いたように身体が動かない。吐く息も冷たく感じる。
『悪魔はな、人間に取憑いて不幸を呼ぶんだ。そしてじわじわと苦しめていくと、生きているのが嫌になるだろ? 俺たちはそんな人間が自ら首を絞めて死ぬのを待つんだ』
「そうなの。それで? 食べるの?」
『それは、ひ・み・つ。お嬢ちゃんがその細い首を自分で絞めれば答えがわかるぜ?』
ゼノリスの指が私の首をなぞる。
「なら、知らなくていいわ。死んだ女が好みなんでしょう? 早く放して」
『そりゃあできない。俺は十年も前からつばをつけていたんだ。自分で死なねーなら、俺が殺してやるよ』
首から指が離れ、ゼノリスが一歩二歩と後ろに下がる。
見えない空気がいまだ私の身体を押さえ、身動き一つ取れない。
ゼノリスが歯を見せて笑った瞬間、足に何かが巻き付いた。
「な、なにっ!?」
痛みに眉を顰める。
『痛いだろ? 自分で死んだほうが楽だぜ?』
「馬鹿にしないで! 私は死ぬ予定なんてないもの」
『そうかそうか。本当に残念だ。結構気に入ってたのになぁ』
足に巻き付いた物はぐるぐると腰を巡り胸まで回った。――薔薇だ。薔薇の蔦が身体を締め付けている。棘が肌に食い込み痛みに眉を寄せた。
「……ったいっ! やめて……!」
『大丈夫。綺麗に殺してやるよ。薔薇に埋もれて死ねるなんて、最高だろ?』
「全然最高じゃないし、死ぬ予定もないの」
『そう言うなって。魔界にも薔薇があるんだ。真っ黒で綺麗なんだぜ? それで飾ってやるよ。その頃にはおまえに意識はないかもしれねぇけど』
ぎゅうぎゅうと蔦が締め付ける。胸を通り過ぎ、首に巻き付いた。
もう……無理。誰か。……って、誰もいないんだったわ。こんなことなら、最後にオルガ様を殴ってすっきりするんだった。
まさか悪魔に襲われるだなんて、最悪だわ。明日はケーキを食べる日なのに。
意識を手放せたら楽なのだろうけど、少々図太い神経をしている私はまだ気を失えない。痛みが全身に走る。
『さあ、俺と一緒に魔界にいこ――……ぐっ』
頬に伸びた指が触れる前に離れていく。ゼノリスはまるで風に吹き飛ばされたかのように薔薇の中へと飛ばされた。
「悪いが、彼女は私の恋人なんだ。勝手に連れて行かれては困る」
「オル……ガさ、ま?」