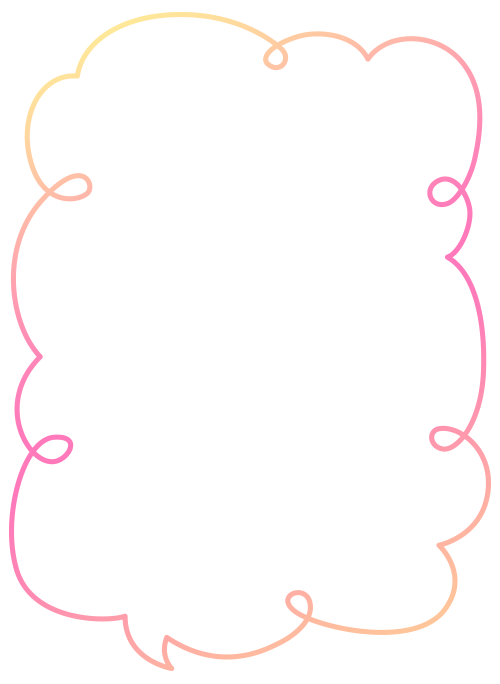「……だ、め」
これ以上の甘さに耐えられる気がしなくて抵抗してみるものの、それは通用するはずもなく、
「ダメって言いながら、俺が触ると嬉しそうに口元緩んでんの、気づいてねぇの?」
鼻で一蹴したかと思うと、髪に優しく唇を落とした。
そこには神経なんて通っていないのだからなにも感じるはずがないのに、そこから電流がビリッと走ったかのように熱が伝わった気がして……私は、限界を超えた。
「なーに顔隠してんの?ほら、目、合わせろよ」
「……やだ」
「俺のときは無理やり覗き込んできたよなぁ?」
「知らないもん」
「……俺が触るから、嬉しい?」
嬉しい……に決まってる。
好きな人から与えられるものはなんだって嬉しい。
心臓の音がうるさくて、壊れてしまうんじゃないかってたまに心配になるけど、それさえも幸せだ。
そう思っているのに。
口に出さない思いなんか、もちろん伝わるはずもない。
「……それとも、さっきのあの、チャラそうなやつにも触られて、同じ顔した?」
健斗は顔を歪ませて突拍子もない、有り得ないことを聞いてきた。
「そんなわけない!触られてドキドキするのは!健斗だ、け……」
「なに?聞こえないんだけど。ほら、もう一回言って?」
にやっと悪魔の笑みを浮かべるその姿に、さっきの悲しそうな表情は演技だったのだと気づく。
反射的に勢いよく否定して、でも途中から恥ずかしくなって。
最後の方はぼそぼそとしか喋れなかった私を意地悪く追い込んでくる。