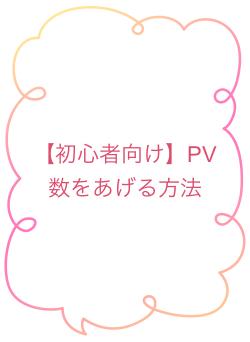「乗って。家まで一緒に帰ろう。」
運転席から降りて来た有が、
私が持っていた段ボールを持ち上げるとドアを開けた。
(…帰ろう。)
子供の時以来、言われたことのない言葉だった。
「うん…。」
誰も待っていない家に
一人で帰るのに慣れてしまっている私の胸を揺らした。
そんな私の表情を見て、有は小さく笑みを浮かべた。
「一緒に帰ろう。」
有には、なんだか心を
見透かされている気がする。
不思議だ。
この瞳に見つめられると
私達は似ている気さえしてくる。
こんな恵まれていそうな人と私なんかが
同じわけないのに。