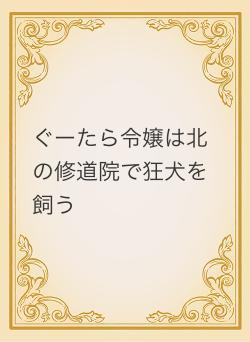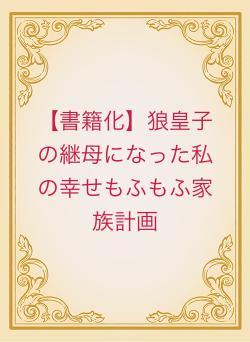歴劫(りゃくごう)修行の代わり。その言葉に愛紗(あいしゃ)は目を瞬かせる。
そのようなものが存在するならば、もっと早く――例えば十回失敗したあたりで提案してほしかった。
「ただし、この試験に失敗したならば、大仙(たいせん)の試験は生涯できん」
「つ、まり……。これが最後の機会となるわけでしょうか?」
「ああ、そういうことだ」
「最後……」
一族に大仙に至る者が生まれることが悲願だったと、両親はよく言っている。猫族(まおぞく)の地位が低いため、天帝から領地は一つももらえていない。狐族(こぞく)が統治する青丘(せいきゅう)の片隅を間借りしている状態だ。
九つある尻尾を揺らし、愛紗を見下す狐たちを思い出す。このまま青丘に帰れば、笑われるに違いない。
「やります! どんな試験でも! 次こそは成功させます!」
天帝は愛紗の言葉に強く頷いた。
「そのように難しい顔をしなくてもよい。代わりの修行は簡単だ。同じように人間界に転生し、一人の男に『老いの苦』まで導いてほしい。『老いの苦』の達人であるそなたなら簡単であろう?」
「つまり、長生きさせればよいと?」
「ああ、その男の魂は地界(ちかい)の鬼(おに)に気に入られていていてな。若くして命を奪われてしまう。事故、自死、あるいは他殺。そこから守ることがそなたの試験だ。どうだ? できそうか?」
「ただの人間が地界の鬼に狙われているのですか?」
地界の鬼は殺戮(さつりく)を好むという話は聞き知っている。しかし。仙界に鬼が現れることはないため、愛紗は会うことがなかった。人間界に現れるのもごく稀であるため、百度の転生人生でも鬼を目にしたことはない。
愛紗にとって鬼は、架空の物語の登場人物と変わらないのだ。
鬼が地界を抜け、人間界に入るには色々と制約があると聞く。その制約を受けてまでただの人間を目的に人間界へと入るものなのだろうか。
愛紗は首を傾げた。
「その人間の魂は特別でな。鬼にとって魅力的らしい」
「なるほど……。その者を鬼から守るのが代わりの試験になるということですね。陛下、一つ問題が。転生すれば私の記憶は消えてしまいます。守れるかは……」
「うむ。今回は特別にそなたの記憶を残しておこう。そして、仙術も制限はつくものの、使えるようにする。どうだ?」
「仙術を人間界で使ってよろしいのでしょうか?」
仙人は人間界で仙術を使うことを禁じられている。正確には、人間に術を使うことを禁じているのだ。変化の術など、自身に術をかけるのであれば問題ない。しかし、人間に使えばたちまち天は怒りの雷(いかづち)を浴びせるだろう。
だが、天帝が許せば話は別だ。
「ああ、だが無制限というわけにはいかない。そうだな……仙術を一度使うと三刻のあいだ猫の姿になってしまう。猫の姿では仙術は使えない。どうだ?」
つまり、三刻に一度は仙術が使えるということだ。三刻といえば、一日の四分の一に相当する。鬼も人間界では活動が制限されると聞く。日に四度も死の危険にさらされることはないだろう。それならば十分守っていける。しかし、気になることがあった。
「陛下、守るべき人を見つけ出すところから修行は始まりますか?」
「いや。人間は数多(あまた)おる。二人の魂を結んでおくことにしよう。地上で出会えば、すぐに分かるだろう。今回、運命録(うんめいろく)によれば、そなたが転生した人間が五つになるまでは、守るべき男に死の危険が訪れることもない。安心して幼少時代を過ごすといい」
「わかりました。謹んでお受けいたします」
胸の前で左の拳に右手を添え、深く頭を下げる。天帝は満足そうに頷き、「期待している」と言った。
これが最後の機会。背水の陣である。
そのようなものが存在するならば、もっと早く――例えば十回失敗したあたりで提案してほしかった。
「ただし、この試験に失敗したならば、大仙(たいせん)の試験は生涯できん」
「つ、まり……。これが最後の機会となるわけでしょうか?」
「ああ、そういうことだ」
「最後……」
一族に大仙に至る者が生まれることが悲願だったと、両親はよく言っている。猫族(まおぞく)の地位が低いため、天帝から領地は一つももらえていない。狐族(こぞく)が統治する青丘(せいきゅう)の片隅を間借りしている状態だ。
九つある尻尾を揺らし、愛紗を見下す狐たちを思い出す。このまま青丘に帰れば、笑われるに違いない。
「やります! どんな試験でも! 次こそは成功させます!」
天帝は愛紗の言葉に強く頷いた。
「そのように難しい顔をしなくてもよい。代わりの修行は簡単だ。同じように人間界に転生し、一人の男に『老いの苦』まで導いてほしい。『老いの苦』の達人であるそなたなら簡単であろう?」
「つまり、長生きさせればよいと?」
「ああ、その男の魂は地界(ちかい)の鬼(おに)に気に入られていていてな。若くして命を奪われてしまう。事故、自死、あるいは他殺。そこから守ることがそなたの試験だ。どうだ? できそうか?」
「ただの人間が地界の鬼に狙われているのですか?」
地界の鬼は殺戮(さつりく)を好むという話は聞き知っている。しかし。仙界に鬼が現れることはないため、愛紗は会うことがなかった。人間界に現れるのもごく稀であるため、百度の転生人生でも鬼を目にしたことはない。
愛紗にとって鬼は、架空の物語の登場人物と変わらないのだ。
鬼が地界を抜け、人間界に入るには色々と制約があると聞く。その制約を受けてまでただの人間を目的に人間界へと入るものなのだろうか。
愛紗は首を傾げた。
「その人間の魂は特別でな。鬼にとって魅力的らしい」
「なるほど……。その者を鬼から守るのが代わりの試験になるということですね。陛下、一つ問題が。転生すれば私の記憶は消えてしまいます。守れるかは……」
「うむ。今回は特別にそなたの記憶を残しておこう。そして、仙術も制限はつくものの、使えるようにする。どうだ?」
「仙術を人間界で使ってよろしいのでしょうか?」
仙人は人間界で仙術を使うことを禁じられている。正確には、人間に術を使うことを禁じているのだ。変化の術など、自身に術をかけるのであれば問題ない。しかし、人間に使えばたちまち天は怒りの雷(いかづち)を浴びせるだろう。
だが、天帝が許せば話は別だ。
「ああ、だが無制限というわけにはいかない。そうだな……仙術を一度使うと三刻のあいだ猫の姿になってしまう。猫の姿では仙術は使えない。どうだ?」
つまり、三刻に一度は仙術が使えるということだ。三刻といえば、一日の四分の一に相当する。鬼も人間界では活動が制限されると聞く。日に四度も死の危険にさらされることはないだろう。それならば十分守っていける。しかし、気になることがあった。
「陛下、守るべき人を見つけ出すところから修行は始まりますか?」
「いや。人間は数多(あまた)おる。二人の魂を結んでおくことにしよう。地上で出会えば、すぐに分かるだろう。今回、運命録(うんめいろく)によれば、そなたが転生した人間が五つになるまでは、守るべき男に死の危険が訪れることもない。安心して幼少時代を過ごすといい」
「わかりました。謹んでお受けいたします」
胸の前で左の拳に右手を添え、深く頭を下げる。天帝は満足そうに頷き、「期待している」と言った。
これが最後の機会。背水の陣である。