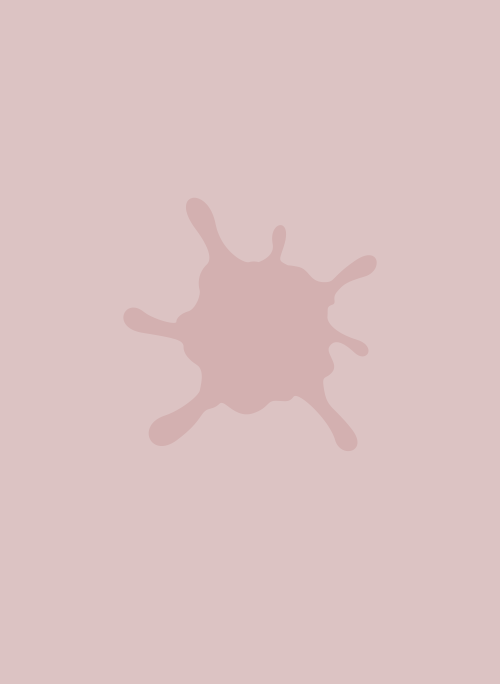そんな文隆の様子がおかしいと感じたのは梅雨入り前のある日だった。
「文隆、なんか今日体調悪い?」
朝からずっと青ざめている文隆に、私はそう声をかけた。
教室を出ようとしていた文隆は振り向き、その顔は驚きで目が丸くなっていた。
「どうして……?」
文隆は消え入りそうな声でそう言ってきた。
『どうしてわかったんだ?』
ということみたいだ。
「そんなの見たらわかるよ。ずっと顔色悪かったじゃん」
そう言うと、文隆は何か思案するように眉を寄せて黙り込んだ。
「どうしたの? なにか言いたいことがあるなら、聞くよ?」
「……うん」
文隆は一言だけ言ってうなづくと、私の手を握って歩き出した。
その手は女の子のように細くて一瞬ドキッとしてしまった。
文隆は本当にこのまま消えてしまうんじゃないか?
そんな不安まで胸によぎった。
「文隆、なんか今日体調悪い?」
朝からずっと青ざめている文隆に、私はそう声をかけた。
教室を出ようとしていた文隆は振り向き、その顔は驚きで目が丸くなっていた。
「どうして……?」
文隆は消え入りそうな声でそう言ってきた。
『どうしてわかったんだ?』
ということみたいだ。
「そんなの見たらわかるよ。ずっと顔色悪かったじゃん」
そう言うと、文隆は何か思案するように眉を寄せて黙り込んだ。
「どうしたの? なにか言いたいことがあるなら、聞くよ?」
「……うん」
文隆は一言だけ言ってうなづくと、私の手を握って歩き出した。
その手は女の子のように細くて一瞬ドキッとしてしまった。
文隆は本当にこのまま消えてしまうんじゃないか?
そんな不安まで胸によぎった。