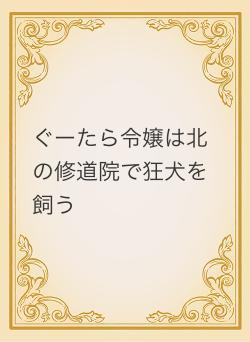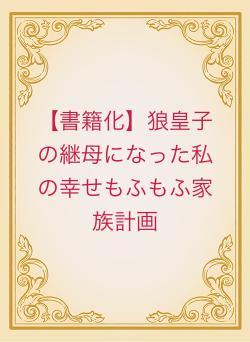問題です。「一晩遊んだ」とは何を示しているのでしょうか。
チェス、とか? 昔よくヴィンセントとハインツでチェス対決をしていたような。
世にはチェス友の会が存在していて、仕事後に夜な夜な……。なんて。
「誰だったかな。もう少しヒントをくれないかな?」
ハインツは悪気もなさそうに笑顔を見せている。私に向ける顔と変わらない笑顔だ。もしかして――……私のこと、気づいているのでは? からかおうと言うのね。ヴィンセントと一緒にいるから意地悪がうつったのかも。
後で「ずっと知っていたよ」と笑うつもりなんだわ。ハインツがそこら辺の女と「一晩遊ぶ」わけないもの。
「ヒントはなしよ。思い出したら教えてください」
「思い出したら何かもらえる?」
「なにが欲しいの?」
「そうだな。……ご褒美に君からの口づけが欲しい」
ハインツはそっと私の耳元で囁いた。
口づけ。口づけって言ったわ。
それだけではない。彼はそれがどういう意味なのか示すために、親指の腹で私の唇をそっと撫でたのだ。
思わず彼の唇を凝視する。
十九にもなれば口づけの意味くらい知っている。唇と唇を合わせるあれだ。ロマンス小説で愛し合う男女が唇を合わせる……あれ。
頬に熱が集まるのが分かった。だって、まだ口づけなんてしたことがないんだもの。
絶対、ハインツは私に気づいているんだ。じゃないと、出会ったばかりの女性に「口づけが欲しい」なんて言うわけがない。
こうなったら気づかれていないと思っているフリをして帰りにネタばらしをしよう。
「ええ、良いわ。口づけくらいお安いご用よ!」
私たちはあと一年もすれば結婚する予定の婚約者同士だ。口づけするくらい問題ではない。きっと、ハインツもそう思っているのだろう。
とうとう大人の階段を上るときがきたのね。
「よし。それで、君は今日私に会いに来たのかな?」
「いいえ、たまたま参加した夜会にあなたがいただけ。こっそり予定を調べて追いかけたりなんてしないから安心して」
こっそり予定を調べて参加しない夜会に参加しては……いたんだけど。嘘は言っていない。
「そう。今日は家族と?」
「いいえ、一人よ」
「へえ、一人で夜会に来るなんて勇気があるね」
「お茶会で王妃様のお話中に、ケーキを食べるより簡単よ」
「王妃陛下とお茶会をしたことが?」
「……た、たとえ話よ」
いけない。つい口が滑ってしまった。
「君は少し変わっているといわれるだろう?」
「そんなこと言われたことはないけど……」
「そうか。私の知っている女性の中では一番変わっているよ」
「失礼だわ」
もしかして、オリアーヌのことも変わっていると思っていたのだろうか。そんな女は嫌い?
「褒めているんだから、機嫌を悪くしないでほしい」
「それが褒めているのだとしたら、もう少し言葉は選んだほうがいいわ」
でも、褒めていると言われたら浮き足だってしまうわね。だって、婚約者に褒められたんだもの。今日は良い日だ。仮面のことは説明しなくてはいけなくなってしまったけれど、ハインツに会えた上に目の前で笑っているのだから。
お祖母様も婚約者に教えるくらいは許してくれるだろう。
緩む頬を引き締めることができない。たとえ変装中とはいえ、会うのは今シーズンが始まった最初の夜会以来なのだ。と、いうことは、かれこれひと月以上会っていないのね。
「さて、こんなところにいたら風邪を引く。そろそろ会場に戻ろう」
「ええ」
ハインツが当たり前のように手を差し伸べる。私はこの手が好きだ。少し暖かくて大きい。
「どうした? エスコートされるのは慣れてない?」
「いえ。ちょっと考えごとをしていただけ」
ハインツとともに会場に戻ると、視線が突き刺さる。それもそうか。ハインツは……なんだっけ? 二大貴公子? つまり、人気がある。オリアーヌ・メダンという婚約者がいてもお構いなしに色目を使う女性が後を絶たないのは、知っているのだ。
きっと、「どこの女よ」くらいのことを言っているに違いない。ソフィアのときに注目を浴びるのは初めてで、少し緊張してしまうわ。
ハインツは視線など気にした風もなく、私に向き直る。
「お嬢さん、一曲いかがですか?」
「もちろん、よろこんで」
女って単純だから、大好きな婚約者の笑顔一つで嫉妬とか注目とかどうでもよくなってしまうものなのよ。この世の女性全員がそうとは限らないけど、婚約者大好き同盟の皆さんは同じだと思う。
リズムに合ったステップ。全然荒々しくもない。一ヶ月以上ぶりだけど安定感が抜群だ。眠りながらでもダンスができそうだわ。
「田舎娘だと思ったが、ダンスはうまいんだね」
ハインツが耳元に唇を寄せる。
なんでかしら。ふだんよりも顔が近いような。いつもとは違う扱いに胸が高鳴っていた。
ダンスを二曲も踊ったあと、ハインツはまた整った顔を近づけて私の耳元に唇を寄せる。
「もっと、君と話しがしたい。二人きりになれるところに行こう」
そろそろ種明かしの時間ということね。でも、会場内で本当に二人きりになれる場所はない。いつ誰が入ってくるか分からないではないか。
「なら、街にアパルトマンを借りているの。そこに行かない? そこならゆっくり話ができるわ」
ハインツは目を見開いた。私がこっそりアパルトマンまで借りていることに驚いたのだろう。こうなったら秘密はなしだわ。仮面のことも今まで一人で遊んでいたことも全部話してすっきりさせないと。
「……いいね。送っていこう」
ハインツは私を連れて屋敷を出た。屋敷の人に迎えに来る予定の御者への伝言は頼んだから大丈夫。ロッド家の御者にアパルトマンの場所を教える。
最後までヴィンセントから声をかけられることはなかったのは幸いだったわ。
ロッド家の馬車に乗るのは久しぶりだ。
最初からこうすれば、よかったのよ。神様は私に、結婚する前に秘密はなくすべきだと言っているのだわ。
アパルトマンに着いたら、まずは謝らなければならない。ずっと秘密にしていたこと。ハインツを盗み見るはずが、目が合ってしまった。
「そ、そろそろアパルトマンに着くと思うわ」
ハインツは私の言葉に頷いた。そして、頬を撫でる。今日のハインツはいつもと違う。まるで別人と会っているようだ。彼はとても奥手で、恋人らしいことをすることはない。手を握るのも、人前でエスコートをするときだけだった。
今までは子どもとして見られていたのだろう。
彼の手は私の顎を捕え、引き寄せた。
ハインツの綺麗な顔が近づいてきて、慌てて両手で押さえる。
「待って! こんなところで困るわ!」
彼が口づけようとしたのは容易く分かった。婚約者同士ならおかしくはないかもしれないけれど、初めての口づけはもっとロマンチックな雰囲気がいい。
こんなことを言うから子どもだと思われるのだろう。それでも、初めての口づけはうっとりするような時間のはずなのだ。そうロマンス小説に書いてあったわ。
彼は首を傾げる。
「誘ったのは君じゃないか」
「なに言って……」
「そろそろ名前を教えてくれてもいいだろう?」
ハインツ、もしかして――……私の正体に気づいていない? フリじゃなくて? まさか、ね。
「ハインツ、本当に分からない?」
「そうだな……。名前を教えてくれたら思い出すかもしれない」
本当に気づいていないんだ。どうにか説明しないと! しかし、考える暇もなく、ハインツが覆い被さってきた。
「やめてっ!」
「君から誘ったのに、突然被害者ぶるのか?」
「違う。誘ったつもりなんてなかったわ」
「自分の家に誘っておいて?」
ハインツはむりやりドレスの胸元に手を差し入れようとした。
「いやっ!」
カッとなって、思いっきり足を蹴り上げる。彼は、声にならない声を上げると、馬車の中で小さくなった。
馬車がゆっくりと止まる。
ハインツは私の正体に気づいていなかった。つまり、知らない女性に手を出そうとしたのだ。婚約者がいるのに。
ふつふつと怒りが湧いてくる。
彼は眉間に皺を寄せながら顔を上げた。何か言おうとしているのか、彼は口を開いたけれど聞く気にもなれず、気づいたときには思いっきり頬を叩いていたのだ。
バチンッと高い音が馬車の中に響く。手のひらも痛い。きっと、同じだけハインツも頬が痛いはずだ。
「婚約者がいるのに、女性に手を出すなんて最低よっ!」
チェス、とか? 昔よくヴィンセントとハインツでチェス対決をしていたような。
世にはチェス友の会が存在していて、仕事後に夜な夜な……。なんて。
「誰だったかな。もう少しヒントをくれないかな?」
ハインツは悪気もなさそうに笑顔を見せている。私に向ける顔と変わらない笑顔だ。もしかして――……私のこと、気づいているのでは? からかおうと言うのね。ヴィンセントと一緒にいるから意地悪がうつったのかも。
後で「ずっと知っていたよ」と笑うつもりなんだわ。ハインツがそこら辺の女と「一晩遊ぶ」わけないもの。
「ヒントはなしよ。思い出したら教えてください」
「思い出したら何かもらえる?」
「なにが欲しいの?」
「そうだな。……ご褒美に君からの口づけが欲しい」
ハインツはそっと私の耳元で囁いた。
口づけ。口づけって言ったわ。
それだけではない。彼はそれがどういう意味なのか示すために、親指の腹で私の唇をそっと撫でたのだ。
思わず彼の唇を凝視する。
十九にもなれば口づけの意味くらい知っている。唇と唇を合わせるあれだ。ロマンス小説で愛し合う男女が唇を合わせる……あれ。
頬に熱が集まるのが分かった。だって、まだ口づけなんてしたことがないんだもの。
絶対、ハインツは私に気づいているんだ。じゃないと、出会ったばかりの女性に「口づけが欲しい」なんて言うわけがない。
こうなったら気づかれていないと思っているフリをして帰りにネタばらしをしよう。
「ええ、良いわ。口づけくらいお安いご用よ!」
私たちはあと一年もすれば結婚する予定の婚約者同士だ。口づけするくらい問題ではない。きっと、ハインツもそう思っているのだろう。
とうとう大人の階段を上るときがきたのね。
「よし。それで、君は今日私に会いに来たのかな?」
「いいえ、たまたま参加した夜会にあなたがいただけ。こっそり予定を調べて追いかけたりなんてしないから安心して」
こっそり予定を調べて参加しない夜会に参加しては……いたんだけど。嘘は言っていない。
「そう。今日は家族と?」
「いいえ、一人よ」
「へえ、一人で夜会に来るなんて勇気があるね」
「お茶会で王妃様のお話中に、ケーキを食べるより簡単よ」
「王妃陛下とお茶会をしたことが?」
「……た、たとえ話よ」
いけない。つい口が滑ってしまった。
「君は少し変わっているといわれるだろう?」
「そんなこと言われたことはないけど……」
「そうか。私の知っている女性の中では一番変わっているよ」
「失礼だわ」
もしかして、オリアーヌのことも変わっていると思っていたのだろうか。そんな女は嫌い?
「褒めているんだから、機嫌を悪くしないでほしい」
「それが褒めているのだとしたら、もう少し言葉は選んだほうがいいわ」
でも、褒めていると言われたら浮き足だってしまうわね。だって、婚約者に褒められたんだもの。今日は良い日だ。仮面のことは説明しなくてはいけなくなってしまったけれど、ハインツに会えた上に目の前で笑っているのだから。
お祖母様も婚約者に教えるくらいは許してくれるだろう。
緩む頬を引き締めることができない。たとえ変装中とはいえ、会うのは今シーズンが始まった最初の夜会以来なのだ。と、いうことは、かれこれひと月以上会っていないのね。
「さて、こんなところにいたら風邪を引く。そろそろ会場に戻ろう」
「ええ」
ハインツが当たり前のように手を差し伸べる。私はこの手が好きだ。少し暖かくて大きい。
「どうした? エスコートされるのは慣れてない?」
「いえ。ちょっと考えごとをしていただけ」
ハインツとともに会場に戻ると、視線が突き刺さる。それもそうか。ハインツは……なんだっけ? 二大貴公子? つまり、人気がある。オリアーヌ・メダンという婚約者がいてもお構いなしに色目を使う女性が後を絶たないのは、知っているのだ。
きっと、「どこの女よ」くらいのことを言っているに違いない。ソフィアのときに注目を浴びるのは初めてで、少し緊張してしまうわ。
ハインツは視線など気にした風もなく、私に向き直る。
「お嬢さん、一曲いかがですか?」
「もちろん、よろこんで」
女って単純だから、大好きな婚約者の笑顔一つで嫉妬とか注目とかどうでもよくなってしまうものなのよ。この世の女性全員がそうとは限らないけど、婚約者大好き同盟の皆さんは同じだと思う。
リズムに合ったステップ。全然荒々しくもない。一ヶ月以上ぶりだけど安定感が抜群だ。眠りながらでもダンスができそうだわ。
「田舎娘だと思ったが、ダンスはうまいんだね」
ハインツが耳元に唇を寄せる。
なんでかしら。ふだんよりも顔が近いような。いつもとは違う扱いに胸が高鳴っていた。
ダンスを二曲も踊ったあと、ハインツはまた整った顔を近づけて私の耳元に唇を寄せる。
「もっと、君と話しがしたい。二人きりになれるところに行こう」
そろそろ種明かしの時間ということね。でも、会場内で本当に二人きりになれる場所はない。いつ誰が入ってくるか分からないではないか。
「なら、街にアパルトマンを借りているの。そこに行かない? そこならゆっくり話ができるわ」
ハインツは目を見開いた。私がこっそりアパルトマンまで借りていることに驚いたのだろう。こうなったら秘密はなしだわ。仮面のことも今まで一人で遊んでいたことも全部話してすっきりさせないと。
「……いいね。送っていこう」
ハインツは私を連れて屋敷を出た。屋敷の人に迎えに来る予定の御者への伝言は頼んだから大丈夫。ロッド家の御者にアパルトマンの場所を教える。
最後までヴィンセントから声をかけられることはなかったのは幸いだったわ。
ロッド家の馬車に乗るのは久しぶりだ。
最初からこうすれば、よかったのよ。神様は私に、結婚する前に秘密はなくすべきだと言っているのだわ。
アパルトマンに着いたら、まずは謝らなければならない。ずっと秘密にしていたこと。ハインツを盗み見るはずが、目が合ってしまった。
「そ、そろそろアパルトマンに着くと思うわ」
ハインツは私の言葉に頷いた。そして、頬を撫でる。今日のハインツはいつもと違う。まるで別人と会っているようだ。彼はとても奥手で、恋人らしいことをすることはない。手を握るのも、人前でエスコートをするときだけだった。
今までは子どもとして見られていたのだろう。
彼の手は私の顎を捕え、引き寄せた。
ハインツの綺麗な顔が近づいてきて、慌てて両手で押さえる。
「待って! こんなところで困るわ!」
彼が口づけようとしたのは容易く分かった。婚約者同士ならおかしくはないかもしれないけれど、初めての口づけはもっとロマンチックな雰囲気がいい。
こんなことを言うから子どもだと思われるのだろう。それでも、初めての口づけはうっとりするような時間のはずなのだ。そうロマンス小説に書いてあったわ。
彼は首を傾げる。
「誘ったのは君じゃないか」
「なに言って……」
「そろそろ名前を教えてくれてもいいだろう?」
ハインツ、もしかして――……私の正体に気づいていない? フリじゃなくて? まさか、ね。
「ハインツ、本当に分からない?」
「そうだな……。名前を教えてくれたら思い出すかもしれない」
本当に気づいていないんだ。どうにか説明しないと! しかし、考える暇もなく、ハインツが覆い被さってきた。
「やめてっ!」
「君から誘ったのに、突然被害者ぶるのか?」
「違う。誘ったつもりなんてなかったわ」
「自分の家に誘っておいて?」
ハインツはむりやりドレスの胸元に手を差し入れようとした。
「いやっ!」
カッとなって、思いっきり足を蹴り上げる。彼は、声にならない声を上げると、馬車の中で小さくなった。
馬車がゆっくりと止まる。
ハインツは私の正体に気づいていなかった。つまり、知らない女性に手を出そうとしたのだ。婚約者がいるのに。
ふつふつと怒りが湧いてくる。
彼は眉間に皺を寄せながら顔を上げた。何か言おうとしているのか、彼は口を開いたけれど聞く気にもなれず、気づいたときには思いっきり頬を叩いていたのだ。
バチンッと高い音が馬車の中に響く。手のひらも痛い。きっと、同じだけハインツも頬が痛いはずだ。
「婚約者がいるのに、女性に手を出すなんて最低よっ!」