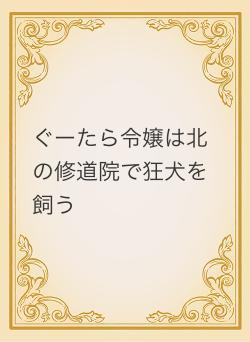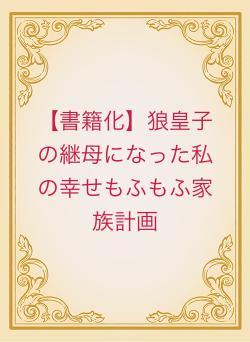前言撤回。
いけると思った自分を殴ってやりたい。
この一時間、あたしはずっと会場内を右往左往している。ヴィンセントとハインツは王太子と公爵家の長男。『偉い』を積み重ねたような偉さなのだから、椅子でも用意してもらってふんぞり返っていればいいのに! かれこれ一時間、彼らはさほど大きくない会場を歩いて回っている。
大勢の人を引き連れて。
狼だって檻の中でジッとしているだけではないもの。これくらい予想の範囲。けれど、常に二人が一緒ではないのは予想の範囲外よ!
友人のため夜会に駆けつけたのであれば、その友人とずっと話していればいいのに。最初に話し始めて数分で「楽しんでいってくれ」と挨拶されてから二人は別行動になってしまった。
「お嬢さん、一曲いかがですか?」
ヴィンセントとハインツのいる場所から一番遠い場所にいると、男に声をかけられた。
年頃の女性は二人の貴公子のもとに集まっているから暇だったのだろう。
他の人たちはほろ酔い気分でダンスをしているし、ずっと一人でいると逆に目立ってしまいそうだわ。
「ええ、よろこんで」
ヴィンセントとハインツは別々の場所で数人の女性に囲まれていた。ヴィンセントはいまだ婚約者もいないし、かっこうの餌食よね。うまく行けば王太子妃になれるとあって入れ食い状態だ。
そもそも今まで恋人の一人もいないのがおかしいのよ。もしかして、男の人が? なんて思ったこともあったけど、妹のジュエラが「それはない」と爆笑していたのを思い出す。あのジュエラがそう言うのだから、それはないのだろう。
理想が高すぎるのかもしれないわね。完璧主義ってやつ。
「お嬢さんはあまり見かけない顔だね」
「え? ええ、田舎から来たから」
すっかりダンス中だったことを忘れていた。この人は音の合わせられないタイプ。ワンテンポ遅れている。
会話のはじめって、いつも「見かけない顔」なのよね。ワンパターンだと思う。どうしていいか分からないときの「いい天気ですね」に近い。
そして、二言目も決まっている。だから、あたしはにっこり笑って見せた。
「一人で参加した女が珍しくて声をかけてくださったのですか?」
「え……っと、そう、だよ」
「田舎では普通なので、こっちでは非常識だなんて知らなかったの」
「へぇ……。田舎ではそうなんだ。じゃあ――……」
おっと。ハインツが近いわ。曲がりなりにも婚約者だし、顔と髪が変わっているだけでは気づかれてしまうかもしれない。逃げないと。
私は男の腕からするりと抜け出る。
「楽しかったわ。ありがとう!」
「えっ!? ちょっと! 君っ!?」
人だかりの中へと入っていく。木を隠すなら森と相場が決まっている。
ハインツから一定の距離離れられたことを確認して、ほっと息を吐き出す。すると、トンっと頬に何かが当たった。
「ごめんなさい」
顔を上げれば、紫の瞳。反射的に私は背を向けた。虫が出たときでもこんなに素早い反応をしたことはないだろう。
なんでヴィンセントがいるの? さっきまであっちでお嬢さん方と楽しそうにお喋りしていたじゃない。
「君、大丈夫?」
背中から声をかけられる。声を出すのはまずい。いや、もう一言聞かれてしまったから終わったかも。とりあえず、頷いて大丈夫だと主張しておこう。
「声を出せないくらい痛かった? 医者を呼んでもらおうか?」
いつもの意地悪はどこへやら。あ、今はオリアーヌじゃないから優しいのか。ヴィンセントがあたしの肩に手をかけた。
「……オリアーヌ?」
「ちっ! チガイマスワッ! モウ、ダイジョウブデスワッ!」
裏声で返事をして、あたしは慌てて走り出した。木々が集まって森になる。森があるということはそこには美しい泉があるということ。人だかりがあるということは二大貴公子の一人、ヴィンセントがいるということに気づかなかったあたしの大馬鹿……!
今、たしかにヴィンセントは「オリアーヌ」と私を読んだ。もしかして、バレた? でも、疑問形だったし顔は別人だ。こっそり振り返ってみると、ヴィンセントはキョロキョロと辺りを見回してあたしを探しているようだ。
次会ったときに知らぬふりをすれば、きっと大丈夫。でも、馬車がくるまでまだあと一時間近くもある……。絶体絶命。
会場を見回す。逃げられる場所は軽食が置いてあるテーブルの下? さすがにそれはできない。入るときも出るときも目立ってしまう。だったら、バルコニー? 外は寒いし、一時間は長すぎる。しかも、ヴィンセントがバルコニーまで追いかけて来たら、背水の陣ではないか。
最後の手段がないことはない。
「……よし」
仕方ないわ。腹を括るしかない。あたしはハインツの居場所を見定めると、一直線に走った。
ハインツは数人の男女と談笑している。社交嫌いの彼のことだ、そろそろ帰りたいなーなんて考えていたりして。
オリアーヌであるならば、笑顔を振りまいて彼らの中にすっと入ることも可能だけど、どこの馬の骨とも分からない女が溶け込むことはまず不可能だ。
かくなる上は。
「ハインツッ! 少し顔を貸して!」
あたしは、ハインツの腕をつかむと、バルコニーを目指した。ハインツは慌てているものの、ついてきてくれている。男と女の力の差は歴然。彼が抵抗すれば、あたしはなすすべがない。
冬という季節のせいか、バルコニーには誰もいなかった。ふだんなら「綺麗な星ね」と空を見上げるけれど、そんな余裕あるわけがない。星の数を数えるよりもうまい言い訳を唱えるようが先だ。
ゆっくり深呼吸をして振り返る。
「ハインツ、突然ごめんなさい」
会場の光を浴びて、キラキラと光る金の髪は見事でついため息が漏れてしまいそうになる。幼いころから見続けてきた婚約者だから、慣れてもいいはずなのに全然慣れない。年を追うごとにかっこよくなっている。
「いや、助かったよ。君のおかげで実りのない話から逃れられた」
肩をすくめる動作すら、神々しく見えるのだから末期だと思う。これは恋の病というやつだ。婚約者が尊い。
そうではなくて。あたしに残された方法はハインツに助けを求めることだ。ヴィンセントにバレるくらいなら、ハインツに秘密を教えてかくまってもらうほうが断然良い。
なんと言っても婚約者だし。
「あの……、ハインツ。私のこと、誰だかわかる……?」
顔と髪の色は違えど、体型は一緒。声も、瞳の色も変わらない。ただの幼馴染みが気づいたのだから、将来を約束した婚約者なら間違いなく気づくはずだ。
ハインツは私のことを上から下まで舐めるように見たあと、小さく首を傾げた。
「ああ、ごめん。一晩遊んだくらいの子の顔はおぼえていないんだ」
ハインツがにこりと笑う。
いけると思った自分を殴ってやりたい。
この一時間、あたしはずっと会場内を右往左往している。ヴィンセントとハインツは王太子と公爵家の長男。『偉い』を積み重ねたような偉さなのだから、椅子でも用意してもらってふんぞり返っていればいいのに! かれこれ一時間、彼らはさほど大きくない会場を歩いて回っている。
大勢の人を引き連れて。
狼だって檻の中でジッとしているだけではないもの。これくらい予想の範囲。けれど、常に二人が一緒ではないのは予想の範囲外よ!
友人のため夜会に駆けつけたのであれば、その友人とずっと話していればいいのに。最初に話し始めて数分で「楽しんでいってくれ」と挨拶されてから二人は別行動になってしまった。
「お嬢さん、一曲いかがですか?」
ヴィンセントとハインツのいる場所から一番遠い場所にいると、男に声をかけられた。
年頃の女性は二人の貴公子のもとに集まっているから暇だったのだろう。
他の人たちはほろ酔い気分でダンスをしているし、ずっと一人でいると逆に目立ってしまいそうだわ。
「ええ、よろこんで」
ヴィンセントとハインツは別々の場所で数人の女性に囲まれていた。ヴィンセントはいまだ婚約者もいないし、かっこうの餌食よね。うまく行けば王太子妃になれるとあって入れ食い状態だ。
そもそも今まで恋人の一人もいないのがおかしいのよ。もしかして、男の人が? なんて思ったこともあったけど、妹のジュエラが「それはない」と爆笑していたのを思い出す。あのジュエラがそう言うのだから、それはないのだろう。
理想が高すぎるのかもしれないわね。完璧主義ってやつ。
「お嬢さんはあまり見かけない顔だね」
「え? ええ、田舎から来たから」
すっかりダンス中だったことを忘れていた。この人は音の合わせられないタイプ。ワンテンポ遅れている。
会話のはじめって、いつも「見かけない顔」なのよね。ワンパターンだと思う。どうしていいか分からないときの「いい天気ですね」に近い。
そして、二言目も決まっている。だから、あたしはにっこり笑って見せた。
「一人で参加した女が珍しくて声をかけてくださったのですか?」
「え……っと、そう、だよ」
「田舎では普通なので、こっちでは非常識だなんて知らなかったの」
「へぇ……。田舎ではそうなんだ。じゃあ――……」
おっと。ハインツが近いわ。曲がりなりにも婚約者だし、顔と髪が変わっているだけでは気づかれてしまうかもしれない。逃げないと。
私は男の腕からするりと抜け出る。
「楽しかったわ。ありがとう!」
「えっ!? ちょっと! 君っ!?」
人だかりの中へと入っていく。木を隠すなら森と相場が決まっている。
ハインツから一定の距離離れられたことを確認して、ほっと息を吐き出す。すると、トンっと頬に何かが当たった。
「ごめんなさい」
顔を上げれば、紫の瞳。反射的に私は背を向けた。虫が出たときでもこんなに素早い反応をしたことはないだろう。
なんでヴィンセントがいるの? さっきまであっちでお嬢さん方と楽しそうにお喋りしていたじゃない。
「君、大丈夫?」
背中から声をかけられる。声を出すのはまずい。いや、もう一言聞かれてしまったから終わったかも。とりあえず、頷いて大丈夫だと主張しておこう。
「声を出せないくらい痛かった? 医者を呼んでもらおうか?」
いつもの意地悪はどこへやら。あ、今はオリアーヌじゃないから優しいのか。ヴィンセントがあたしの肩に手をかけた。
「……オリアーヌ?」
「ちっ! チガイマスワッ! モウ、ダイジョウブデスワッ!」
裏声で返事をして、あたしは慌てて走り出した。木々が集まって森になる。森があるということはそこには美しい泉があるということ。人だかりがあるということは二大貴公子の一人、ヴィンセントがいるということに気づかなかったあたしの大馬鹿……!
今、たしかにヴィンセントは「オリアーヌ」と私を読んだ。もしかして、バレた? でも、疑問形だったし顔は別人だ。こっそり振り返ってみると、ヴィンセントはキョロキョロと辺りを見回してあたしを探しているようだ。
次会ったときに知らぬふりをすれば、きっと大丈夫。でも、馬車がくるまでまだあと一時間近くもある……。絶体絶命。
会場を見回す。逃げられる場所は軽食が置いてあるテーブルの下? さすがにそれはできない。入るときも出るときも目立ってしまう。だったら、バルコニー? 外は寒いし、一時間は長すぎる。しかも、ヴィンセントがバルコニーまで追いかけて来たら、背水の陣ではないか。
最後の手段がないことはない。
「……よし」
仕方ないわ。腹を括るしかない。あたしはハインツの居場所を見定めると、一直線に走った。
ハインツは数人の男女と談笑している。社交嫌いの彼のことだ、そろそろ帰りたいなーなんて考えていたりして。
オリアーヌであるならば、笑顔を振りまいて彼らの中にすっと入ることも可能だけど、どこの馬の骨とも分からない女が溶け込むことはまず不可能だ。
かくなる上は。
「ハインツッ! 少し顔を貸して!」
あたしは、ハインツの腕をつかむと、バルコニーを目指した。ハインツは慌てているものの、ついてきてくれている。男と女の力の差は歴然。彼が抵抗すれば、あたしはなすすべがない。
冬という季節のせいか、バルコニーには誰もいなかった。ふだんなら「綺麗な星ね」と空を見上げるけれど、そんな余裕あるわけがない。星の数を数えるよりもうまい言い訳を唱えるようが先だ。
ゆっくり深呼吸をして振り返る。
「ハインツ、突然ごめんなさい」
会場の光を浴びて、キラキラと光る金の髪は見事でついため息が漏れてしまいそうになる。幼いころから見続けてきた婚約者だから、慣れてもいいはずなのに全然慣れない。年を追うごとにかっこよくなっている。
「いや、助かったよ。君のおかげで実りのない話から逃れられた」
肩をすくめる動作すら、神々しく見えるのだから末期だと思う。これは恋の病というやつだ。婚約者が尊い。
そうではなくて。あたしに残された方法はハインツに助けを求めることだ。ヴィンセントにバレるくらいなら、ハインツに秘密を教えてかくまってもらうほうが断然良い。
なんと言っても婚約者だし。
「あの……、ハインツ。私のこと、誰だかわかる……?」
顔と髪の色は違えど、体型は一緒。声も、瞳の色も変わらない。ただの幼馴染みが気づいたのだから、将来を約束した婚約者なら間違いなく気づくはずだ。
ハインツは私のことを上から下まで舐めるように見たあと、小さく首を傾げた。
「ああ、ごめん。一晩遊んだくらいの子の顔はおぼえていないんだ」
ハインツがにこりと笑う。