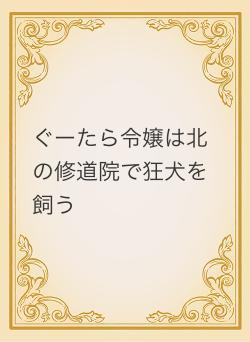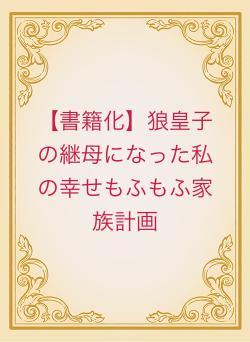婚約者のハインツは、あたしの手を取って言った。
「君こそが私の運命だ」
相手はとびきりの美男子だ。たとえば、これが本当に運命なら、私の心も躍っていただろう。拳一つ分くらい浮いていたかもしれない。あ、間違った今は「あたし」だ。
そういう設定にしたのだから、全うしなければ。
でもね、この運命っていうのがそもそも勘違いなのよね。運命なら、気づいているはずなのだ。
私が変装したあなたの婚約者だって。
でも彼は私の本当の姿に気づかない。まだ二度しか会っていない名も知らない女だと信じているのだ。
「そんな……困ります。だって、ハインツ様には婚約者がいらっしゃるんでしょう?」
しおらしく俯けば、ハインツの手が強くなる。直訳すると、『婚約者がいるのに他の女を口説くなよ』である。しかし、浮かれた男は気づかない。
あたしの正体にも、この直訳にも。
「確かに婚約者はいる……だが、あれは親が決めたもので私の意思ではないんだ。私が愛しているのは君だ」
「まだ出会って二度目ではありませんか。それで愛しているなんて言われても」
「時間なんて関係ない。ひと目みた瞬間から君に心を奪われていた。だから、また会いたくてここにいる」
ハインツはそう言って、あたしの顔をのぞき込む。返事をためらっていると、ハインツはあたしを抱きしめた。
「お願いだ……私の運命」
変装しているとはいえ、婚約者からは甘い言葉を向けられると同時に、実は愛されていなかったことが判明するとはこれ、いかに。滑稽もここまで極めると、笑いすら起きなくなる。
なんで、こんなことになってしまったの?
私は彼の腕の中、綺麗な青空を見上げる。まるで私をあざ笑うような快晴だった。
私(・)、オリアーヌ・メダンは恵まれている。
社交場に出るようになって、私はその言葉を何度耳にしただろうか。その言葉に異論はない。自分自身、恵まれていると思う。
容姿端麗な父は代々続く侯爵で、宮廷では重要な役割を担っているというし、母は三人の子どもがいるとは思えないほど美しい。
その血を継いだ私は、淡く色づくローズブロンドを持ち、瞳はエメラルドの如く輝いている。透けるような白い肌は今にも消えてしまいそうな儚さで、上気した頬は見る者が見れば勘違いしてしまうかもしれない。「天使だ」「妖精だ」と幼いころから言われてきたので、自己評価が高すぎるとうことはないだろう。
二人の兄は少し変わってはいるが優秀で、私が生きているうちにメダン家が落ちぶれることはない。つまり、私が悪役にでもならない限り、将来は安泰なのだ。
王妃様や王女とは個人的にお茶会を楽しむ間柄。
そして、極めつきの婚約者は王族の血を引くロッド公爵家の長男ハインツ・ロッドだ。
これだけそろっている中で、「全然恵まれていないわよ」なんて言えば、今夜にでも後ろからグサッと刺されるに違いない。
改めて考える。私に足りないものがあるだろうか。
こんなに恵まれている私にも、苦手なものがある。
黒くて、大きくて……意地が悪い。そう、目の前にいる男のことだ。
「やあ、オリアーヌ。相変わらず愛想が悪い」
「……ヴィンセント王太子殿下。ごきげんよう」
「今は公式の場ではないんだ。畏まる必要はない。私と君との仲だろう?」
なにが「私と君の仲」だ。ただの幼馴染みのくせによく言うわよ。
この広い王宮の廊下で、この世で一番会いたくない人に遭遇した。まだネズミが横切ったほうがマシだ。今日は星の巡りが悪いみたい。王宮に来たときの遭遇率は九割にのぼる。ヴィンセントはここに住んでいる人だから、当たり前なのかもしれない。けれど、広い王宮だから、せいぜい六割くらいにとどめておいて欲しいわ。
「今日は母上とお茶会だって? ……相変わらず君には同年代の友人がいないな」
「失礼ね。私にだって友人くらいいるわ」
「へー。妹のジュエラと? あとは?」
いちいち嫌みったらしい。とびきり仲が良いのは王女のジュエラくらいだけど、不定期ながらお茶会を開催して楽しくお喋りする友人の一人や二人いるわよ。
確かに数でいったら多くはない。でもその分太くなが~く付き合うのが私のモットーなの。美しくて身分も申し分ないお嬢様だもの、みんな遠慮してしまうのよ。過去に何度か友人を増やそうと思ったことはあったが、諸々の事情があって今の友人に落ち着いた。
ヴィンセントは昔から私にだけ意地悪なのだ。容姿が整っている分、たちが悪い。癖のある漆黒の艶やかな黒髪と紫の瞳。黙っていれば美男子。いや、私に声をかけるまではそれなりにいい男なのだ。王太子という身分もあって他の女性からの人気も高い。私からの人気は残念ながら最底辺だけど。
「あなたこそ王太子のくせに暇なんじゃない? こんな時間にほっつき歩いているなんて」
私の婚約者のハインツはヴィンセントとは従兄弟。そのハインツは朝から晩まで忙しい毎日を送っているという。そのうち公爵位を継ぐとはいえ、王太子のヴィンセントよりもハインツが忙しいなんてことあり得るのだろうか。
それとも、ハインツがヴィンセントの代わりに仕事を引き受けている……とか? ヴィンセントはずる賢いところがあるから、ハインツに仕事を押しつけるくらいしそう。
そして、ハインツは外見も中身も天使だからきっと断れないんだわ。かわいそうなハインツ。
「私は要領がいいからね。散歩する時間くらい作れるさ」
「要領よく人に仕事を押しつけているの間違いじゃないの?」
「王太子ともなれば、仕事は回す側になる。人を使うのも私の仕事だ」
いけしゃあしゃあと言ってくれるじゃない。絶対、ハインツに仕事を押しつけているに違いないわ。そのせいでハインツは私との時間をなかなか作れないのだ。
「そういえば、王妃様が今日のお茶会でヴィンセントのことをこぼしていたわよ。……忙しいからってなかなか社交場に顔も出さないせいで浮いた話一つない。って……」
ヴィンセントは私の五歳年上だから……二十四歳か。王太子だというのに、いまだ婚約者の一人もいない。
この国は大小五つの国に囲まれている。過去には争いが絶えない時代もあったようだけれど、今はいたって平和。政略結婚が必要な時代ではないせいか、王族同士の政略結婚も頻繁ではないようだ。
ゆえにヴィンセントの結婚は彼自身に任せられているらしいのだが、なかなか相手は決まらない。最近では王妃様もしびれを切らして勝手に決めてしまおうかと考えているようだ。ヴィンセントは何を考えているのか、それとも何も考えていないのか。
「時間があるなら、王妃様に顔を見せて差し上げたら? 言いたいことがたくさんあるそうよ」
ヴィンセントは私には意地悪だが、母親である王妃様には頭が上がらない。ヴィンセントにいじめられて泣いていると助けてくれるのはいつも王妃様だった。
「そうだ、オリアーヌ。ここで会ったのも何かの縁だ。送っていこうか?」
ヴィンセントは人好きのする笑顔で私を見下ろす。優しいことを言っているように見えるが、彼の考えなどお見通しだ。
「大丈夫よ。一人で帰れます。王妃様から逃げたいのは分かっているんですから」
「……バレたか。オリアーヌを送ったと言えば角が立たない。ここは一つ」
「残念だけど、共犯はいやよ。私は王妃様の味方なの」
なかなか離れないヴィンセントを振り切り、私は王宮を出た。ヴィンセントと馬車の中で二人きりとか考えただけでも身震いが出る。
屋敷に着くあいだ、どんな風にいじめられるか分かったものじゃないわ。屋敷に着いたら着いたで、お兄様と一緒になって私をいじるのは間違いない。長兄とヴィンセントは一歳違いで貴族の息子たちが通う学院でも仲がよかったと聞く。絶対に混ぜてはいけない二人なのだ。
それに、今日は私にとって特別な日なので、ヴィンセントなんかに邪魔されたくない。
この日のためにお茶会に参加したと言っても過言ではないのだから。今日、家には「ジュエラのところに泊まってくる」と言ってある。もちろんジュエラにも口裏を合わせてもらっているから完璧だ。
私はジュエラに手配してもらった御者に「いつもの場所に向かって」と指示を出した。
私には秘密がある。これは、婚約者のハインツも知らない特別な秘密だ。
「君こそが私の運命だ」
相手はとびきりの美男子だ。たとえば、これが本当に運命なら、私の心も躍っていただろう。拳一つ分くらい浮いていたかもしれない。あ、間違った今は「あたし」だ。
そういう設定にしたのだから、全うしなければ。
でもね、この運命っていうのがそもそも勘違いなのよね。運命なら、気づいているはずなのだ。
私が変装したあなたの婚約者だって。
でも彼は私の本当の姿に気づかない。まだ二度しか会っていない名も知らない女だと信じているのだ。
「そんな……困ります。だって、ハインツ様には婚約者がいらっしゃるんでしょう?」
しおらしく俯けば、ハインツの手が強くなる。直訳すると、『婚約者がいるのに他の女を口説くなよ』である。しかし、浮かれた男は気づかない。
あたしの正体にも、この直訳にも。
「確かに婚約者はいる……だが、あれは親が決めたもので私の意思ではないんだ。私が愛しているのは君だ」
「まだ出会って二度目ではありませんか。それで愛しているなんて言われても」
「時間なんて関係ない。ひと目みた瞬間から君に心を奪われていた。だから、また会いたくてここにいる」
ハインツはそう言って、あたしの顔をのぞき込む。返事をためらっていると、ハインツはあたしを抱きしめた。
「お願いだ……私の運命」
変装しているとはいえ、婚約者からは甘い言葉を向けられると同時に、実は愛されていなかったことが判明するとはこれ、いかに。滑稽もここまで極めると、笑いすら起きなくなる。
なんで、こんなことになってしまったの?
私は彼の腕の中、綺麗な青空を見上げる。まるで私をあざ笑うような快晴だった。
私(・)、オリアーヌ・メダンは恵まれている。
社交場に出るようになって、私はその言葉を何度耳にしただろうか。その言葉に異論はない。自分自身、恵まれていると思う。
容姿端麗な父は代々続く侯爵で、宮廷では重要な役割を担っているというし、母は三人の子どもがいるとは思えないほど美しい。
その血を継いだ私は、淡く色づくローズブロンドを持ち、瞳はエメラルドの如く輝いている。透けるような白い肌は今にも消えてしまいそうな儚さで、上気した頬は見る者が見れば勘違いしてしまうかもしれない。「天使だ」「妖精だ」と幼いころから言われてきたので、自己評価が高すぎるとうことはないだろう。
二人の兄は少し変わってはいるが優秀で、私が生きているうちにメダン家が落ちぶれることはない。つまり、私が悪役にでもならない限り、将来は安泰なのだ。
王妃様や王女とは個人的にお茶会を楽しむ間柄。
そして、極めつきの婚約者は王族の血を引くロッド公爵家の長男ハインツ・ロッドだ。
これだけそろっている中で、「全然恵まれていないわよ」なんて言えば、今夜にでも後ろからグサッと刺されるに違いない。
改めて考える。私に足りないものがあるだろうか。
こんなに恵まれている私にも、苦手なものがある。
黒くて、大きくて……意地が悪い。そう、目の前にいる男のことだ。
「やあ、オリアーヌ。相変わらず愛想が悪い」
「……ヴィンセント王太子殿下。ごきげんよう」
「今は公式の場ではないんだ。畏まる必要はない。私と君との仲だろう?」
なにが「私と君の仲」だ。ただの幼馴染みのくせによく言うわよ。
この広い王宮の廊下で、この世で一番会いたくない人に遭遇した。まだネズミが横切ったほうがマシだ。今日は星の巡りが悪いみたい。王宮に来たときの遭遇率は九割にのぼる。ヴィンセントはここに住んでいる人だから、当たり前なのかもしれない。けれど、広い王宮だから、せいぜい六割くらいにとどめておいて欲しいわ。
「今日は母上とお茶会だって? ……相変わらず君には同年代の友人がいないな」
「失礼ね。私にだって友人くらいいるわ」
「へー。妹のジュエラと? あとは?」
いちいち嫌みったらしい。とびきり仲が良いのは王女のジュエラくらいだけど、不定期ながらお茶会を開催して楽しくお喋りする友人の一人や二人いるわよ。
確かに数でいったら多くはない。でもその分太くなが~く付き合うのが私のモットーなの。美しくて身分も申し分ないお嬢様だもの、みんな遠慮してしまうのよ。過去に何度か友人を増やそうと思ったことはあったが、諸々の事情があって今の友人に落ち着いた。
ヴィンセントは昔から私にだけ意地悪なのだ。容姿が整っている分、たちが悪い。癖のある漆黒の艶やかな黒髪と紫の瞳。黙っていれば美男子。いや、私に声をかけるまではそれなりにいい男なのだ。王太子という身分もあって他の女性からの人気も高い。私からの人気は残念ながら最底辺だけど。
「あなたこそ王太子のくせに暇なんじゃない? こんな時間にほっつき歩いているなんて」
私の婚約者のハインツはヴィンセントとは従兄弟。そのハインツは朝から晩まで忙しい毎日を送っているという。そのうち公爵位を継ぐとはいえ、王太子のヴィンセントよりもハインツが忙しいなんてことあり得るのだろうか。
それとも、ハインツがヴィンセントの代わりに仕事を引き受けている……とか? ヴィンセントはずる賢いところがあるから、ハインツに仕事を押しつけるくらいしそう。
そして、ハインツは外見も中身も天使だからきっと断れないんだわ。かわいそうなハインツ。
「私は要領がいいからね。散歩する時間くらい作れるさ」
「要領よく人に仕事を押しつけているの間違いじゃないの?」
「王太子ともなれば、仕事は回す側になる。人を使うのも私の仕事だ」
いけしゃあしゃあと言ってくれるじゃない。絶対、ハインツに仕事を押しつけているに違いないわ。そのせいでハインツは私との時間をなかなか作れないのだ。
「そういえば、王妃様が今日のお茶会でヴィンセントのことをこぼしていたわよ。……忙しいからってなかなか社交場に顔も出さないせいで浮いた話一つない。って……」
ヴィンセントは私の五歳年上だから……二十四歳か。王太子だというのに、いまだ婚約者の一人もいない。
この国は大小五つの国に囲まれている。過去には争いが絶えない時代もあったようだけれど、今はいたって平和。政略結婚が必要な時代ではないせいか、王族同士の政略結婚も頻繁ではないようだ。
ゆえにヴィンセントの結婚は彼自身に任せられているらしいのだが、なかなか相手は決まらない。最近では王妃様もしびれを切らして勝手に決めてしまおうかと考えているようだ。ヴィンセントは何を考えているのか、それとも何も考えていないのか。
「時間があるなら、王妃様に顔を見せて差し上げたら? 言いたいことがたくさんあるそうよ」
ヴィンセントは私には意地悪だが、母親である王妃様には頭が上がらない。ヴィンセントにいじめられて泣いていると助けてくれるのはいつも王妃様だった。
「そうだ、オリアーヌ。ここで会ったのも何かの縁だ。送っていこうか?」
ヴィンセントは人好きのする笑顔で私を見下ろす。優しいことを言っているように見えるが、彼の考えなどお見通しだ。
「大丈夫よ。一人で帰れます。王妃様から逃げたいのは分かっているんですから」
「……バレたか。オリアーヌを送ったと言えば角が立たない。ここは一つ」
「残念だけど、共犯はいやよ。私は王妃様の味方なの」
なかなか離れないヴィンセントを振り切り、私は王宮を出た。ヴィンセントと馬車の中で二人きりとか考えただけでも身震いが出る。
屋敷に着くあいだ、どんな風にいじめられるか分かったものじゃないわ。屋敷に着いたら着いたで、お兄様と一緒になって私をいじるのは間違いない。長兄とヴィンセントは一歳違いで貴族の息子たちが通う学院でも仲がよかったと聞く。絶対に混ぜてはいけない二人なのだ。
それに、今日は私にとって特別な日なので、ヴィンセントなんかに邪魔されたくない。
この日のためにお茶会に参加したと言っても過言ではないのだから。今日、家には「ジュエラのところに泊まってくる」と言ってある。もちろんジュエラにも口裏を合わせてもらっているから完璧だ。
私はジュエラに手配してもらった御者に「いつもの場所に向かって」と指示を出した。
私には秘密がある。これは、婚約者のハインツも知らない特別な秘密だ。