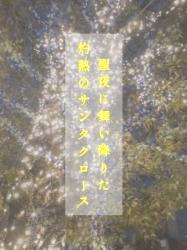返事をする間もなく、先輩の大きな手が私の髪の毛にそっと触れた。
「糸くずついてた」
「ありがとうございます……」
ゴミがついていた恥ずかしさと、触れられたドキドキで顔の熱がカーッと上がっていく。
多分糸くずの正体は手拭きのタオル。
しゃがんだ時に髪の毛に当たったんだと思う。
コップを手に取り、残っていたお茶を全部のどに流し込む。
……ダメだ。全然涼しくならない。
胃はもう充分涼しくなっているのに、顔だけが熱いまま。
もう一杯飲みたいけど、これ以上飲んだらトイレに行きたくなりそうだし。お腹も壊しちゃう。
「実玖ちゃん」
「はい? ひゃあ!」
横を向いた瞬間、頬にヒヤッと冷たい感触が広がり、小さく声を上げた。
「な、何するんですか……っ!」
「顔火照ってるみたいだから冷まそうかなって」
「どう? 涼しい?」と先輩はコップ片手にイタズラっ子みたいに笑っている。
さっきまで私と同じように焦ってたのに。いつの間に余裕戻ったの⁉
「俺、先に戻るね。おやすみ」
「……おやすみなさい」
返事をし、口を一文字に結んでそっぽを向く。
……先輩のバカ。目、冴えちゃったじゃん。