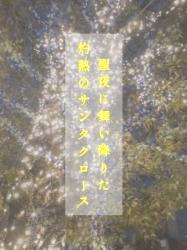バイトが終わった夜の9時過ぎ。
中学時代の友人からメッセージが届いていたので、帰宅してすぐ電話をかけた。
【はい、もしもし】
「もしもし? 今大丈夫?」
【うん。家にいるから。新淵が電話なんて珍しいね。どうしたの?】
あっけらかんとした口調。まるで自分が何をしたのか身に覚えのない様子。
腸が煮えくり返っているが、心を鎮めて冷静に答える。
「そんなのお前が1番わかってるくせに。どういうことか説明しろよ」
だが、怒りは完全に消えず。問い詰めるような言い方に。
電話に出て早々、ドスの利いた声で返答されたら、大半の人は恐怖を抱くか驚くか動揺するだろう。
しかし、このエリートお坊っちゃんは恐ろしいほど肝が据わっているため、一切うろたえることがない。
今も「もしかして妬いてるの〜?」とケラケラ笑っている。
「ふざけるな。こっちは真面目に聞いてるんだぞ」
【わー、こわーい。久しぶりの電話なのに、そんなに嫉妬しなくてもいいじゃん】
「するだろ、あんな写真見たら」
中学時代の友人からメッセージが届いていたので、帰宅してすぐ電話をかけた。
【はい、もしもし】
「もしもし? 今大丈夫?」
【うん。家にいるから。新淵が電話なんて珍しいね。どうしたの?】
あっけらかんとした口調。まるで自分が何をしたのか身に覚えのない様子。
腸が煮えくり返っているが、心を鎮めて冷静に答える。
「そんなのお前が1番わかってるくせに。どういうことか説明しろよ」
だが、怒りは完全に消えず。問い詰めるような言い方に。
電話に出て早々、ドスの利いた声で返答されたら、大半の人は恐怖を抱くか驚くか動揺するだろう。
しかし、このエリートお坊っちゃんは恐ろしいほど肝が据わっているため、一切うろたえることがない。
今も「もしかして妬いてるの〜?」とケラケラ笑っている。
「ふざけるな。こっちは真面目に聞いてるんだぞ」
【わー、こわーい。久しぶりの電話なのに、そんなに嫉妬しなくてもいいじゃん】
「するだろ、あんな写真見たら」