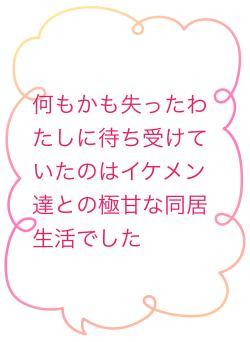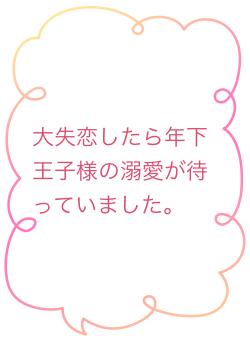ーー
ーーー
『只今より院長の回診が始まりますーー』
ポロロンとチャイムが鳴り、綺麗な女の人の声のアナウンスが病室に響いた。
気持ち悪くなってからどれぐらい時間が経ったのかもわからない。
わたしはぐるぐると気持ち悪い感覚から一向に解放されないまま目を強く閉じて、ただただ耐えていた。
そんなわたしの元へもやって来たらしい院長。
「この人はどうしたのかね?」
「はい。術後、なかなか麻酔が抜けきれないみたいでして」
「そうか。君、元気をだしたまえよ。それじゃあ」
院長らしきひとと誰かの会話をただ耳で拾うのだけで精一杯だったから、院長がどんな顔してる人なのかも確認出来なかった。
ただ、悔しい思いだけがわたしの脳と心に残った。
ーー誰も、
誰もわたしの気持ち悪さを解ってくれない。
それはまるで、あの頃のようで。
誰からも信じてもらえずに「仮病だ」と後ろ指を指されたあの頃のーーー
うっすらと開けた瞳から溢れ出るは、悔し涙。
「っっ」
声も出さず、嗚咽さえ飲み込んでただただ涙だけを流す。
それを見ていたお母さんはハンカチでわたしの涙を優しく拭いながら、
「そんな辛いなら…ウチへ、帰ってくる…?」
そんな言葉をわたしにかけてくれた。