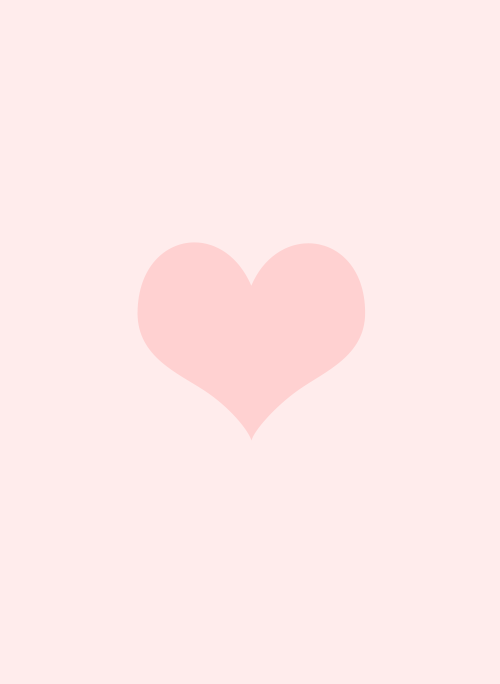嘘はなかった――。
そう言った彼の言葉を信じたい。この指輪を見ていると、本当に嘘はないように思えてくる。私にとって、これが唯一の希望の光になっていた。
「言っちゃ悪いけど、晴日ってさ。大事な時に言葉が足りないよね。」
すると、突然始まった説教。
「え?」
「中学の時、いじめられてた時もそう。きっかけは、ただのとばっちりだったのに、違うってハッキリ言わないから。ズルズルあんな奴らに標的にされちゃって。」
そして、持ち出されたのは、十何年も前の話。
「いつの話してんの....。」
驚き混じりにそう声を漏らし、苦笑いを浮かべると、双葉は私をキッと睨みつけ、頬を膨らませた。
「あれから結局、本質は変わってないよって話。」
テーブルに頬杖をつき、こちらをジッと見つめながら言う。その真剣な眼差しにドキッとさせられ、思わず目を逸らしたくなった。
「お父さんにもそう。千秋さんにもそう。本当は言いたいこと山ほどあるくせに、その言いたいことの半分も言えてない。心の中にとどめて、口に出すとこまでいかないじゃん。」
だんだんと口調が強くなり、昔ヤンチャしていた頃の双葉を見ているようだった。
私は黙り込んだまま何も言えずに、また静かにミルクティーをすする。
正直、言っていることは確信をついている。何一つ、言い返せる気がしなかった。