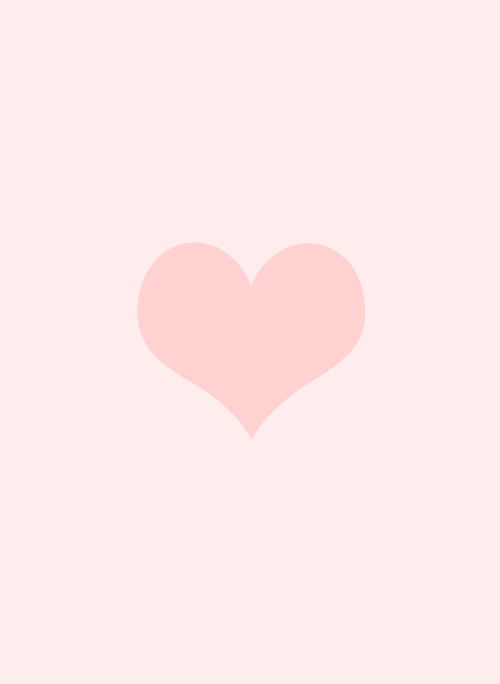「えっと、勘違いさせたならごめん。でも、胡桃ちゃんが思ってるようなことは、何もないから。創くんとはただのお友達っていうか――」
「へー。本当にそうならいいんですけどね。」
しかし、全く信じてくれる様子はない。むしろ何かに火をつけてしまったようで、語尾がだんだんと強くなっていく。
「ちょっと綺麗だからって、7つも年上のおばさん。創さんが相手にするはずないですから、優しくしてくれるからって勘違いしない方がいいですよ。」
続く罵倒に、言い返す気力なんて残っていない。
「恋人もいない、結婚もしてない。30手前で焦ってるからって、学生の恋愛に入り込んでこないでください!」
こんなに感情をむき出しにして、暴言を吐く彼女の姿を、私は初めて見た。息を切らしながら私を睨みつけると、背を向けて去っていく。
しかし、それでも言い足りなかったのか、最後にニコッと笑顔を作ってこちらを振り返った。
「胡桃、子供じみた嫌がらせなんてしませんから。何かあっても、胡桃のことは疑わないでくださいね?」
そう言って、扉を勢いよく閉めていく。
その状況に呆気に取られ、私は放心状態だった。