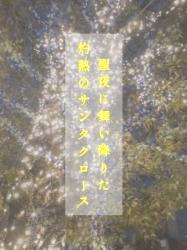否定したのが逆効果だったようで、詩恩は私の腰に腕を回し、さらに距離を縮めてきた。
「まだ疲れが取れないなら……もっと甘くして癒してあげようか」
「わっ……」
首元に顔が近づく。
甘々姿が見てみたいとは思っていたけれど……。
「フフッ……可愛い」
これは刺激が強すぎるよぉぉーー‼
────
──
「し、しおっ、首は……ダメ、だよぉ……」
「…………光野さん、一発背中叩いてやってくれない?」
「えっ、いいの?」
「そろそろ現実に引き戻してあげないと可哀想でしょ?」
机に突っ伏して寝言を呟く明莉を真顔で見る。
「詩恩くんってば冷た~い。せっかく自分の夢見てくれてるのにぃ~。嬉しくないの?」
「嬉しくない。お願い光野さん、俺だと力加減がわからないから早く起こしてあげて」
「わ、わかった……」
トイレに行っている間に爆睡したかと思えば。
これ以上こんな恥ずかしい寝言を聞いてられるか。
光野さんに背中を叩かれて目を覚まし、現実に引き戻された明莉は、目をまん丸にしてキョロキョロし始めた。
うわぁ、ものすごく残念そうな顔。
まったく……次のデートは手を繋いであげますか。
「まだ疲れが取れないなら……もっと甘くして癒してあげようか」
「わっ……」
首元に顔が近づく。
甘々姿が見てみたいとは思っていたけれど……。
「フフッ……可愛い」
これは刺激が強すぎるよぉぉーー‼
────
──
「し、しおっ、首は……ダメ、だよぉ……」
「…………光野さん、一発背中叩いてやってくれない?」
「えっ、いいの?」
「そろそろ現実に引き戻してあげないと可哀想でしょ?」
机に突っ伏して寝言を呟く明莉を真顔で見る。
「詩恩くんってば冷た~い。せっかく自分の夢見てくれてるのにぃ~。嬉しくないの?」
「嬉しくない。お願い光野さん、俺だと力加減がわからないから早く起こしてあげて」
「わ、わかった……」
トイレに行っている間に爆睡したかと思えば。
これ以上こんな恥ずかしい寝言を聞いてられるか。
光野さんに背中を叩かれて目を覚まし、現実に引き戻された明莉は、目をまん丸にしてキョロキョロし始めた。
うわぁ、ものすごく残念そうな顔。
まったく……次のデートは手を繋いであげますか。