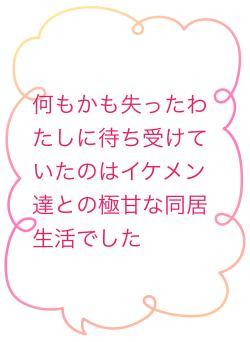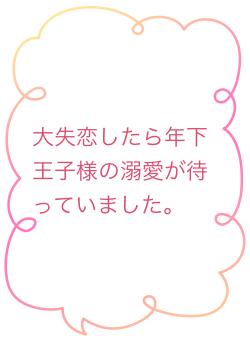「言っただろう、見ていたと」
心地よく耳に響く声にとろけてしまいそうだ。
「痛くて、厳しくて、辛くて。決まりきったそんなレールの上も、お前と一緒ならどこまでも歩いて行けそうな気がするんだ」
「…え?」
思いがけなくかけられた言葉に、パッと顔を上げると真剣な眼をした碧がジッとわたしを見ていて。
「あ…」
視線が交わった瞬間。
その切れ長の漆黒の眼に捕らわれた。
もう、わたしはこの人から逃げられない。
そう、確信した。
碧はわたしを捕らえたままどんどんその距離を縮めて、唇と唇が重なーーー
ドサッッッ!!!!!
何か荷物が床に落ちた音がして
ハッと我に返り、音のした方を見やると
そこにはまるでこの世の終わりを目撃したような表情でわなわなと震えている朔がいて。
キッ…
「「キャァァァアアアアッッッ!!!」」
双子らしく、見事な程に叫び声が重なった。