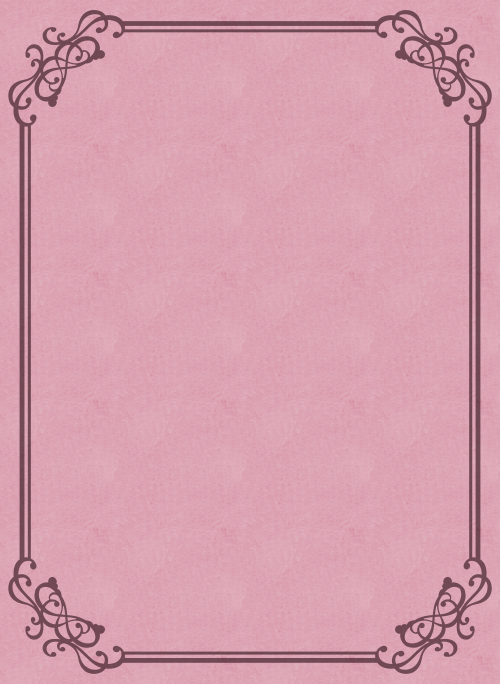足を止めたヴィルヘルムは、深々とため息をついた。
(私、今、ヴィルヘルム様を怒らせるようなことを言ってしまった?)
自分でやるとは言わず、ヴィルヘルムの助けを借りた方がよかっただろうか。
――でも。
いつまでも、父やヴィルヘルムの庇(ひ)護(ご)のもとにいることもできない。それでは、レオンティーナの望む未来には到達できないのだ。
「君は、そうやって自分ひとりで抱え込もうとする。それに、いつだって俺より先を見据えているんだよな」
「そ、そんなこと……」
こちらを見るヴィルヘルムは、まぶしそうに目を細めた。
その表情にまた、鼓動が跳ねる。
ヴィルヘルムは気づいているだろうか。彼と一緒にいる時は、レオンティーナは、大公家の娘であるという立場も、ヴァスロア帝国一の才女と呼ばれる立場であることも忘れてしまうということを。
「もし、ヴィルヘルム様の助けが必要になったら、真っ先に相談させていただきます」
「……ひとつだけ、いいかな」
「なんでしょう?」
(私、今、ヴィルヘルム様を怒らせるようなことを言ってしまった?)
自分でやるとは言わず、ヴィルヘルムの助けを借りた方がよかっただろうか。
――でも。
いつまでも、父やヴィルヘルムの庇(ひ)護(ご)のもとにいることもできない。それでは、レオンティーナの望む未来には到達できないのだ。
「君は、そうやって自分ひとりで抱え込もうとする。それに、いつだって俺より先を見据えているんだよな」
「そ、そんなこと……」
こちらを見るヴィルヘルムは、まぶしそうに目を細めた。
その表情にまた、鼓動が跳ねる。
ヴィルヘルムは気づいているだろうか。彼と一緒にいる時は、レオンティーナは、大公家の娘であるという立場も、ヴァスロア帝国一の才女と呼ばれる立場であることも忘れてしまうということを。
「もし、ヴィルヘルム様の助けが必要になったら、真っ先に相談させていただきます」
「……ひとつだけ、いいかな」
「なんでしょう?」