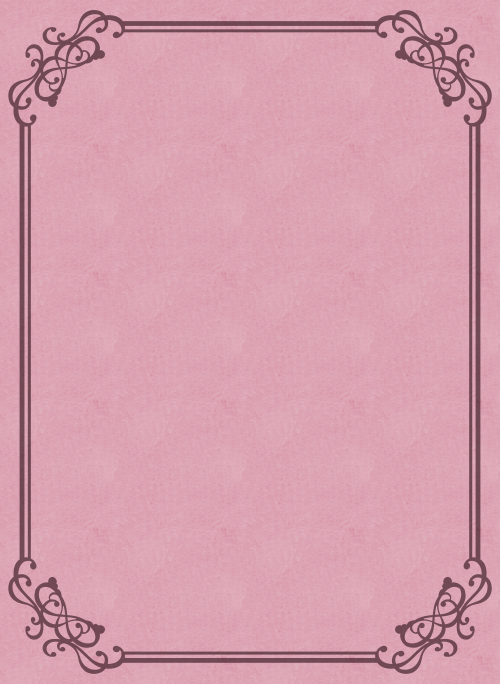「レオンティーナ、結婚祝いにはあなたが刺繍した室内履きをちょうだい。ふたり分よ!」
「ルイーザ、お前……浮かれ過ぎだぞ」
「いいじゃないの、お兄様。私、陛下をメロメロにしてみせるわ!」
メロメロって、そんな言葉をどこで覚えてきたのだろう。
だが、ルイーザのやる気をそぐのも気が咎(とが)めて、刺繍した室内履きをふたり分、と心の中に記憶する。
「……では、交渉はうまくいったというわけですね」
ルイーザが落ち着きを取り戻すのを待ち、茶の席へと場所を移す。ルイーザの侍女とソニアが給仕にあたってくれた。
「ああ。大公家の娘ではなく、皇女というところでファブリスの気持ちを動かすことができたようだな」
ファブリスの名を呼ぶヴィルヘルムの声音が、以前とは少し変わっている気がする。
この国で顔を合わせた時には、彼のことを警戒していたのに。
「……でしょ? だから、私が行くと言ったのよ。ティーポットで頭を殴ろうとしていた私で、気の毒な気もするけれど」
くすりと笑い、ルイーザは紅茶のカップに角砂糖を入れた。
あの時、ルイーザはファブリスとレオンティーナをあえてふたりきりにした。
「ルイーザ、お前……浮かれ過ぎだぞ」
「いいじゃないの、お兄様。私、陛下をメロメロにしてみせるわ!」
メロメロって、そんな言葉をどこで覚えてきたのだろう。
だが、ルイーザのやる気をそぐのも気が咎(とが)めて、刺繍した室内履きをふたり分、と心の中に記憶する。
「……では、交渉はうまくいったというわけですね」
ルイーザが落ち着きを取り戻すのを待ち、茶の席へと場所を移す。ルイーザの侍女とソニアが給仕にあたってくれた。
「ああ。大公家の娘ではなく、皇女というところでファブリスの気持ちを動かすことができたようだな」
ファブリスの名を呼ぶヴィルヘルムの声音が、以前とは少し変わっている気がする。
この国で顔を合わせた時には、彼のことを警戒していたのに。
「……でしょ? だから、私が行くと言ったのよ。ティーポットで頭を殴ろうとしていた私で、気の毒な気もするけれど」
くすりと笑い、ルイーザは紅茶のカップに角砂糖を入れた。
あの時、ルイーザはファブリスとレオンティーナをあえてふたりきりにした。