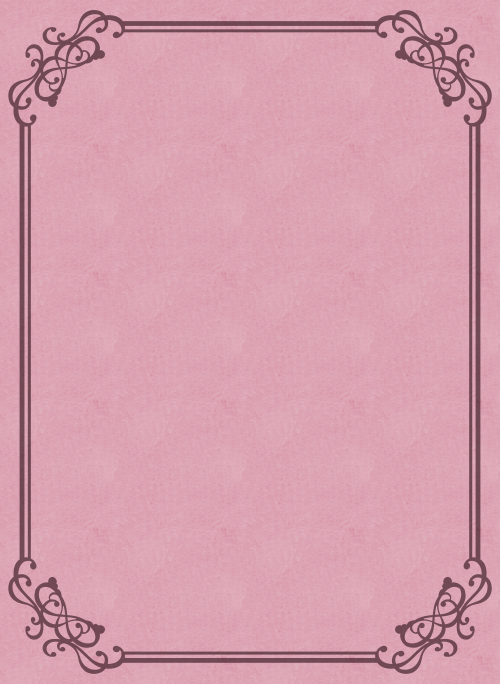「お前、ずっと俺を見ていただろう」
「そ、そうだったでしょうか……?」
じろじろと見つめるような無作法はしていなかったつもりだが、ファブリスのことを気にしていたのは否定できない。
「そんなつもりはなかったのですが……ご無礼を働いていたのであれば申し訳ありません」
くるりと回されながら、謝罪の言葉を口にすると、彼はくっと唇の端を上げて笑う。
「俺が言いたいのは、そういうことじゃない。お前は、俺に興味があるんだろう」
「そ、そういうわけでは……いえ、あの」
どうしてだろう。普段なら、もう少しまともな社交上の言葉が出てくるのに。
ファブリスを見ていると、頭が真っ白になってしまって、何も言うことができなくなるのだ。
「……俺は、お前に興味があるぞ。レオンティーナ・バルダート」
「わ、私のことを……ご存じなんですか?」
今回の人生では、ファブリスとは初対面だ。だが、彼はレオンティーナを知っているようだった。
「お前に興味があると言っただろう。お前について調べるくらいのことはするさ。お前を自分の目で確認したくて、ここに来たんだからな」
「そ、そうだったでしょうか……?」
じろじろと見つめるような無作法はしていなかったつもりだが、ファブリスのことを気にしていたのは否定できない。
「そんなつもりはなかったのですが……ご無礼を働いていたのであれば申し訳ありません」
くるりと回されながら、謝罪の言葉を口にすると、彼はくっと唇の端を上げて笑う。
「俺が言いたいのは、そういうことじゃない。お前は、俺に興味があるんだろう」
「そ、そういうわけでは……いえ、あの」
どうしてだろう。普段なら、もう少しまともな社交上の言葉が出てくるのに。
ファブリスを見ていると、頭が真っ白になってしまって、何も言うことができなくなるのだ。
「……俺は、お前に興味があるぞ。レオンティーナ・バルダート」
「わ、私のことを……ご存じなんですか?」
今回の人生では、ファブリスとは初対面だ。だが、彼はレオンティーナを知っているようだった。
「お前に興味があると言っただろう。お前について調べるくらいのことはするさ。お前を自分の目で確認したくて、ここに来たんだからな」