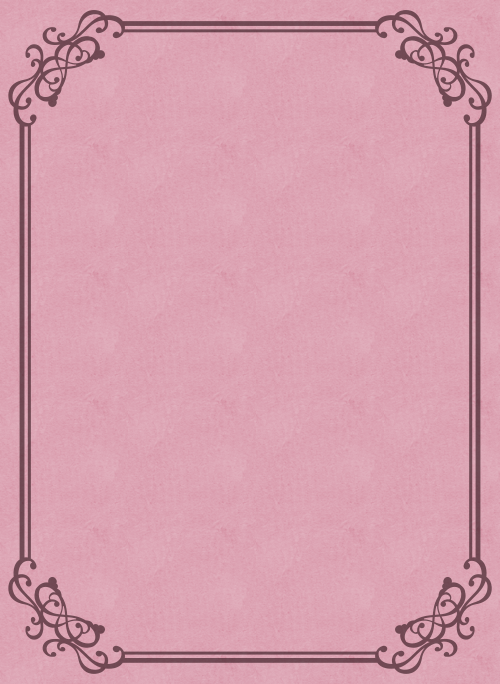あまりのことに声が出ない。そのままぐっと後ろに倒され、気がついた時には冷たい地面が背中に触れていた。
両腕は、アイリーシャを押し倒した人間の膝に押さえつけられていて、身動きひとつできない。
恐怖のあまり、目はぎゅっと閉じたままだった。首に刃の感触が触れ、ちりっとした痛みが首に走る。
「こんなところで"隠密"を使うとは怪しいやつ。どこの間者だ?」
耳を打つのは、低い声。
その声には聞き覚えがある。つい先ほど、少女達に囲まれ、不愛想に返していた声だ。
(……王太子殿下?)
――けれど、なぜ。
今日の主役である王太子がここにいるのだろう。
「――姿を見せろ」
首に押しつけられた刃の感触が、ますます強くなる。
どうして、なぜ。
頭の中で、ぐるぐるとその言葉が回る。
「――姿を見せられないというのなら……」
「いぃぃっぃやぁぁぁぁぁぁぁっ!」
もう少しだけ、首に当てられた剣に力がこめられるのと、アイリーシャの唇から激しい悲鳴が上がったのは同時だった。
両腕は、アイリーシャを押し倒した人間の膝に押さえつけられていて、身動きひとつできない。
恐怖のあまり、目はぎゅっと閉じたままだった。首に刃の感触が触れ、ちりっとした痛みが首に走る。
「こんなところで"隠密"を使うとは怪しいやつ。どこの間者だ?」
耳を打つのは、低い声。
その声には聞き覚えがある。つい先ほど、少女達に囲まれ、不愛想に返していた声だ。
(……王太子殿下?)
――けれど、なぜ。
今日の主役である王太子がここにいるのだろう。
「――姿を見せろ」
首に押しつけられた刃の感触が、ますます強くなる。
どうして、なぜ。
頭の中で、ぐるぐるとその言葉が回る。
「――姿を見せられないというのなら……」
「いぃぃっぃやぁぁぁぁぁぁぁっ!」
もう少しだけ、首に当てられた剣に力がこめられるのと、アイリーシャの唇から激しい悲鳴が上がったのは同時だった。