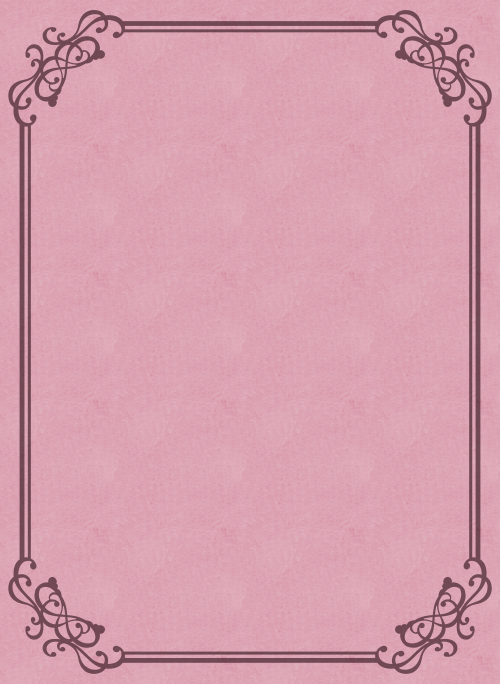アイリーシャ自身の記憶と、それをどこか他人事のように観察している愛美の記憶が、瞬時にして交錯する。
「神様の嘘つきぃぃぃ! "玉"に転生させてくれるって言ってたのにぃぃぃぃぃ!」
さらに毒づこうとした時、部屋の扉がバァンッと勢いよく開かれた。
「リーシャ、何があったの?」
寝間着のまま飛び込んできたのは、アイリーシャの母、シュタッドミュラー公爵夫人であった。十八で嫁ぎ、立て続けに三人の男児を出産、最後にアイリーシャを出産したのだが、四人の子持ちとは思えないほっそりとした美女だ。
まだ寝ぐせがついたままの銀色の髪はぼさぼさだが、二十年後のアイリーシャはこうなっているであろうと想像できる。
「あ、えっと……その、その……」
うろうろとアイリーシャは視線を巡らせる。けれど、母はアイリーシャを逃がしはしなかった。
「何があったの? お母様に言ってごらんなさい」
「……お腹、空いた」
考えあぐねた末、そんな言葉がこぼれ出た。別に、空腹なんて感じてない。
「神様の嘘つきぃぃぃ! "玉"に転生させてくれるって言ってたのにぃぃぃぃぃ!」
さらに毒づこうとした時、部屋の扉がバァンッと勢いよく開かれた。
「リーシャ、何があったの?」
寝間着のまま飛び込んできたのは、アイリーシャの母、シュタッドミュラー公爵夫人であった。十八で嫁ぎ、立て続けに三人の男児を出産、最後にアイリーシャを出産したのだが、四人の子持ちとは思えないほっそりとした美女だ。
まだ寝ぐせがついたままの銀色の髪はぼさぼさだが、二十年後のアイリーシャはこうなっているであろうと想像できる。
「あ、えっと……その、その……」
うろうろとアイリーシャは視線を巡らせる。けれど、母はアイリーシャを逃がしはしなかった。
「何があったの? お母様に言ってごらんなさい」
「……お腹、空いた」
考えあぐねた末、そんな言葉がこぼれ出た。別に、空腹なんて感じてない。