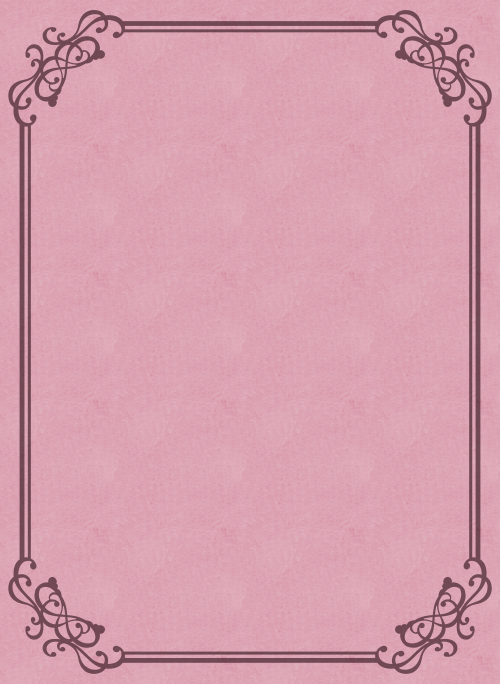天花寺家と縁を繋ぎたい人間はたくさんいる。愛美の配偶者の席を求めて、多数の男性に囲まれるのもいつものことだった。
両親にとって、愛美は天花寺家をより反映させるための道具でしかなかったのである。
「まあ、アイリーシャ様。お綺麗になって……!」
「将来が楽しみなの。娘って、こんなにも可愛いとは思ってもいなかったわ」
母と手を繋いで庭に出ると、さっそく多数の女性に囲まれた。母の友人、それから母と縁を繋ぎたい人達だ。
「今度、我が家にもいらしてくださいね」
「アイリーシャ様なら、縁談はよりどりみどりでしょうね。お年頃になるのが楽しみだわ。私の親戚にちょうどいい年回りの子がいますから、ぜひ」
でも――とちらり、と母の顔を見上げてみる。
前世の母は、こういった時すぐに愛美の売り込みにかかっていた。でも、今回の人生の母は違う。
「娘には、幸せになってもらえればそれでいいの。家のために結婚だなんて、古い概念だわ」
「公爵夫人のところは、熱烈に愛し合っての結婚ですものね」
そうか、両親は恋愛結婚だったのか。
両親にとって、愛美は天花寺家をより反映させるための道具でしかなかったのである。
「まあ、アイリーシャ様。お綺麗になって……!」
「将来が楽しみなの。娘って、こんなにも可愛いとは思ってもいなかったわ」
母と手を繋いで庭に出ると、さっそく多数の女性に囲まれた。母の友人、それから母と縁を繋ぎたい人達だ。
「今度、我が家にもいらしてくださいね」
「アイリーシャ様なら、縁談はよりどりみどりでしょうね。お年頃になるのが楽しみだわ。私の親戚にちょうどいい年回りの子がいますから、ぜひ」
でも――とちらり、と母の顔を見上げてみる。
前世の母は、こういった時すぐに愛美の売り込みにかかっていた。でも、今回の人生の母は違う。
「娘には、幸せになってもらえればそれでいいの。家のために結婚だなんて、古い概念だわ」
「公爵夫人のところは、熱烈に愛し合っての結婚ですものね」
そうか、両親は恋愛結婚だったのか。