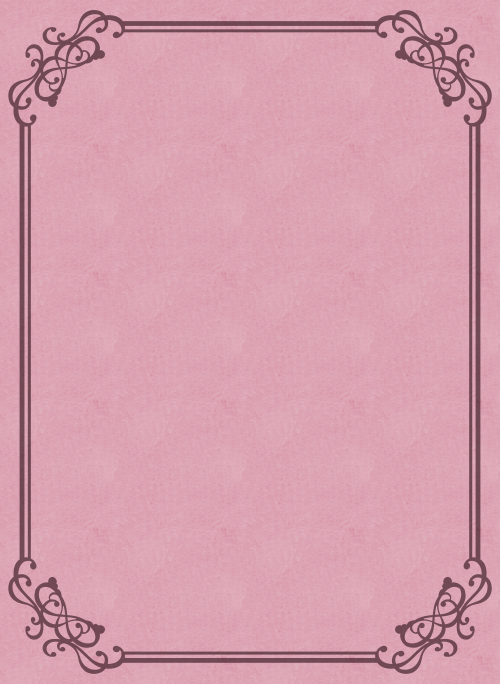「……殿下とあなたの関係です」
それは、胸にナイフを突き立てられたようなものだった。
エドアルトとアイリーシャの関係が、他の女性達とは少し違うのにはとっくの昔に気づいていた。
他の女性には冷たいエドアルトの表情が、アイリーシャを見る時は、ほんの少し、ほんの少しだけど柔らかくなる。
目つきの鋭さだってそうなるといくぶん緩和されて――それに、彼の心根には、他者に対する思いやりだってある。
倒れていたアデルを見つけた時には、迷うことなく自分のマントを差し出し、応急処置を施していた。
(――たぶん)
彼のあの対応は、余計な期待はさせまいというところからきているのだろう。王太子という立場上、特定の女性と親しくするのは好ましくない。
もし、期待させてしまったら、大変な事態を引き起こしかねない。彼の縁談というのは、彼の一存では決められないだろうから。
「アイリーシャ様」
気がついた時には、師匠の前ですっかり自らの思考に沈み込んでしまっていた。慌ててアイリーシャは居住まいを正す。
「ごめんなさい、ミカル先生。少し、ぼうっとしてしまいました」
それは、胸にナイフを突き立てられたようなものだった。
エドアルトとアイリーシャの関係が、他の女性達とは少し違うのにはとっくの昔に気づいていた。
他の女性には冷たいエドアルトの表情が、アイリーシャを見る時は、ほんの少し、ほんの少しだけど柔らかくなる。
目つきの鋭さだってそうなるといくぶん緩和されて――それに、彼の心根には、他者に対する思いやりだってある。
倒れていたアデルを見つけた時には、迷うことなく自分のマントを差し出し、応急処置を施していた。
(――たぶん)
彼のあの対応は、余計な期待はさせまいというところからきているのだろう。王太子という立場上、特定の女性と親しくするのは好ましくない。
もし、期待させてしまったら、大変な事態を引き起こしかねない。彼の縁談というのは、彼の一存では決められないだろうから。
「アイリーシャ様」
気がついた時には、師匠の前ですっかり自らの思考に沈み込んでしまっていた。慌ててアイリーシャは居住まいを正す。
「ごめんなさい、ミカル先生。少し、ぼうっとしてしまいました」