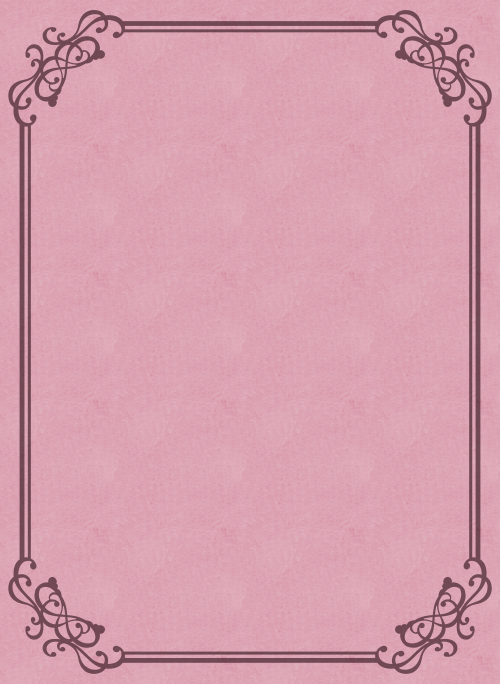完璧に存在を消すならともかく、目立たなくする程度ならお目こぼししてもらえる。そう言う自分の顔がまたひきつっているような気がして、視線をそらした。
「――馬車まで送る」
これ以上、近づいたら。
余計なことを口にしてしまいそう。胸が痛むのは、気のせいではない。
それなのに、差し出された手は優しくて、その手を拒むことなんてできなかった。
◇ ◇ ◇
「――まったく、ひどい話じゃない?」
ミリアムは憤慨していた。アイリーシャとヴァレリアが廊下でやり合ったという話は、あっという間に王宮中を駆け巡ったそうだ。
あんなことがあったのは、昨日だというのに、もう王妃の耳にまで届いていた。
「私達が親しくしているのは王妃様もご存じだから、あなたの様子を見てくるようにと言われたのよ」
王妃からの差し入れを差し出しながら、ダリアが気づかわし気な目をこちらに向ける。友人達だけではなく、王妃にまで心配をかけていると思うと申し訳なさが募る。
「――馬車まで送る」
これ以上、近づいたら。
余計なことを口にしてしまいそう。胸が痛むのは、気のせいではない。
それなのに、差し出された手は優しくて、その手を拒むことなんてできなかった。
◇ ◇ ◇
「――まったく、ひどい話じゃない?」
ミリアムは憤慨していた。アイリーシャとヴァレリアが廊下でやり合ったという話は、あっという間に王宮中を駆け巡ったそうだ。
あんなことがあったのは、昨日だというのに、もう王妃の耳にまで届いていた。
「私達が親しくしているのは王妃様もご存じだから、あなたの様子を見てくるようにと言われたのよ」
王妃からの差し入れを差し出しながら、ダリアが気づかわし気な目をこちらに向ける。友人達だけではなく、王妃にまで心配をかけていると思うと申し訳なさが募る。