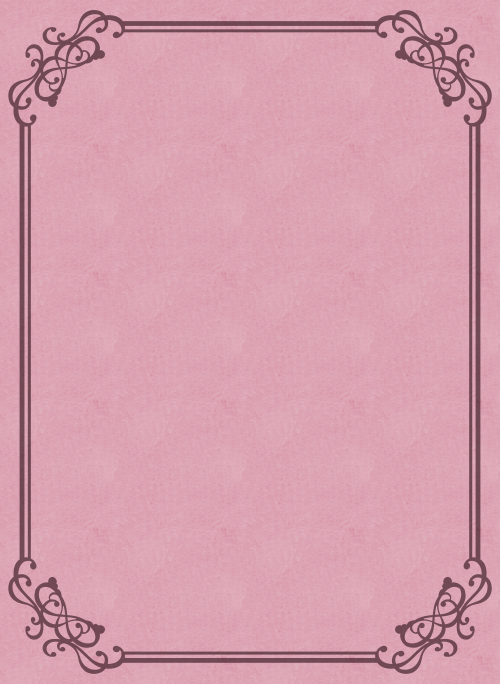「赤い首輪をつけた犬なんて、世の中にはたくさんいる。そう言いたいのかしら? でも、貴族の屋敷の中、寝室でも見かけられているのよ。そんなところまで入り込むのだもの。悪魔の力が働いているのではなくて?」
「――それは、ルルが、"聖獣"の血を引いているからで……!」
「あら、そんなのあなたが勝手に言っているだけでしょう。聖獣の血を引いているか否かなんて、私達にはわからないもの」
他の娘達の前で、アイリーシャに対して優位に振る舞えるのが、そんなにも嬉しいのだろうか。彼女の唇は、とまることを知らなかった。
(何も知らないくせに……!)
頭がかっと熱くなっていくのとは対照的に、手の方は少しずつ冷たくなってくる。
初対面の時から、たしかにヴァレリアの印象は悪かった。仲良くなれないだろうなとも思っていた。
だが、お互い家を背負っている身だ。人前で相手を貶めるような真似だけはすまいと思っていた。
けれど、そのアイリーシャの想いは、一方通行でしかなかったらしい。
黙り込んでしまったアイリーシャの前で、ヴァレリアはなおも続けた。
「――それは、ルルが、"聖獣"の血を引いているからで……!」
「あら、そんなのあなたが勝手に言っているだけでしょう。聖獣の血を引いているか否かなんて、私達にはわからないもの」
他の娘達の前で、アイリーシャに対して優位に振る舞えるのが、そんなにも嬉しいのだろうか。彼女の唇は、とまることを知らなかった。
(何も知らないくせに……!)
頭がかっと熱くなっていくのとは対照的に、手の方は少しずつ冷たくなってくる。
初対面の時から、たしかにヴァレリアの印象は悪かった。仲良くなれないだろうなとも思っていた。
だが、お互い家を背負っている身だ。人前で相手を貶めるような真似だけはすまいと思っていた。
けれど、そのアイリーシャの想いは、一方通行でしかなかったらしい。
黙り込んでしまったアイリーシャの前で、ヴァレリアはなおも続けた。