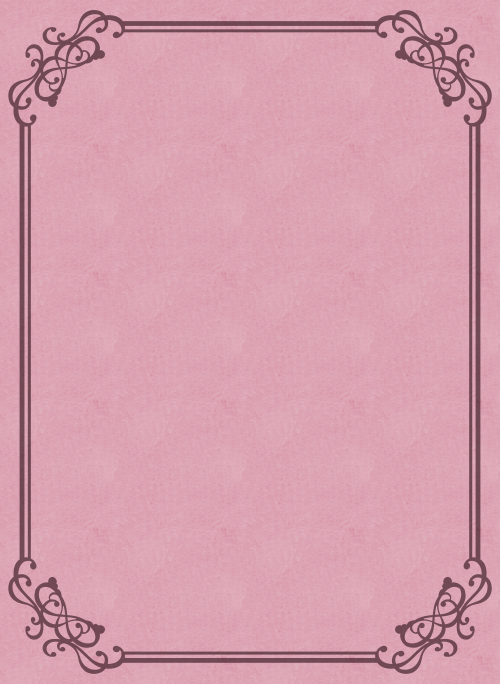アイリーシャは青ざめた。この屋敷で暮らしている犬はルルだけだ。そして、今の鳴き声は、間違いなく家の中からではない。
(また、脱走しちゃったの……!)
さっき、言い聞かせたばかりだというのに、まったく通じていなかっただろうか。
だが、あの鳴き声はただ事ではない。
「殿下、申し訳ないのですが」
「わかった。俺も行く」
違う、そうではない。
もう馬車のすぐ近くまで来ているのだから、このまま乗ってもらってよかったのに。
というか、次の予定があったのではないだろうか。
だが、アイリーシャが口を挟む前にエドアルトは身をひるがえしている。
ルルの首輪と対になる水晶は、部屋に置いてきてしまっていたけれど、これだけ激しく鳴き声が聞こえてくるのだからそちらに行けば問題ない。
「犬を飼い始めたと、ノルヴェルトが言っていたが、その犬か。どれだけ閉じ込めても逃げ出してしまう、と」
「そうなんです。ミカル先生にお願いして、探すための装置を作ることになりました」
声の方に大急ぎで向かう。
(また、脱走しちゃったの……!)
さっき、言い聞かせたばかりだというのに、まったく通じていなかっただろうか。
だが、あの鳴き声はただ事ではない。
「殿下、申し訳ないのですが」
「わかった。俺も行く」
違う、そうではない。
もう馬車のすぐ近くまで来ているのだから、このまま乗ってもらってよかったのに。
というか、次の予定があったのではないだろうか。
だが、アイリーシャが口を挟む前にエドアルトは身をひるがえしている。
ルルの首輪と対になる水晶は、部屋に置いてきてしまっていたけれど、これだけ激しく鳴き声が聞こえてくるのだからそちらに行けば問題ない。
「犬を飼い始めたと、ノルヴェルトが言っていたが、その犬か。どれだけ閉じ込めても逃げ出してしまう、と」
「そうなんです。ミカル先生にお願いして、探すための装置を作ることになりました」
声の方に大急ぎで向かう。