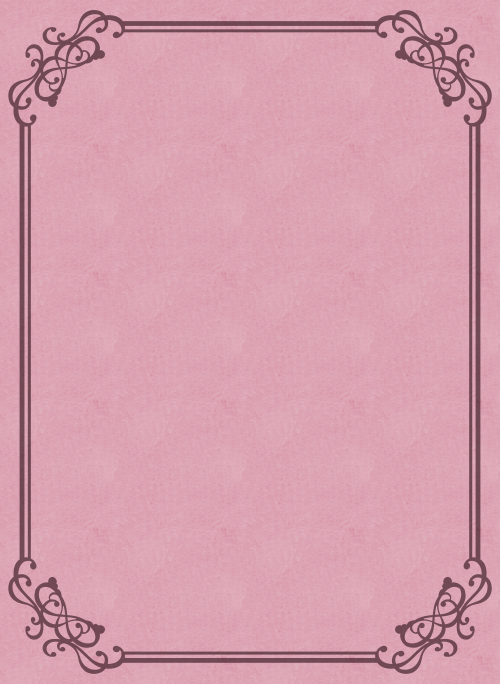『シュタッドミュラー家とフォンタナ家、殿下はどちらにつくのかしら』
『あの様子からすると、アイリーシャ様優位ではない?』
『いえ、ヴァレリア様は十年の間、殿下の側におられたのよ?』
なんて会話が交わされているのだろう。そんなことくらい、容易に想像がつくというものだ。
(……殿下には申し訳ないけれど)
エドアルトと一緒に歩いているけれど、つい、一歩引いてしまう。周囲の人の目が、どうしても気になるのだ。
できることなら、この場から逃走したいくらいだ。
一歩前を行くエドアルトは、アイリーシャの内面なんて知るはずもない。肩越しにこちらを振り返る。
(笑ってる、のかな……?)
ほんの少し、口角が上がっているように見えるのは気のせいだろうか。先ほどまでの氷っぷりを見ていたら、気のせいのような気もする。
「王宮には慣れたか?」
「……なんとか」
周囲の人達の目が向いているのがわかるから、アイリーシャの対応もつい、それなりになる。エドアルトは、アイリーシャのぶしつけともいえる対応をさほど気にしていないようだった。
(……困る、な)
本当、こういうのは困る。
『あの様子からすると、アイリーシャ様優位ではない?』
『いえ、ヴァレリア様は十年の間、殿下の側におられたのよ?』
なんて会話が交わされているのだろう。そんなことくらい、容易に想像がつくというものだ。
(……殿下には申し訳ないけれど)
エドアルトと一緒に歩いているけれど、つい、一歩引いてしまう。周囲の人の目が、どうしても気になるのだ。
できることなら、この場から逃走したいくらいだ。
一歩前を行くエドアルトは、アイリーシャの内面なんて知るはずもない。肩越しにこちらを振り返る。
(笑ってる、のかな……?)
ほんの少し、口角が上がっているように見えるのは気のせいだろうか。先ほどまでの氷っぷりを見ていたら、気のせいのような気もする。
「王宮には慣れたか?」
「……なんとか」
周囲の人達の目が向いているのがわかるから、アイリーシャの対応もつい、それなりになる。エドアルトは、アイリーシャのぶしつけともいえる対応をさほど気にしていないようだった。
(……困る、な)
本当、こういうのは困る。