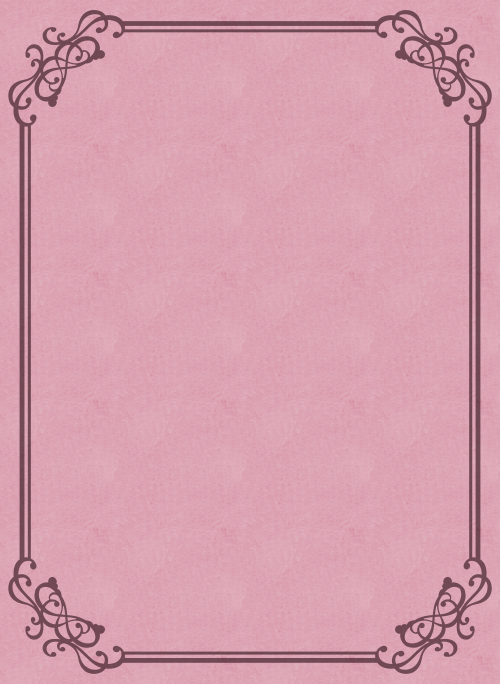ただ、ひとつ、問題があるとすれば、馬車を汚してしまうということだろうか。
赤い舌をのぞかせながら、子犬はぱたぱたと尾を振り続けている。可愛らしいが、馬車に同乗させるには、あまりにも汚れすぎている。
「どうやって連れて帰ろうかしら……」
「タオルでくるめば馬車を汚さないですむんじゃないか?」
「あ、そうですね。そうします」
あまり頑固にエドアルトの提案を断るのもどうかと思ったので、おとなしく送ってもらう。
馬車には大きなタオルもあって、それですっぽりと子犬をくるむ。エドアルトに別れを告げようとしたら、彼はアイリーシャが抱いている犬の顔を真正面からのぞき込んだ。
ばたばたとまた尾が揺れて、エドアルトの鼻の先が舐められる。彼が顔をしかめたので、思わずくすりと笑ってしまった。
「何がおかしい?」
「いえ――そういう顔もするんだと思って。殿下は、あまり表情を変えないようにしてらっしゃるでしょう?」
かつて、アイリーシャもそうだったからわかる。日本で暮らしていた頃、天花寺愛美と呼ばれていた時代。
赤い舌をのぞかせながら、子犬はぱたぱたと尾を振り続けている。可愛らしいが、馬車に同乗させるには、あまりにも汚れすぎている。
「どうやって連れて帰ろうかしら……」
「タオルでくるめば馬車を汚さないですむんじゃないか?」
「あ、そうですね。そうします」
あまり頑固にエドアルトの提案を断るのもどうかと思ったので、おとなしく送ってもらう。
馬車には大きなタオルもあって、それですっぽりと子犬をくるむ。エドアルトに別れを告げようとしたら、彼はアイリーシャが抱いている犬の顔を真正面からのぞき込んだ。
ばたばたとまた尾が揺れて、エドアルトの鼻の先が舐められる。彼が顔をしかめたので、思わずくすりと笑ってしまった。
「何がおかしい?」
「いえ――そういう顔もするんだと思って。殿下は、あまり表情を変えないようにしてらっしゃるでしょう?」
かつて、アイリーシャもそうだったからわかる。日本で暮らしていた頃、天花寺愛美と呼ばれていた時代。