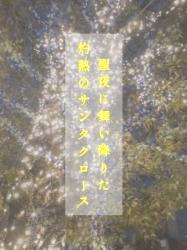放たれた言葉を耳にした瞬間、ゴンと頭を鈍器で殴られたような感覚がした。
突然の発言に頭が追いつかず、脳内がグラグラぐるぐる揺れて、軽くパニックを引き起こしている。
「私……智恵理さんに酷いことをしてきました。本当にごめんなさい」
「っ……」
一向に顔を上げない彼女。
その下の地面には小さなシミができている。
それが涙の跡だとわかると、一気に感情が込み上げてきて、ギュッと拳を握った。
『そのアザどうしたの……?』
『あぁ、部活で転んでできちゃった』
『マジで? そんなにたくさん?』
『マジ。運動部はこういうのよくあるんだよ』
『姉ちゃん、これ廊下に落ちてた』
『あっ……ありがと』
『……運動部ってそんなにサポーター要るんだね』
『あー……まぁね。私は毎日練習してるからすぐボロボロになっちゃうの』
「ふざけんな……っ、なんで……なんで今更なんだよ‼」
「……ごめんなさい……っ!」
姉とのやり取りが走馬灯のように甦ってきて──気づいたら俺は彼女の両肩を掴んでいた。