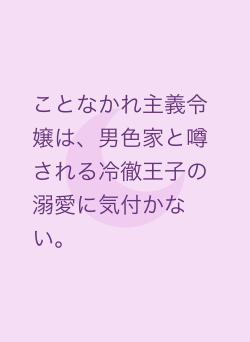旭君は、私の手首を掴んでいた手を離す。
「ひまり」
それから、優しく私の名前を呼んで、
「痛っ」
両方の頬っぺたを摘んで軽く左右に引っ張った。
「ちょ、旭君っ」
「バーカ」
今度は反対に、手の平で挟んでムニュッと押し潰す。
「ひ、酷っ」
「アホ」
「ア、アホ?」
「考え過ぎ」
「だ、だって…」
「つか、俺らレベル一緒だからな」
旭君は頬っぺたから手を離すと、優しく目を細めた。
「変なこと考えてんじゃねぇよ」
「旭君…」
「俺らは一緒なの。普通でいんだよ」
「でも、私…」
「ひまり」
「はい」
「す」
「す?」
「好き、です」
さっきまで飄々としてた旭君が、クシャッと顔をしかめる。
「こっちだってなぁ、余裕なんかねんだよ。お前のことばっか考えてるし、色々もっと上手く…」
「…」
「知ってんだろ?俺が嘘吐きだってこと。余裕なんかあると思ってんの?」
「…思わない」
「だったら、気にする必要ねぇから。ひまりはひまりらしくしてりゃいーの」
「うん」
「よし」
「旭君」
「ん?」
「ありがとう」
フワッと自然に溢れた笑顔、旭君は目を細めて私を見る。気が付いたら、もうちゃんと旭君の目を見れている私がいて。
胸のドキドキは変わらないんだけど、旭君の少しだけ気持ちが落ち着いた気がする。
「旭君」
「…」
「旭君?」
今度は旭君の様子がおかしい。フイッと顔を逸らして、スタスタと行ってしまった。
「ちょっ、旭君待ってよーっ」
「いいから行くぞ」
「どうしたの急に」
「何もねぇ」
「そんな風に見えないよぉ」
「いーんだよ」
それから旭君に何回聞いても、何も答えてはくれなかった。
「ひまり」
それから、優しく私の名前を呼んで、
「痛っ」
両方の頬っぺたを摘んで軽く左右に引っ張った。
「ちょ、旭君っ」
「バーカ」
今度は反対に、手の平で挟んでムニュッと押し潰す。
「ひ、酷っ」
「アホ」
「ア、アホ?」
「考え過ぎ」
「だ、だって…」
「つか、俺らレベル一緒だからな」
旭君は頬っぺたから手を離すと、優しく目を細めた。
「変なこと考えてんじゃねぇよ」
「旭君…」
「俺らは一緒なの。普通でいんだよ」
「でも、私…」
「ひまり」
「はい」
「す」
「す?」
「好き、です」
さっきまで飄々としてた旭君が、クシャッと顔をしかめる。
「こっちだってなぁ、余裕なんかねんだよ。お前のことばっか考えてるし、色々もっと上手く…」
「…」
「知ってんだろ?俺が嘘吐きだってこと。余裕なんかあると思ってんの?」
「…思わない」
「だったら、気にする必要ねぇから。ひまりはひまりらしくしてりゃいーの」
「うん」
「よし」
「旭君」
「ん?」
「ありがとう」
フワッと自然に溢れた笑顔、旭君は目を細めて私を見る。気が付いたら、もうちゃんと旭君の目を見れている私がいて。
胸のドキドキは変わらないんだけど、旭君の少しだけ気持ちが落ち着いた気がする。
「旭君」
「…」
「旭君?」
今度は旭君の様子がおかしい。フイッと顔を逸らして、スタスタと行ってしまった。
「ちょっ、旭君待ってよーっ」
「いいから行くぞ」
「どうしたの急に」
「何もねぇ」
「そんな風に見えないよぉ」
「いーんだよ」
それから旭君に何回聞いても、何も答えてはくれなかった。