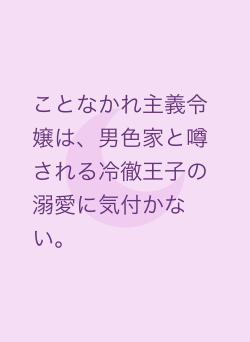「…笑うんじゃねぇよっ」
「ごめん、だって」
「仕方ねーだろ!俺こんな…っ」
旭君はまた前髪をくしゃくしゃにして、手の平で目元を隠す。
「今までずっと、嘘ばっか吐いてた。俺お前見てるとどうしても、逆の言葉しか出てこなくて。嫌な思いさせてるって分かってても、ずっと」
「うん」
「嫌いとか思ったことねぇし、喋んのも、見んのも、お前のことは全部…っ」
「うん」
「だ、だから…っあー、もう何だこれ俺死にそうマジで」
「フフッ」
「だーかーら、笑うなって!」
「だ、だって旭君がそんな風なの初めてなんだもん」
「俺だって初めてだっつの!あーマジで今まで何やってたんだ俺…」
「何って?」
「いや、だから嘘ばっか吐いてっからこんなことに…っ」
「もしかして、そういうの隠したくて天邪鬼ばっかりしてたの?」
「バッカ違…くない…しお前はバカじゃねぇ」
「アハハッ、もうおっかしい」
「だぁー、くそっ」
いつもと全然違う旭君に、私の口角は自然と緩む。飄々としててカッコいい旭君は、今はしどろもどろの可愛い照れ屋さん。
「…悪かった」
旭君は少し下を向いて、視線だけを私に向ける。上目遣いで見られてるみたいで、それだけでドキッとした。
「お前はいままでずっと、素直にちゃんと色々言ってくれてた。なのに俺は自分守ってばっかで、誤魔化して嘘吐いて傷付けて。でも側に居ないと嫌で、理由付けては会いたくて。お前が俺意外の男と話してんのもすげぇ嫌で、家が隣同士っての利用して彼氏ができねぇようにずっと張り付いて」
「…」
「分かってる。俺は最低だってこと。今までずっと、自分のことしか考えてなかった。だからこんな肝心な時に、情けない位カッコつかねーし。どもるし、噛むし、喋れねーし」
「それはまぁ、仕方ないよ」
「これからは、お前にさせてたこと全部俺がする。死にそうに恥ずかしくても、嘘吐いて傷付けたりしねぇ」
「…」
「ひまり」
「っ」
旭君は私の名前を呼ぶと、深く頭を下げた。
「この間のこと、マジでごめん。お前が知ってるとは思わなかったけど、俺はそれ利用してお前と…」
「ちょっと待って」
「は?」
「利用って、何?」
「いやだから、お前守るの口実にして告らず強引に付き合ったってこと」
「守る?何から?」
「クラスのやつら」
「ん、んん?」
旭君は昔から、圧倒的に言葉が足りない。
私が理解してる前提で話が進んでるみたいだけど、ちっとも話が見えてこない。
旭君の雰囲気にドキドキしっぱなしだったけど、その先の言葉に今の私の頭の中はクエスチョンマークでいっぱい。
「ごめん、だって」
「仕方ねーだろ!俺こんな…っ」
旭君はまた前髪をくしゃくしゃにして、手の平で目元を隠す。
「今までずっと、嘘ばっか吐いてた。俺お前見てるとどうしても、逆の言葉しか出てこなくて。嫌な思いさせてるって分かってても、ずっと」
「うん」
「嫌いとか思ったことねぇし、喋んのも、見んのも、お前のことは全部…っ」
「うん」
「だ、だから…っあー、もう何だこれ俺死にそうマジで」
「フフッ」
「だーかーら、笑うなって!」
「だ、だって旭君がそんな風なの初めてなんだもん」
「俺だって初めてだっつの!あーマジで今まで何やってたんだ俺…」
「何って?」
「いや、だから嘘ばっか吐いてっからこんなことに…っ」
「もしかして、そういうの隠したくて天邪鬼ばっかりしてたの?」
「バッカ違…くない…しお前はバカじゃねぇ」
「アハハッ、もうおっかしい」
「だぁー、くそっ」
いつもと全然違う旭君に、私の口角は自然と緩む。飄々としててカッコいい旭君は、今はしどろもどろの可愛い照れ屋さん。
「…悪かった」
旭君は少し下を向いて、視線だけを私に向ける。上目遣いで見られてるみたいで、それだけでドキッとした。
「お前はいままでずっと、素直にちゃんと色々言ってくれてた。なのに俺は自分守ってばっかで、誤魔化して嘘吐いて傷付けて。でも側に居ないと嫌で、理由付けては会いたくて。お前が俺意外の男と話してんのもすげぇ嫌で、家が隣同士っての利用して彼氏ができねぇようにずっと張り付いて」
「…」
「分かってる。俺は最低だってこと。今までずっと、自分のことしか考えてなかった。だからこんな肝心な時に、情けない位カッコつかねーし。どもるし、噛むし、喋れねーし」
「それはまぁ、仕方ないよ」
「これからは、お前にさせてたこと全部俺がする。死にそうに恥ずかしくても、嘘吐いて傷付けたりしねぇ」
「…」
「ひまり」
「っ」
旭君は私の名前を呼ぶと、深く頭を下げた。
「この間のこと、マジでごめん。お前が知ってるとは思わなかったけど、俺はそれ利用してお前と…」
「ちょっと待って」
「は?」
「利用って、何?」
「いやだから、お前守るの口実にして告らず強引に付き合ったってこと」
「守る?何から?」
「クラスのやつら」
「ん、んん?」
旭君は昔から、圧倒的に言葉が足りない。
私が理解してる前提で話が進んでるみたいだけど、ちっとも話が見えてこない。
旭君の雰囲気にドキドキしっぱなしだったけど、その先の言葉に今の私の頭の中はクエスチョンマークでいっぱい。