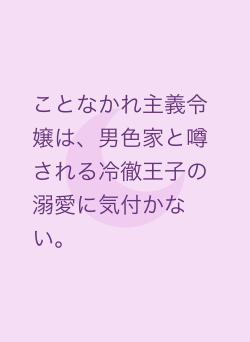目の前でしたって意味ないけど、思わず手櫛で髪の毛を整える。
普段あんまり目を合わせてくれない旭君がこうやってたまに私を見てくれると、もう血液が沸騰してしまうんじゃないかって位体の中全部が熱くなるんだ。
「…こっち」
玄関をチラッと見て、旭君は私の手を軽く引いた。彼が持ってる紙袋がガサッと音を立ててくれたおかげで、私が小さく漏らしてしまった「キャッ」って声は多分聞かれなくて済んだ。
旭君は家の壁と車の間に身を滑らせるようにして、そこに私も引っ張り込む。いつもより距離が近くて、もう本当に心臓が破けそうだ。
「…あの、さ」
「う、うん」
「お前、好きなヤツとかいんの?」
「え!」
思わず大きな声が出て、旭君が一瞬顔をしかめる。
「あ、ご、ごめん。ビックリしちゃって。旭君にそんなこと聞かれると思ってなかったから」
「…」
「好きな人はね…えっと、どうだろう?まだよく分かんないかなぁ?」
いないって嘘は吐きたくなくて、でもいるって答えて誰?って聞かれても困るから曖昧に濁す。
旭君は私の答えに数秒黙ってから、今度は視線を逸らしたまま聞こえるか聞こえないかギリギリの小さな声でボソッと呟いた。
「俺と…付き合う?」
「え…」
「だから…俺と、付き合ってみるかって」
「…」
いつも見てる、怒ったような旭君のしかめっ面。でもこの表情の時は、彼が照れてる証拠だ。
…あぁ、ダメだ。これは夢?なんて漫画みたいなセリフが口から飛び出してきそう。
私は、旭君が大好き。幼馴染みとしても、男の子としても、旭君のことが本当に好き。
だけど、旭君はきっと違う。お隣さんで、ただの友達。そんな風にしか見られてはいないと思ってた。
「あ、あの…」
緊張して、思わず声が震える。こんなことが、本当に起こるなんて…どうしよう、泣きそうだ。
「よ、よろしく…お願いします…っ」
カラカラに乾いた唇を一生懸命動かして、なんとかそれだけ絞り出す。もっと嬉しそうな顔とか、可愛い声とか出したい。でも無理、これ以上はホントに泣いてしまう。
「え…」
一瞬、旭君が戸惑ったような声を出す。
「え…」
まさか…付き合うってどっかの場所に、的な漫画みたいなオチじゃないよね…?
「いや、何でもね」
旭君はよく分からない表情を浮かべて、それから私の体をグイッと押した。
「おら、帰んぞ」
「ほぇ?」
「漫画、サンキュー」
「え?あ、う、うん」
「じゃ、そういうことでよろしく」
「う、うん?」
旭君はやっぱりよく分からない表情のまま、片手だけ挙げて家の中へと入っていってしまった。
残された私は、そのまま暫く機能停止。こういうの、きつねにつままれるっていうんだろうか。
私は、大好きな旭君と彼氏彼女になれた。
…んだよね?
普段あんまり目を合わせてくれない旭君がこうやってたまに私を見てくれると、もう血液が沸騰してしまうんじゃないかって位体の中全部が熱くなるんだ。
「…こっち」
玄関をチラッと見て、旭君は私の手を軽く引いた。彼が持ってる紙袋がガサッと音を立ててくれたおかげで、私が小さく漏らしてしまった「キャッ」って声は多分聞かれなくて済んだ。
旭君は家の壁と車の間に身を滑らせるようにして、そこに私も引っ張り込む。いつもより距離が近くて、もう本当に心臓が破けそうだ。
「…あの、さ」
「う、うん」
「お前、好きなヤツとかいんの?」
「え!」
思わず大きな声が出て、旭君が一瞬顔をしかめる。
「あ、ご、ごめん。ビックリしちゃって。旭君にそんなこと聞かれると思ってなかったから」
「…」
「好きな人はね…えっと、どうだろう?まだよく分かんないかなぁ?」
いないって嘘は吐きたくなくて、でもいるって答えて誰?って聞かれても困るから曖昧に濁す。
旭君は私の答えに数秒黙ってから、今度は視線を逸らしたまま聞こえるか聞こえないかギリギリの小さな声でボソッと呟いた。
「俺と…付き合う?」
「え…」
「だから…俺と、付き合ってみるかって」
「…」
いつも見てる、怒ったような旭君のしかめっ面。でもこの表情の時は、彼が照れてる証拠だ。
…あぁ、ダメだ。これは夢?なんて漫画みたいなセリフが口から飛び出してきそう。
私は、旭君が大好き。幼馴染みとしても、男の子としても、旭君のことが本当に好き。
だけど、旭君はきっと違う。お隣さんで、ただの友達。そんな風にしか見られてはいないと思ってた。
「あ、あの…」
緊張して、思わず声が震える。こんなことが、本当に起こるなんて…どうしよう、泣きそうだ。
「よ、よろしく…お願いします…っ」
カラカラに乾いた唇を一生懸命動かして、なんとかそれだけ絞り出す。もっと嬉しそうな顔とか、可愛い声とか出したい。でも無理、これ以上はホントに泣いてしまう。
「え…」
一瞬、旭君が戸惑ったような声を出す。
「え…」
まさか…付き合うってどっかの場所に、的な漫画みたいなオチじゃないよね…?
「いや、何でもね」
旭君はよく分からない表情を浮かべて、それから私の体をグイッと押した。
「おら、帰んぞ」
「ほぇ?」
「漫画、サンキュー」
「え?あ、う、うん」
「じゃ、そういうことでよろしく」
「う、うん?」
旭君はやっぱりよく分からない表情のまま、片手だけ挙げて家の中へと入っていってしまった。
残された私は、そのまま暫く機能停止。こういうの、きつねにつままれるっていうんだろうか。
私は、大好きな旭君と彼氏彼女になれた。
…んだよね?